2月8日の日経朝刊の一面トップは(電子化でそういう読み方をしていない人も多いだろうが)、農地集約の話。
農地集約が進むような取引を増やすために、政府が取引仲介の支援をするという話。政策目的自体は素晴らしいし、今、これは喫緊の課題だ。私自身もこのための政策は考えており、だからというわけではないが、政策のポイントとしては素晴らしい。
しかし、である。
センスがない。
センスとは何か。
政策が、目的の達成に本当に貢献できるか、その点で、実効性があるか、ということである。
この取引仲介はうまくいかないだろう。
そもそも土地の仲介は難しい。日本では、土地を売ることは隠避すべきことと思われているからである。
なぜ隠避すべきと思われているのか、わからないでもないが、ここでは議論しない。都市部の住宅地ですらそうなのに、誰が農地を売るときにデータベースに提供するだろうか。
土地の取引のコツは、誰にもばれないように買ってあげることである。だからそもそも仲介をはさまないのがコツなのだ。さらすのは最悪。あほすぎる。
農地の問題は、最終的な買い手と売り手の立場やバックグランドが違いすぎて接点がないことだ。だから、仲介というのは短絡的過ぎる。仲介させてもらうにはかなりの信頼を得ないといけない。相続も絡むし、現金も動く。
そのためには、仲介を促進するのではなく、買い手を直接登場させなくてはいけない。売り手と買い手がほかの人になるべく知られずに、あるいは知られてもいいベース、ルート、チャネルで結びつかないといけない。
結びつけるのではなく、結びつかないといけないのである。
やはり、こういうところは、官民一体ではないが、政府の中にいろんな人がいて、自然にアイデアが融合する形を作らないと難しい。現政権の実は一番の弱点である、ブレーンの質、偏りが、こういうところにも出ているが、官僚機構自体も、もっと人材のバックグラウンドが多様化し、流動化しないとセンスのいい政策は打ち出されないだろう。
それが次の政権の課題だ。









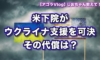



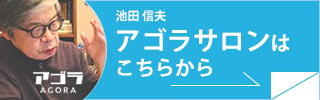
コメント
日経電子版では「農地バンク」取引仲介で新規参入促す”売却、賃貸情報を一元化、TPPにらみ”です。
重要と思われる項目は3点。
1.農地の名義人が連絡が取れない(所在地不明者の大半が外国人)
2.農地ではなく(土)のみを自治体の許認可財として自治体の条例化して、雑草駆除等の施策をして、近隣農地の農作物の発育保護とする。
3.農地として土地の登録をするには国(今は自治体かも知れません)の許可が必要。ただし、これも殆どのケースで許可が下りず、結果として、農協の積立金を利用した農協による土地の転売による価格下落の保護に繋がっています(前回の事業仕分け対象事業)
他にもあると思いますが、気になるトピックを3つ程、挙げさせて貰いました。