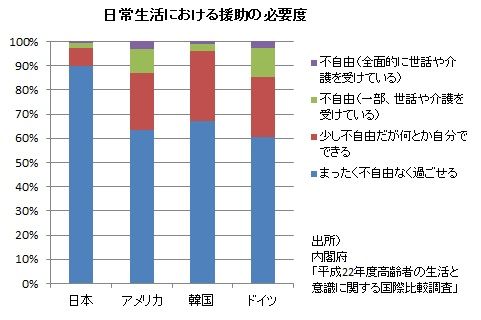行動ファイナンス第三部である。
第三部は、第二部の終わりに述べた、市場のダイナミックス、つまり多様な投資家が行動を取ることにより、お互いの将来の行動の意志決定に影響を与え、それが市場を動かし、動いた市場が再び投資家の意志決定を変え、新たな投資行動となり、それが市場を動かす、このような連鎖が市場である、ということから始まる。
第二部では超合理的な投資家が存在したが、第三部では、存在しても好いのだが、存在しないと考えた方がわかりやすい。超合理的な投資家がいるということは、ダイナミックな問題(動学的な問題)であっても、超合理的な投資家にはバックワードで解けてしまうということだ。これはShleiferらの初期の論文(1990)でも、そうなっている(しかし、依然としてバブルの構造を端的に示したモデル(算数的にはちゃちだが)としては最も現実を的確に捉えているものである)。
しかし、これでは、問題はダイナミックでありながら、実質的にはスタティックである。もちろん、こういう部分はある。仕手筋は、思い通りに動かすが、動かし方は、そのときのフォロワーの動き方による。リーマンショック前のバブルにおいても、あそこまでフォロワーが大きくなるとは思っていなかったかもしれないが、概ね予想通りの方向であった。このような場合は、ダイナミックであるが、シナリオが予想できるダイナミックスであり、ある意味静的なダイナミックスとも言える。
一方、真にダイナミックな市場においては、どんな投資家であっても、結果は予測できない。リーマンショックは、この二つの中間と言っていい。バブルであり、いつか崩壊することは分かっている、という点では、静的なダイナミズムであるが、それがいつか、どこまで上がってから崩壊するかが分からなかったから、今日バブルに乗り続けるべきか、降りておくべきか、という判断からすると、結果の読めない動的な意思決定をしなければならない、という点で真のダイナミックスといえる。
これはよくある話で、第二部的に、超合理的投資家が、あるいは仕手筋がバブルを膨らませようと意図して膨らませたバブルが、予想以上のフォロワーを呼び込み、予想を超えて長期の大規模なバブルになってしまう場合がある。チューリップバブルもこの可能性があるかもしれないが、このときに、最初の超合理的投資家は、いち早くバブルから降りて、利益を確定しているはずである。
これは、彼らにとっては最悪である。儲かっているからいいじゃないか、というのは素人の考えで、プロの投資家とは、その瞬間瞬間で相対的に他のプロに勝たなければ行けない。だから、バブルがあれば、ぎりぎりまで乗っていないと行けないのである。ITバブルの時にも、日本のネット投資家バブルの時にもあったことだが、2倍で利益を確定させ、その後10倍になった株というのはいくらでもあり、その場合は、せめて8倍ぐらいまでは乗っていないと、個人投資家の場合はひどく後悔するし、プロの場合は、資金を引き揚げられる。しかも、プロの一部は、そのバブルにおけるリーダーだった投資家、つまり、そのバブルを仕掛けた投資家もいるから、彼らにとっては目も当てられないほど、ショックを受ける。
これが第三部のエッセンスである。多様な投資家がいて、リーダーもフォロワーもいるが、リーダーであっても、市場の構造は分かっているが、個々の投資家の行動は予測しきれない。予測しきれない、というのは新古典派経済学でもゲームセオリーでも当然のことだが、その場合は、行動が不確実なだけで、その可能性の分布は既知であるから、その分布に基づき、最適戦略を立て、自分の行動を決定できる。限定合理性であっても、基本的な考え方は同じことだ。しかし、ここでは、岩井克人的な不均衡動学的な考え方をしている。本来のケインズ自身の考え方といってもいいかもしれない。
つまり、フォロワーの行動は予測できない。しかも、フォロワーにもいろいろいる。そして群集心理が働くから、いろいろなシナリオがあり得る。理論上は、すべてのシナリオの結果を統計的に処理して、自己の行動を決定することになる。いや、理論上というのは新古典派的な理論上だ。これなら普通だ。行動ファイナンスではどう考えるか。いろいろあり得る。いわゆるエージェントベースモデルアプローチは、この一つの対処法だ。Simulationで対応するが、単なるsimulationではなく、ダイナミズムに重点を置いたものだ。つまり、均衡がどうなるか、simulationして、均衡の分布を知るのではなく、変化のプロセスを観察するということだ。均衡にたどり着くかどうかはどうでもよく、動きのプロセス、ダイナミズムそのものが重要なのだ。だから、均衡アプローチからは外れている。
さらにダイナミックなマクロ行動ファイナンスを指向するのであれば、このダイナミズムがプレイヤーの行動原理をどう変えていくか、そのプロセスを重視することになろう。これは進化論的アプローチでもあり、エージェントベースでもそう考えることは可能だ。プレイしていく中で、スタイルを変えていく。それは自分で選べるとしてもいいし、市場環境に影響を受ける、という設定でもいい。
しかし、最も興味深いのは、新しいスタイルを自ら作り出すということだ。そして、それがスタイルだと自分では認識していない。しかし、他人から見ると、そのスタイルは明らかに見える。いや、明らかに見える場合もあれば、単に他人からは別のスタイルに見える、ということもありうる。自己認識、相手の認識、神のような俯瞰した認識、この3つが異なるということだ。
これが第三部の行動ファイナンスである。どのプレイヤーにも将来の予測はできないが、その中で行動を選択する。その選択が市場を世界を変えることにより、他者の行動が変わり、それは自分に対する環境を変える。行動モデルの変化を含むから、短期と長期の乖離、行動も乖離するし、思考も、嗜好も乖離する。
この第三部の問題点は、そのようなモデル、理論的ツールが完成からほど遠いどころか、ほとんど開発されていないところだ。現時点では、私の妄想に近い、といわれても仕方がない状態だ。そして、今後、そのようなモデルを作ることが可能か、という問題がある。この問に対しては、現代ファイナンス(あるいは新古典派的な経済学者、あるいは普通の経済学者)の側も、行動経済学者であっても、懐疑的だ。だから、マクロ行動経済学をあきらめ、あるいは、もともと無意識のうちに、そのような成功しそうもないアカデミックベンチャーは選択から排除し(こういう行動パターンを選択的に確立するのが、前述のモデルの一部である)、神経経済学や細かいモデルの精緻化、実験に経済学者のエネルギー資源が配分されている。
だから、まともな行動経済学は、池尾氏にとってはつまらないのであり、興味深い行動経済学は非現実的であり、行動経済学というアプローチに対する重要性は認識しても、評価が低くなることが一般的なのである。