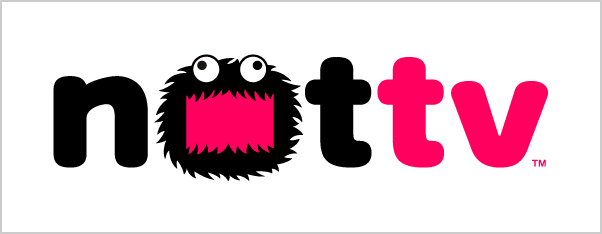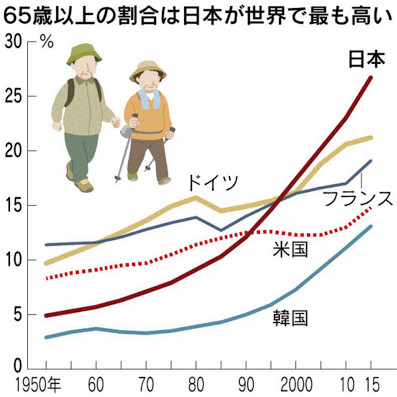ロンドン発の記事をフォローしていると、英国民は欧州連合(EU)から離脱を望んでいなかったような印象を受ける。23日に実施された国民投票の結果は約51.9%の国民が離脱を願っていた。残留派との差は僅差だが、多数決原則に基づく民主主義国家では十分な差だ。繰り返すが、英国民はEU離脱を決定したのだ。実際、残留を主張してきたキャメロン首相は24日、敗北を認め、引責辞任を早々と表明している。
にもかかわらず、というべきか、残留派は執拗に国民投票のやり直しを要求し、請願書を送り続けている。あたかも23日の国民投票の決定は国民ではなく、欧州に彷徨う亡霊が国民の意思に反して離脱の道を強いたと主張しているようにだ。そうではないはずだ。それでは離脱派の情報操作や偽情報が多くの国民をミスリードした結果だろうか。情報操作や偽情報は選挙戦で常に見られる現象であり、特筆に値しない。残留派にも、一定の情報操作はあったはずだ。
それでは、直接民主主義の代表的な制度、国民投票は国民の総意を反映しないのだろうか。この問い掛けはかなり危険だが、英国民の「その後」の反応をみていると問わざるを得なくなる。
民主主義は基本的には多数決原理に立脚している。選挙では一票でも多い候補者、政党が当選し、少なければ落選だ。最近では、オーストリアで実施された大統領選は文字通り、2候補者は1%以下の得票差だったが、集計のやり直しを要求できても、不正が判明しない限り、選挙のやり直しはできない。
多数を獲得した政党は政権を担当し、その選挙公約を実施する。しかし、議会民主主義は決して勝利者オンリーの政治システムではない。国民の人権尊重や少数派の権利は保障される。その上、民主主義は2重、3重の自己規制のメカニズムが機能している。
先ず、総選挙で過半数を獲得した政権の任期は決められている。ローマ法王のように終身制ではない。通常、4年から5年だ。国会議員も同様だ。所属する政党の党綱領に縛られているから、自分勝手な言動をふるまうことはできない。
選挙で落選すれば、「先生」と呼ばれてきた国会議員も「ただの人」となる。日本の永田町の住民はそのことを肌で感じている。その意味で民主主義の多数決原則には暴走防止のさまざまな規制メカニズムが機能しているわけだ。換言すれば、民主主義下で独裁者が誕生しないように防止策がとられているわけだ。
過半数を獲得した政党、指導者が任期中に大多数の国民に好ましくない政策を実施した場合、有権者は次回の選挙でその政党、指導者に投票しないという制裁を下せばいい。例えば、憲法改正という国の行方を決める大きな課題の場合、議会の3分の2の支持が必要な国が多い。
一方、国民投票の場合、そのよう自己規制メカニズムは十分ではない。国民投票で一度決定した政策は無効にするのは難しい。なぜならば、「国家の主権者」の国民自らが決定したからだ。誰がその決定を無効と表明できるだろうか。民主主義下では国民以上の高位の主権者がいない。国民投票のやり直しを主張したり、その無効を叫ぶことは、国民が自身の決定に文句を告げているような錯乱状況を意味する。
それでは、国民投票では国民の意思がなぜ予想外の結果をもたらすのだろうか。国民投票の場合、国民に十分な情報を提供し、その是非を判断できるだけの時間が必要となる。例えば、イスラム寺院の建設問題やイスラム教女性のスカーフ着用の場合、国民は自身の体験から判断できるが、原発建設の是非となれば、国のエネルギー政策から安全問題まで専門的な知識が求められる。だから知識も時間も限定されている多くの国民はポピュリストの扇動などにどうしても影響を受けやすくなるのだ。
国民投票の場合、技術的な問題点もある。国の行方を決定するEU離脱問題を「イエス」か「ノー」の2者択一形式でしか問うことが出来ないから、国民の意思が100%反映した結果をもたらすことは期待できない。だから、重要な議題であればあるほど、国民投票で問うことは賢明ではないと言わざるを得ないのだ。
間接民主主義の最大の利点には、国民はやり直しが出来ることだ。自己規制のメカニズムを有する民主主義も大衆迎合主義に陥りやすい弱点もあるが、現時点では最善な政治システムと言わざるを得ないわけだ。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2016年6月30日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。