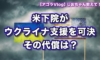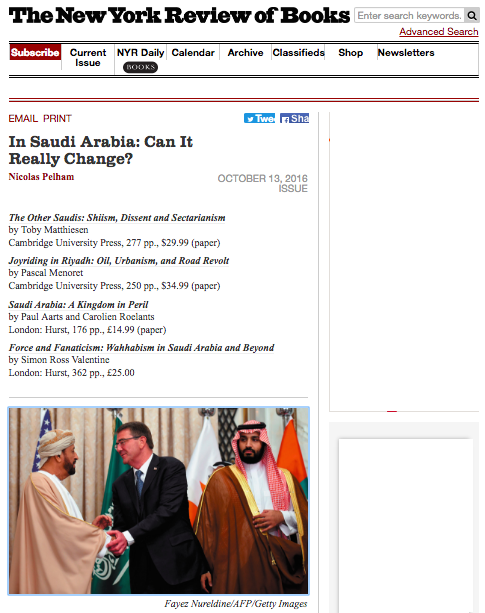
Nicolas Pelham氏がNYTのブックレビューサイトに寄稿した記事
アラブ問題の専門家である Nicolas Pelham が New York Review of Books に寄稿した “In Saudi Arabia : Can it really change?” (Oct 13, 2016 issue)を読んでいて、思わず座り直した箇所があった。
本年1月、著者も同行してムハンマド・ビン・サルマン副皇太子(MBS)とインタビューを行った時、手配をしてくれた人のアドバイスにも関わらず、英誌“The Economist”の編集長はベールもアバヤ(全身を覆うコート)も纏うことを拒絶した、というくだりだ。編集長が女性だったとも知らずに、あの有名なインタビュー記事を読み、弊ブログ(2016年1月11日「サウジアラムコは石油精製・石油化学部門のみを売却」)を書いたのだが、この寄稿文を読む限り、MBSがこのことを問題視したとは思えない。MBSがどう感じたのかは別にして、リヤド郊外の自らの別荘(rest house)の居間で、ベールも被らず、アバヤも着ていない、西洋社会の女性とのインタビューに応えたようなのだ。
これは何を意味しているのだろうか?
当該寄稿文は、サウジアラビアに関する最近刊の4冊の本を紹介する形をとりながら、著者自らの見聞、調査結果をも報じ、共生社会の利点を理解しているMBSが、サウド家の統治を維持ししつつ脱石油経済の社会に変革するためには「言葉以上のものが必要だ」と結論的に述べているものである。
本文では、サウジの国家としての成り立ちを詳細に紹介しながら、ワッハーブ派の原理主義的な厳格な教義に基づく生活規範に基づく社会、というイメージと異なり、外部からは見えにくいが現実のサウジ社会はより多様的で緩やかである様子を伝えている。
たとえばジェッダ地元のビジネスマンたちが組織するチャリテイ団体主催による、ワッハーブ派時代以前を思い出そう、というフェスティバルなどは、オスマン・トルコ帝国の版図が紅海側もペルシャ湾側も海沿いだけで、アラビア半島の中心部は対象外だったことを思い出させて興味深いものがある。古より国際的貿易港であったジェッダの人々にとっては、内陸で誕生したワッハーブ派以前からオレたちはこの地で暮らしていたのだぞ、という意思表示であり、サウジ政府もこれを容認しているのだ。
さらには、本年1月に処刑されたシーア派の指導者ニムル師の兄弟(17歳の息子もすでに死刑判決を受けている)の言葉を紹介しながら、東部のシーア派が「二等国民」扱いされている実態なども紹介している。
中身の濃い長文で、筆者の能力では本文の趣旨を簡潔にまとめてお伝え出来ないので、サウジ専門家の解説を待ちたいと思う。
だが、一つだけ触れておきたい点がある。
著者は、4冊の本の著者がそれぞれサウジ社会のゆるい現実を紹介している箇所をいくつも示しているのだが、その中で筆者が特に印象づけられたのはSimon Ross Valentineが “Wahhabism in Saudi”の中で「どこに行っても、楽しい時間を過ごすために麻薬や酒や女はどうだ、と言われた」と記述しているという箇所だ。
約20年前、筆者がテヘラン勤務をしていた時、当時のイランでは正式に結婚できない貧しい男たちのために「一晩婚」が流行っている、という英文記事を読んだことがあった。
結婚をするときには、離婚する際に夫が妻に渡す財産を記した契約書を交わす必要があるのだが、「一晩婚」とは、翌朝に「離婚」するときの「財産」を記した契約書を交わす「一晩」限りの「結婚」のことだ。社会の不満の一端をガス抜きする方策で、聖職者が承認しているものだった。
「一晩婚」は、建前としての厳しい戒律に基づいた社会規範を維持しつつ、現実的な対応を行うイスラム社会の「生活の知恵」とでも言うべきものだろうか。
サウジの「女」とは、やはり「一晩婚」のことなのだろうか?
正しく理解するためには原文を読んでみる必要があるが、その時間が取れるかな?
編集部より:この記事は「岩瀬昇のエネルギーブログ」2016年10月4日のブログより転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はこちらをご覧ください。