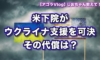日本経済新聞編集委員としてエネルギー問題等に健筆をふるう松尾博文氏の今朝(12月12日)のブログ「減産合意の影でちらつく石油時代の終わり」(編集部注・リンク先有料会員限定)を読んで、思わず腕を組んで考え込んでしまった。
新しい「ピークオイル」論である「石油需要のピーク」がいつか来ることを念頭におくべきだ、という松尾氏の指摘には100%同感だ。これは産油国や石油会社のみならず、最終消費者である我々も持つべき視点だろう。
だが松尾氏がいうように「長引く原油安」が「産油国や石油会社」に「迫っている」「構造的な対応」とは「天然ガスへのシフトや再生可能エネルギーの拡大」だけだろうか。
弊ブログをお読みいただいている方々に誤解はないと思うが、「石油需要のピーク」が来る、ということは、その日を境に石油がまったく使われなくなる、ということではない。今日の約9,500万BDほどの需要がこれから1億~1.1億BD程度にまで漸増し、そこでピークを迎え、以降しばらく横ばいとなり、それから徐々に減少していく、というのが考えられているシナリオだ。問題は、その「ピーク」がいつ来るのか、ということだ。
つまり向こう数十年間は、現在とあまり変わらない量の石油が消費され続けるのは間違いがない。
第二次世界大戦後「エネルギー革命」により、「石炭の時代」は終わり「石油の時代」になったと認識されている。だが「終わった」はずの石炭が、数十年を経た今日でも世界の一次エネルギー供給比率で、33%の石油に次ぎ29%で第二位を占めている(BP統計集2016年版)。「石器時代は石が無くなったから終わったのではない」というヤマニの警句は、この事実とともに噛みしめる必要がある。
弊著『原油暴落の謎を解く』(文春新書、2016年6月)の「第四章 石油の時代は終わるのか?」で紹介したように、スーパーメジャーであるBP調査部門のトップ、スペンサー・デールは2015年10月の講演「石油の新経済学」で、石油が枯渇する心配はもうないだろう、と指摘している。論拠は松尾氏が指摘しているものと同じだ。その結果、右肩上がりで需要が伸び続ける一方で、採掘コストの安いものから供給されるので、石油価格は時間の経過とともに高くなる、というこれまでの「古い経済学」の考え方は成り立たなくなる、というのだ。
つらつら考えるに、「産油国や石油会社」が迫られている「対応」の一つに、技術力に裏打ちされたコスト競争力のある埋蔵量を持つ、ということもあるのではないだろうか?
今年のダボス会議でエネルギー関連の会議を仕切ったカリフォルニア大学のジャッフェ氏が指摘しているように、投資家は投資先の「保有埋蔵量」だけでなく、経営能力を冷静に判断する必要があるのだろう(弊ブログ「『石油需要ピーク』が来たら?」2016年8月18日参照)。
この観点から、2018年にも予定されているサウジアラムコのIPOに際し、同社が保有する約2,600億バレル(1,000万BDで70年以上生産できる量)の埋蔵量がどれだけのコスト競争力があるのか、そしてまた、どの程度関連情報が開示されるのか、非常に興味深いものがある。
はてさてサウジの石油埋蔵量は、どれだけの量が「放置された資源」になってしまうのだろうか?
編集部より:この記事は「岩瀬昇のエネルギーブログ」2016年12月12日のブログより転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はこちらをご覧ください。