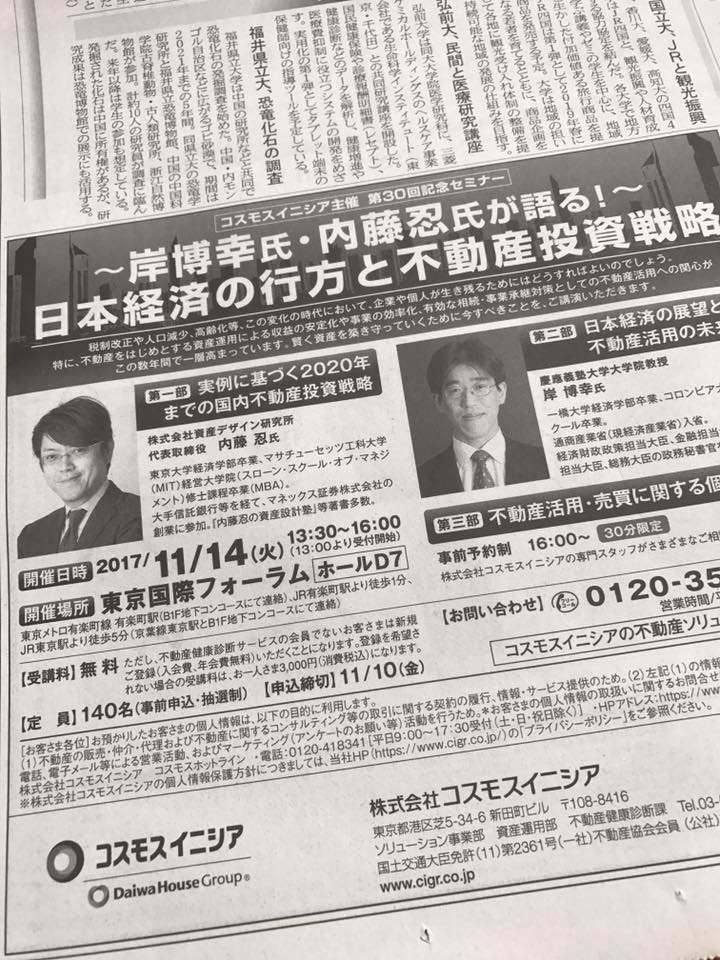19世紀末のフランス。上流階級の令嬢で、17歳のヴァランティーヌは、親が決めたジュールとの婚約を一度は破棄するが、彼の熱心な求愛に心を動かされ結婚する。二人は、深い絆で結ばれた夫婦となるが、病気や戦争で子どもが亡くなる悲劇に見舞われる。ジュールも亡くなり失意のヴァランティーヌだったが、残った息子アンリが幼なじみのマチルドと結婚し、孫が生まれたことが彼女に再び喜びをもたらした。マチルドの従妹のガブリエルと彼女の夫も頻繁に家を訪れ、大家族のような、穏やかな幸せな日々が続く。だがヴァランティーヌと家族たちの運命には、思いがけない形で転機が訪れる…。
花と緑に囲まれたフランスの美しい大邸宅を舞台に、ある富豪の一家の3人の女性たちの人生を描く大河ドラマ「エタニティ 永遠の花たちへ」。アリス・フェルネの原作小説をベースに「青いパパイヤの香り」「夏至」などの名匠トラン・アン・ユン監督が、圧倒的な映像美で描く物語だ。テーマは、生と死が永遠(エタニティ)に繰り返され、受け継がれていくこと。命の連鎖を支える時間の存在を、美しいものとしてとらえて、受け入れていくことだろう。
オドレイ・トトゥ、メラニー・ロラン、ベレニス・ベジョという仏映画界を代表する人気女優の贅沢な競演は見所のひとつだ。19世紀から20世紀にかけての上流社会の優雅な暮らしぶりや、衣装や家具調度品が美しく、思わず見惚れてしまう。だが、あまりにもストーリーが平坦でメリハリがない。戦死や病死、時に修道院に入って俗世から離れるなど、家族に降りかかる悲劇が何度か描かれるが、女性たちは悲しみを胸に秘めながら静かに乗り越えていくといった描写だ。そもそも、3世代の女性を描くという触れ込みなのに、よくよく見れば、母、娘、孫ではなく、母、息子の嫁、その嫁の従妹という3人の関係性が微妙に不自然だったりする。そんな「?」もあるにはあるが、トラン・アン・ユン作品を支えてきた名撮影監督マーク・リー・ピンビンの、しびれるような映像美に酔いしれ、しばし別世界へと誘われれば、心地よい陶酔感を味わえるだろう。監督の妻トラン・ヌー・イェン・ケーの、しみいるような美声のナレーションが、これまた独特の優美なムードを醸し出している。
【55点】
(原題「ETERNITY」)
(仏・ベルギー/トラン・アン・ユン監督/オドレイ・トトゥ、メラニー・ロラン、ベレニス・ベジョ、他)
(映像美度:★★★★★)
この記事は、映画ライター渡まち子氏のブログ「映画通信シネマッシモ☆映画ライター渡まち子の映画評」2017年10月11日の記事を転載させていただきました(アイキャッチ画像は公式ウェブサイトから)。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。