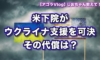4作目の最終章に入り、大きな壁にぶつかっている。「日章丸事件」の位置づけだ。
「日章丸事件」については、一般的には太平洋戦争の敗北により占領下にあった日本が、サンフランシスコ講和条約の発効によりようやく独立を勝ち取ったころに、欧米の圧迫を跳ね除けて、イギリス艦隊が監視するペルシャ湾に果敢にタンカーを送り、禁輸措置により財政難に喘いでいたイランから石油を輸入し、多くの日本人が溜飲を下げた快挙として理解されている。
「海賊と呼ばれた男」出光佐三は、さらに「世界に挑んだ」というわけだ。
昨年12月、東宝映画『海賊と呼ばれた男』封切りに合わせて発行された『歴史街道』2017年1月号(PHP研究所)は、「日本人の『矜持』と『底力』」を見せて「世界に挑んだ海賊」とのサブタイトルをつけた「総力特集 出光佐三」を組んだ。
出光佐三の評伝を書いている水木揚氏や橘川武郎教授などを含め、多くの人がさまざまな時代の局面を解説し、全体として人間・出光佐三を描き出そうという編集方針で、筆者が担当したのは支那事変から日本軍が南進した時期の出光の活躍ぶりだった。異なる複数の執筆者の前後の文章がつながるように構成されているため、筆者が一番強調したかった「元祖・起業家」という出光佐三像の表現は割愛されている。
だが、供給元の日本石油の販売政策の盲点をついて、どこの特約店の販売地域でもない関門海峡で船舶用のディーゼル油を売りまくった「海賊と呼ばれた男」は、満鉄への潤滑油納入でも寒冷地の気象状況を研究することにより米メジャーの市場を奪い取っている。まさに創意工夫の塊、すべての起業家が学ぶべき元祖と言っていい大人物だ。
だが、起業家は「自分がやっていることが世の中のためになる」という信念を抱いて事業に取り組んでいる一方で、やはり「利益」を出すことが事業家として毎期末に受け取る「通信簿」であることも強く認識しているものなのだ。
元祖・起業家である出光佐三は、日本人が「溜飲を下げる」ためだけに「日章丸」をペルシャ湾に送ったのではないはずだ。儲かる商機、将来の事業拡大の可能性を見据えていたはずだ。
この「思い」を裏付ける資料を漁っていたところ、今日(2017年11月17日)、非常に興味深い論文に遭遇した。神奈川大学非常勤講師のケイワン・アブドリ氏による「出光石油協定に見る1950年代のイランと日本のエネルギー外交」(以下、「アブドリ論考」)というものだ。
この論考はまだ暫定版で、2018年3月発行予定のウエブ雑誌『中東レビュー』第5号に最終テキストが掲載される予定とのことだが、筆者が伝えたいポイントは不変と思われるので、ここに紹介しておこう。
アブドリ氏が翻訳・解題しているのは、イラン国立図書館・資料局が公開している資料の一つで、1956年9月22日に日本大使館からイラン外務省に送られ、外務省が財務省に提供した書簡のペルシャ語翻訳文だそうだ。イラン外務省のレターヘッドが入っており、イラン側によって翻訳されているが、署名がなく、送り主も明記されていないとのこと。ただし、別の資料に基づき、イラン外務省が日本大使館から直接手渡されたものだ、とアブドリ氏は解説している。
なお文末に「Dr.アリーゴリー・アルダラーン氏宛て」とあるから、アルダラーン氏が受け取った外務省の高官なのだろう。
筆者には「アブドリ論考」の資料の信憑性を問う能力はないが、日本政府が公式に「出光との協定履行」をイラン政府に求めていたとしたら、非常に興味深い。
要点は次のとおりだ。
「1953年2月14日に締結された・・・協定は二段階からなり、その全有効期間は9年間・・・。協定締結から2ヶ月後に結ばれた補足協定に基づいて・・・18ヶ月以内に500万バレルの石油製品を積み取ることが義務付けられ、価格は国際価格よりほぼ3割近く安く定められた。また第二段階においても“競争的地位”が保てる原則が守られるよう合意された」
だが、船積みが開始された1953年の夏、クーデーターが起こり、国有化を実施したモサッデク政権は倒れてしまった。クーデーター後イラン政府は、国有化前の利権保持者であるアングロ・イラニアン石油(現在のBP)を含む欧米8社からなるコンソーシアムと1954年に新たな石油協定を締結した。当該新石油協定に基づきNIOC(イラン国営石油)は、生産量の12.5%を自由に販売することができるようになったのだが、コンソーシアムが買い取ってくれる「国際価格」より値引きして出光など第三者に販売するインセンティブはなかった。NIOCは当然のように、価格条件を一方的に改訂、出光に突きつけてきた。だが「国際価格」そのものでは出光にメリットはない。「競争的地位」を保つという条件を守れ、と出光は主張した。
こうした中で、日本政府が動いた、というわけだ。
だが、冷静に考えると、敗戦の廃墟から懸命に立ち上がろうとしている当時の日本石油産業には、探鉱、開発、生産、精製、販売の、どの分野をとっても、技術力、資金力、経験、ノウハウ、全ての点でセブンシスターズの名で知られる大手国際石油の「力」に勝てるものはなかった。NIOCが出光ではなく、コンソーシアムによりかかったのは当然だ。
かくて「世界に挑んだ海賊」も、協定履行を勝ち取ることはできず、捲土重来を期するしか対応策はなかったのだ。
だが、18ヶ月間で500万バレル(約80万kl)に上る超安値のイラン石油製品を輸入できたことは、550万kl(1953年)から960万kl(1955年)とへと急増していた日本の消費量を考慮すると、ようやく精製業に進出し始めた出光に、販売シェアー拡大と高利潤をもたらしたことは間違いがないだろう。
「日章丸事件」とは、元祖・起業家の面目躍如たる “a very risky but highly profitable deal”(「アブドリ論考」)だったのである。
編集部より:この記事は「岩瀬昇のエネルギーブログ」2017年11月17日のブログより転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はこちらをご覧ください。