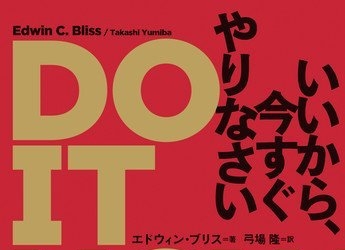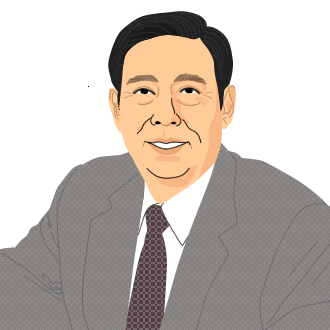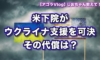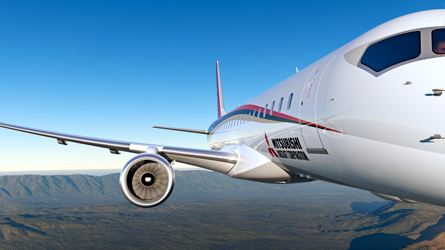
MRJ公式サイトより:編集部
これは今から約10年前に文藝春秋社の月刊「諸君!」に書いた原稿です。
MRJがファンボロー航空ショーでデモフライトをした期ですので、掲載しておきます。
これを書いた当時は自称事情通の軍オタさんたちから散々貶されましたが、10年経って誰が正しかったは明白だと思います。
■
防衛省は本年度予算から装備の「まとめ買い」を始めた。二年にわたって8機調達する空自のF2戦闘機を本年度で一括調達、これで162億円の経費削減、同じく本年から3年間で調達するはずだった陸自の多用途ヘリコプター、UH-1J16機も一括調達で16億円のコスト削減、総額を実現している。また平成20年度年度予算の要求分では、PX(次期哨戒機)やF15戦闘機の近代化改修、MCH-101ヘリコプターなどごく一部を「まとめ買い」するだけで、約400億円の調達費のコスト削減を行うとしている。
これは防衛省の装備調達の画期的な変化であるのだが、メディアでこれを伝えたところは殆ど無かった。
他国では通常防衛装備の調達に先立って調達数、調達期間、予算総額を決定する。例えば6年で戦闘ヘリを50機、予算は三千億円、一機当たりの単価は60億円と言った具合である。このような調達契約を結べばサプライヤー(メーカーや商社)はプロジェクトの内容が明確となり、ラインの維持期間、人件費、利益が事前に確定できる。また下請け企業にも部品などを纏めて発注できる。故にコストを抑えることができる。
ところが我が国の単年度会計に基づく調達方式では初めに数量、調達期間、総額を決定せずに、漫然と何十年もかけて装備が調達されることが恒常化している。故に国産、輸入品を問わず諸外国に比べて調達価格が何倍も高い。
このような「まとめ買い」が始まったのは、MD(ミサイル防衛)で通常装備の調達予算が圧迫されて、今までのように調達期間を引き延ばして毎年少量を発注するという、高コストな調達に耐えられなくなってきているからである。始まった「まとめ買い」はある意味需要の先食いであり、今後必然的に国内の防衛産業ではメーカーの淘汰が始まるだろう。
もし何の対策も講じないまま放置すれば、我が国の防衛・航空宇宙産業は緩慢な死を迎えるか、外国資本の傘下に入って生き残るかしか道はあるまい。
我が国の安全保障にとって独自の防衛航空宇宙産業とその生産基盤の維持は必要である。これを維持発展させるためには民間機市場への参入が必要である。いまこそ内閣府、あるいは首相官邸が音頭をとって、長期的視野に立った政策を立案し、業界の自立と再編成を促すべきである。
このような背景もあり、産業界では航空宇宙の分野では防衛省の「官需」に頼らないで民需に活路を見いだそうという動きもでている。
既に多くの国内メディアで報道されているように、三菱重工はリージョナルジェット(100人未満乗りの小型旅客機)市場に参入すべく、70~90人乗りのMRJ(三菱リージョナルジェット)の開発を進めている。
複合材料を多用して機体を軽量化、また新型の効率的なエンジンを搭載するなどして、他社製品より2割ほど高い燃費と広いキャビンを売り物にしている。08年から本格的な開発を行い、12年に就航予定となっている。開発費用1200億円、事業化の費用は約七〇〇〇億円といわれる一大プロジェクトである。
6月に行われた第47回パリ航空ショーではMRJの胴体モックアップが公開された。また、約一二〇〇億円とされている開発資金のうち、経産省は既に四〇〇億円を提供することを決定している。成功すればYS-11以来の国産旅客機の誕生となる。
現在我が国の防衛航空産業は防衛省の需要と、民間分野ではボーイングやエアバス、エンブラエル、ボンバルディアなど航空機メーカー大手の下請けがその売り上げの柱となっている。しかし防衛費は今後大幅に増加される可能性は低く、先細りが予想される。また外国の下請け仕事に甘んじ、総合的に航空機を開発する能力をもたなければ、将来的に自主開発能力は勿論、高い技術を維持できる保障はなく、韓国やトルコ、中国など中進国、途上国に仕事を奪われていくだろう。
我が国は「武器輸出三原則等」により現状では兵器の輸出ができない。であるならば、海外に輸出可能な旅客機を開発するという方針は正しい。
航空産業は先端技術の塊であり、単に航空機メーカーだけではなく、各種コンポーネントから素材産業まで、幅の広い経済および雇用の波及効果がある。また、航空技術の基礎研究は軍用機にも応用できるので、その成果は軍用機=自衛隊用機体の開発にも応用できる。そのような観点からも国産旅客機開発はメリットがある。
だが、筆者にはMRJのプロジェクトは途中で挫折し、経産省が投資する資金は死に金になると予想している。その理由として第一に、当の三菱重工にプロジェクトを何が何でも成功させるといった気魄が感じられない。第二に、このような巨大プロジェクトには三菱のみならず他の国内メーカーの協力が必要だが、そのようなコンセンサスが業界にない。第三に政府に防衛航空産業育成のグランドデザインが欠如しており、明確なビジョンがないことが挙げられる。
防衛省、国交省、財務省など関係省庁の間に充分なコンセンサスが出来ていない。そんな現状のまま、思いつきで小出しの補助金を出しても、軍事において下策とされる「兵力の逐次投入」を行うに等しい。
6月に開催されたパリ航空ショーにおいて、三菱重工がスポンサーとなってMRJプロモーションのためのレセプションが日本大使公邸を借りて行われた。ところが筆者の得た情報によると参加者約300名の内日本の業界関係者が約250名、フランス人が30名、その他20名ほどがスウェーデン人など他の外国人であったという(なお、在仏日本大使館に確認したところによると参加者は約280名、内外国人が90名とのことである)。いずれにしても国際的な航空ショーでのレセプションとして日本人の比率が多すぎる。
パリ航空ショーは英国のファンボロウ航空ショーと並び、世界中の航空業界関係者が集まる航空業界最大のイベントである。レセプションを開くのであれば、国内の業界関係者よりも潜在的顧客である各国のエアライン、プロジェクトに投資をしてくれそうな投資会社や銀行、リース会社(旅客機はリースで運用されることが多い)、メディア、特に航空専門誌などの関係者を優先的に招待すべきだろう。
海外への情報発信の千載一遇のチャンスで、日本人同士で飲み食いしているようではやる気を疑われても仕方あるまい。在仏日本大使館によると外国人の参加者を絞ったのは、「大使公邸のキャパシティの問題」であるとのことだったが、ならば初めからホテルの宴会場を借りればいいだけの話である。大使公邸を借り切るメリットはない。
別な事例を挙げよう。
三菱重工は民間ヘリコプター市場に参入するためにMH2000なるヘリコプターを開発したことがある。これは機体、エンジンともに同社の開発によるもので、99年から10年間で100機を販売する予定だった。しかし、現在に至るまで売れたのは僅か数機で、事実上販売から撤退を行っている。原因はマーケティングの不足、特に甘い需要予測と販売体制の不備である。実績のない後発メーカーが、実績もない自社開発のエンジンを搭載して売ろうというのだから不人気は容易に予想できたはずである。同社の関係者によるとエンジンは騒音が酷く売り物にはならなかった、という。三菱重工には長年「軍需」に依存しきたためか「民間航空機メーカー」としての自覚、言い換えれば当事者意識が欠如しているといわざるを得ない。
そもそもMRJの計画自体に無理がある。まず三菱重工の航空宇宙部門の規模が過小である。先に述べたように、MRJの場合、開発費が約一二〇〇億円、事業化に七〇〇〇億円ほどかかると見られている。三菱重工の売り上げは06年度で3兆600億円、経常利益は830億円ほどで、その事業規模は世界の防衛産業メーカーのランキングで第4位のノースロップグラマンに近い。だが、航空宇宙部門は売り上げが五〇〇〇億円弱、経常利益は約一四四億円に過ぎない。開発費の内四〇〇億円は国が負担するとしてとしても、残りは800億円。この金額は同社の航空宇宙部門の経常利益の5.5年分であり、事業化の経費七〇〇〇億円は実に同社の経常利益の半世紀分に相当する。同社は三菱グループや協力を表明している富士重工、銀行、商社などに資金面での協力を呼びかけているが、かなり厳しいだろう。
しかも現在のところ、国は事業化に際してどこまで経済的な支援を行うか明らかにしていない。筆者は旅客機開発に関しては明確な戦略や覚悟があれば兆円規模の国費を支出してもいいと思っている。エアバスも三〇年ほどか嘗て黒字化を実現したが、これも参加各国の財政的支援があってのことである。
だが、明確なビジョンがないままズルズルと小出しに援助をする、あるいは逆に途中で放り投げるのでは単なる税金の無駄遣いに終わる。YS-11はそれで失敗したが、その教訓から何も学んでいない。
MRJは採算分岐点が三五〇機といわれているがこれもかなり楽観的な数字だ。この市場はカナダのボンバルディアとブラジルのエンブラエルの寡占状態である。先行メーカーは既に基本モデルを元に座席数を増減するなどしたバリエーションを販売してファミリー化を進めている。エアラインは同一機種のファミリーを採用すれば、調達コスト、乗員の訓練、メンテナンス、部品のストックなどロジスティックスのコストを安く済ませられる。この点でも後発は不利だ。エアラインは基本的に保守的で、長年の信用と実績のあるメーカーの製品を好む。
それはもし新型機が欠陥に起因する大事故を起こせば、被害は補償などの直接的な面に留まらないからだ。同機種は原因が究明されるまで飛行が停止されるのでエアラインは運行面でも大きなダメージを蒙る。一九四〇年代末、英国のデ=ハビランド社は世界初のジェット旅客機、コメットを開発して人気を博したが、金属疲労に起因する墜落事後が続発し、コメットが市場から姿を消しただけ同社も経営が傾き他社と合併する羽目になった。
意外かも知れないが、信頼性に関しては軍用機より旅客機の方がシビアである。それは民間航空の方が遙かに機体を酷使するからである。エアラインは投入した資金を回収するために導入した機体を可能な限り可動させる。例えば東京―大阪便であれば機体は一日に何往復もする。
ところが軍用機はそれほど頻繁に飛行しない。一例を挙げれば空自の戦闘機の年間飛行時間は一八〇時間ほどに過ぎない。使用頻度が低い故に一般に機体の寿命は軍用機の方が長い。1952年に初飛行を行った米空軍のB-52爆撃機は2045年まで使用されることになっている。B-52の最終型の製造が終わったのは1962年であるから、実に80年以上も使用されることになる。それに比べて使用頻度の高い民間旅客機は遙かに耐用期間が短い。
話が逸れたが、エアラインにとっていい旅客機とは購入金額が安くて頑丈で故障しない機体である。稼働率が高く、運行経費が安く済む、即ち投下した資金を、早く回収できる旅客機=稼げる機体なのだ。
新規参入組は実績がない分、値段をかなり下げる、あるいは顧客に有利なファイナンスを付けるなどの実質的なディスカウントが必要となる。しかも売り上げを伸ばすためには、先に述べたように初めのモデルの投資を回収する前から基本型以外に座席数を増減したバリエーションを開発製造して品揃えを増やす必要がある。そのための開発・生産の投資が更に必要となり、より多額の事業費が必要となる。
当然黒字化は更に先へと延びる。事業の黒字化には10年単位の時間がかかり、その間の必要な資金は兆円単位に膨らむだろう。
既に三菱重工は日本航空や全日本空輸に対して機体を引き渡すまでのつなぎの代替機のリース代や、購入した代替機の売却損などを一部補償するといった、エアライン側にとってかなりの好条件の申し出を行っている。この優遇で三菱重工の負担は数十億円にのぼるとみられる(読売新聞06年11月21日 )。
当然これらのディスカウントを行えば、採算分岐点は三五〇機よりも一層高くなる。しかも9・11のような突発事によって市場が冷え込めば尚更採算ラインは尚更遠のく。航空機の場合、生産をやめて事業を撤退した後も、世界中で一定数の機体が運用されていれば、メーカーは部品の供給の義務を負う。つまり撤退後も長年にわたって負担が必要なのである。
端的に言えばMRJ事業は三菱重工一社(三菱グループが支えるにしても)が背負うには、その企業規模からみても荷がかちすぎる。しかも多くの事業部門を抱えるデパートのような三菱重工には専業メーカーのように果敢に判断を下して、迅速に投資を行うといった経営判断が出来ない。
同社が造船、工作機械、原発、宇宙ロケット、エアコンなどの他の部門の研究開発費や設備投資を削り、それらの部門の競争力を犠牲にしてまでMRJのプロジェクトに賭けるとは考えにくい。我が国の造船業界をみても積極的な投資を行ってきたのは専業メーカーであり、三菱重工や川崎重工のような総合重機メーカーではない。
八〇年代から九〇年代初頭、リージョナルジェット市場は乱戦時代で、ボンバルディアとエンブラエルは多くの敗者を市場から駆逐して、成功を収めた。
ボンバルディアは元来スノーモービルや鉄道車輛のメーカーだったが、八〇年代に低迷していた国営カナディア社および英国のショート社を買収して旅客機ビジネスに参入、高収益の航空部門に育て上げた。またブラジルのエンブラエルも赤字の国営企業だったが、民営化によってこれまた優良企業として蘇った。
両社に共通しているのは経営者が強いリーダーシップを発揮してリストラクチャリング(単なる首切りではなく本来の意味での事業の再構成)と果敢な投資を行ったことである。つまり、リスクを厭わぬ企業家精神とリスクマネジメントこそが航空産業で成功する条件である。これが日本の航空業界には決定的に欠落している。
我が国ではYS―11に続く国産旅客機の構想は通産省と業界で練られていたが、熾烈な競争を目の当たりにして足踏み状態を続け、市場参入の決断は先送りされてきた。
しかもリージョナルジェットの市場には戦闘機で有名なロシアのスホーイ社がスーパージェット100で参入を発表しており、競争の激化は避けられない。スーパージェット100は来年就航で、既にロシア国内で一〇〇機以上の受注を獲得している。また同社はイタリアの航空宇宙メーカーであるアレニア社とフランスの防衛電子大手であるタレス社と提携している。
アレニアとの生産と販売の提携もあり既にイタリアのエアラインから受注にも成功している。タレスのカナダの子会社はリージョナルジェットのアビオニクスや搭載電子システム統合の最大手でボンバルディアやエンブラエルの仕事も手がけている。更にスホーイは販売でボーイングの協力も取り付けている。このように同社は非常に手堅い布陣を敷いている。更にスホーイ自身には戦闘機メーカーとしての強いブランド力があり、これまた販売面では有利である。
報道などによると米ボーイング社が販売面などで三菱のMRJに協力すると言っているが、これを額面通りに受け取るのはナイーブ過ぎる。ボーイングがMRJの事業にパートナーとして参加し、何割か資本を提供するならば話は別であるが、今のところその様な動きは見られない。先に述べたようにボーイングは既にスホーイのとの提携を発表している。
そもそもMRJが成功すれば三菱はボーイングの縄張りである100席以上の旅客機に参入するのが目に見えている。生き馬の目を抜く航空業界に、わざわざ「下請け」を自分のライバルを育てるようなお人好しはいない。ボーイングが望むのは三菱重工が従順な下請けとして自陣営に留まることである。販売提携の話はそのための「アメ」と考えた方が自然である。
本来このような巨大なプロジェクトは我が国の航空産業界が挙国一致体制で当たり、自らリスクをとらなければ成功はおぼつかない。ところがMRJに積極的参加を表明しているのは、三菱以外では富士重工ぐらいで、他社は下請けの仕事は受けてもいいが、パートナーとしてリスクを共有しようというスタンスではない。
仮に国が今後兆単位の資金を投入するにしても、三菱重工一社に対して補助金として行うのであれば、納税者の理解は得られまい。
川崎重工は現在自衛隊のPX(次期哨戒機)、CXを担当しているが、PXをベースに旅客機を開発することを計画している。また同社はCXも民間輸送機として売りこむなどの構想を発表している。更に海自の救難用飛行艇US―2を製造している新明和はこれを消防用や民間用に海外に販売していくとしている。
これらの事業に現実性があるかというと、実はあまりない。まずPXの旅客機転用には防衛省、経産省とも協力する立場をとっているが、当然、三菱のMRJと競合することなり、タダでさえ当てにならない政府の支援を奪い合いことになる。共倒れは必至だろう。
7月3日付けの日経新聞一面は「競合するボーイング、欧州エアバスが旅客機を転用しているのに対し、トラックをそのまま積めるなど積載能力が高い」と報じているが、現在の航空貨物はその殆どが規格化された航空コンテナないしパレットで輸送される。誰が好き好んで貨物本体より重く嵩張るトラックごと空輸しようか。そもそも軍用輸送機であるCXは民間機と比べて頑丈につくれられており、その分生産コストも高い。また高翼機であるので低翼の旅客機を転用した輸送機に比べ速度が遅く、燃費も悪い。故に傑作軍用輸送機であるC-130ハーキュリーズやC-17グローブマスターIIなども殆ど民間に転用されていない。経済専門紙がこのような与太を一面に掲載してはいけない。
新明和のUS―2は現用のUA―1の後継で、世界にあまり例のない海自の最新鋭の大型飛行艇である。海自の1機あたりの調達コストは70億円であり、おいそれと消防や民間で出せる価格ではない。実は海自にしても実はUS―2を調達する必要性は低い。そもそも救難用に大型飛行艇を運用しているのは我が国だけである。他国はこのような任務にはヘリコプターを使用している。米軍ですら装備していない贅沢な(あるいは必要性のない)機体を装備する合理的理由は見あたらない。
確かにUS―2は世界でも類を見ないユニークな機体である。ヘリコプターに比べれば進出速度は遙かに速く、航続距離も格段に大きい。また離島の救急患者の移送などでも活躍している。筆者はこれを高く評価するが、費用対効果からみるとこの機体を採用するメリットは決して高くない。軽乗用車で間に合う近所の買い物用にボルボのステーションワゴンを購入するようなものである。
US―2は海自より、むしろ救難機として海上保安庁が保有するに相応しい機体である。だが全予算が約1600億円の海上保安庁が、数百億円(運用は最低3~4機が必要)を投じて、US―2の部隊を編成するのは不可能である。付け加えるならば、世界第二位の経済大国である我が国の消防庁の予算は僅かに160億円弱に過ぎない。この点からも海外での販売は如何に実現が難しいかわかるだろう。
このように航空メーカー各社のぶち上げている民間機市場への参入プランは、現実性があまり高くない。むしろ現実離れしているといってよい。これが我が国の航空産業界の認識なのである。
これら既存の航空機メーカーよりもむしろホンダやトヨタなど自動車メーカーの参入プランの方が現実的かつ堅実で、民間機市場で成功する可能性が高い。両社は長年にわたる入念な準備を経て、ビジネスジェットを開発、北米を中心に粛々と事業化に向けて活動している。実は企業のVIPや大金持ちをターゲットにしたビジネスジェットは、空飛ぶリムジンといえる存在で、経済効率やコストパフォーマンスよりもオーナーの趣味で購入が決定される傾向がある。しかも旅客機のように経済性を最優先する必要もない。
旅客機よりむしろ高級車にマーケット特性が似ている。しかも両社はクルマで培ったブランド力が大きな武器として活かせる。トヨタは05年に富士重工を買収したが、これは将来の航空機ビジネス参入に備えて航空機部門の開発のノウハウと、生産力を入手したいという思惑が働いたことは間違いあるまい。
ソ連崩壊後の世界の防衛航空宇宙マーケットは統合され、各国による保護の壁が取り払われた。その上多くの国々では国防予算が劇的に削減された。各国の企業は生存競争を勝ち抜くために買収や合併を繰り返し、企業規模の拡大と競争力の強化に勤しんできた。そうでなければ高騰する開発費や設備投資をまかなえないからである。米国を除けば先進国で航空産業は概ね機体メーカー、エンジンメーカー各一社という状況になっているのはこのような背景がある。
ところが我が国では三菱重工、川崎重工、富士重工、新明和工業の4社も航空機メーカーが存在する。この4社が互いに競合しているのであればまだ話はわかるのだが、戦闘機は三菱、大型機は川崎重工、飛行艇は新明和などと棲み分けがなされており、競合原理が働いていない。また、ジェットエンジンに関しては昭和30年代に一度石川島播磨重工(現株式会社IHI)に一本化されたが、その後通産省の意向もあり、昭和四〇年代に三菱重工と川崎重工が参入している。
ヘリコプターも三菱重工、川崎重工、富士重工の3社も存在する。欧州ではユーロコプター(独仏、EADS傘下)と、アグスタ・ウエストランド(伊英、フィンメカニカ傘下)の二社に集約されている。ヘリコプターは軍用民間用の垣根が低く、民間市場に参入し易いはずなのだが、我が国の三社は防衛需要の米国製ヘリのライセンス生産に偏重、民間市場の開拓を怠ってきた。このため国内の民間市場はおろか海保、自治体などの市場も殆ど欧米メーカーに抑えられている。
この競争力に欠ける防衛航空産業を維持、あるいは「振興」するために、戦後天文学的な税金が投入されてきた。特に防衛庁の調達は各社に仕事を分配するために一年あたりの調達数を少なく抑え、長期にわたって細々と生産している。当然調達単価は高額になる。
一例をあげると陸自の攻撃ヘリ、富士重工がライセンス生産したAH―1の生産は20余年にわたり、その1機あたりの調達コストは米国の8倍ほどとなっている。しかも調達が完了した頃には機材は旧式化し、また初期の機体は寿命を迎えている。つまり調達された約九〇機が纏まって運用されることはほとんど無かった。
一般に諸外国では兵器の調達に際しては調達数と金額が予め決定され、メーカーと契約する。例えば新戦車五〇〇輛を五年間で調達し、契約金額は5000億円といった具合である。ところが我が国では単年度予算制をとっていることもあり、防衛省は明確な調達数、総額、所用期間が示されず、なし崩し的にズルズルと生産される。つまり必要とされる装備をいつまでに、どれだけ、いくらで調達するという計画がないのである。換言すれば「調達が五年後に完了しようが、三〇年後に完了しようがかまわない、調達に一〇〇億円で済むのか、あるいは五〇〇億円かかるのか分かりません」と言っているに等しい。
このような防衛省の調達は我が国をとりまく将来の脅威の見積もりをせず、また国防のグランドデザインや戦略、ドクトリンもなく、ドンブリ勘定で装備の調達を行っていることになる。
しかもこのいい加減な調達計画を財務省が査定し、国会で承認されている。これは民主国家として極めて異常である。
これは装備を開発する際にも問題となる。本来開発費と調達費がパッケージで実際の装備の調達コストとなる。現状では開発・生産のコストを見積もらずに開発が了承されていることになる。
そんなことだから北海道でしか使えない90式戦車を「我が国固有の環境に適した戦車を自主開発」と自画自賛して何の疑問も持たないのである。
このような現状は無論メーカー側だけに非があるわけではない。むしろ官の側に大きな問題がある。何故このようなことがまかり通ってきたかというと、防衛航空宇宙産業が経産省、防衛省などといった関連省庁の天下りの受け皿として機能してきたからである。四社ある航空機メーカーが一社になれば単純計算で天下り先は四分の一に減る。
またあれこれ天下り用の業界団体や特殊法人、財団などを業界につくらせるときも企業の頭数が多い程カネが集めやすい。因みに航空機メーカー各社の天下りの受け入れは三菱重工62名、川崎重工49名、富士重工26名、新明和工業14名、IHI34名となっている。これに各社の子会社、業界団体を含めれば概ねその倍程度の天下りの面倒を見ていることになる(週刊ダイヤモンド 2007/06/23号)。役所は単年度予算を隠れ蓑に、航空産業の育成よりも、自分たちの天下り先の確保を優先してきたとしか思えない。
そもそも戦後の経産省(かつての通産省)の航空機行政は失敗の連続である。我が国は武器輸出の自粛を国是としているのであれば、航空産業を産業として自立させるためは、民間機分野に産業育成の力点をおくべきなのは自明の理であった。民間機部門が育てば、基礎研究費なども民間と案分でき、結果として防衛予算の節約にもつながったはずである。
かつてYS―11製造の際、国策会社・日本飛行機製造が設立され、各メーカーはそれに協力するという形をとった。ところが各メーカーはコスト削減に励むことなく、積み上げ式でコストを計算し、〝親方日の丸〟の日本飛行機製造に請求した。
結果としてYS―11の製造コストは高騰し、三六〇億円の損失を計上して日本飛行機製造は清算された。同社の社員はちりぢりとなり、せっかく獲得した旅客機の製造と販売のノウハウは失われた。通産省がメーカー各社に厳しくコスト削減を求め、また断固として旅客機産業を育成する方針を持っていれば、今頃はボーイングやエアバスに匹敵するメーカーに成長し、航空産業の再編もスムーズに進んでいたかもしれない。同様な高コスト体質、補助金漬けと批判の多かった、寄り合い所帯のエアバスはパートナー各国政府の補助金に支えられ、三〇年ほどかけて黒字化を実現している。
また、七〇年代、747の開発で倒産の危機に瀕したボーイングは金策のために、我が国に737の製造販売権売却の打診をしてきたが、経産省(それと業界も)はこれを拒否した。737は現在でもボーイングのドル箱である。日本航空機製造が経営を続けて、737の生産が行われていれば我が国の航空産業の現状はかなり変わったものになっていただろう。
これら例を見れば経産省(旧通産省)に航空振興の政策立案能力が欠如し、むしろ航空産業の活力を奪って育成を阻害してきていることは疑いない。通産省のビジョンと指導力の不足が旅客機ビジネスを廃業に追い込んだと言っても過言ではあるまい。
経産省の政策は猫の目のように変わり、業界を支援するための補助金も中途半端な金額で終わり、結果を出せないことが多い。その何よりの証拠が現在の防衛航空産業の現状である。メーカーは防衛庁需要に寄りかかり、企業体質の強化も、リスクをとって積極的に世界の市場に打って出ることもしなかった。天下りを受け入れている限り仕事に困ることはない。こうした官と民のもたれ合いの体質が日本の航空産業の「産業」としての自立を阻んできた。
リージョナルジェットの国産開発にしてもほかにやりようがあったろう。例えばPXへの転用を前提にすれば、かなりの開発費及びリスクを減らすことができたはずである。PXのエンジンは4発でるが、旅客機としては運用コストの安い2発の方が適しているため主翼の再設計が必要であるが、それでも単独開発よりは格段に安く上がる。実際PX開発に際してはそのような構想も存在した。
現在PXは海自が60~80機程発注することになっているが、更に海自の現用の電子戦機、連絡機、輸送機、早期警戒期機など後継機、更には海上保安庁などのYS―11などの需要(既に海保は他の機種を採用してしまった)を纏めれば100機を越えるほどの機数を確保できたろう。また現在保有している政府専用機は大型の747だけなので使い勝手が悪い。地方の小さな空港でも離着陸でき、運用コストの安い小型政府専用機の必要性が検討されているが、そういう需要も取り込めるだろう。
纏まった官需があれば、旅客機製造コストも低減でき、価格競争力が上がる。同時にPXも開発費を案分でき、しかも量産化により生産コスト、調達コストも削減できる。
その上官需だけで採算分岐点の三分の一あるいは半分を消化でき、リスクを大幅に軽減できる。更に既にPXという「軍用機」としての運用実績があれば、信頼性の面でエアラインの印象もよくなるだろう。しかも万が一、リージョナルジェットの販売が思わしくなく、事業から撤退するにしても、一〇〇機以上の官需で生産した機体のメンテナンスや部品供給の需要があるので、撤退に伴う損失を極小化できる。
このような取り組みは経産省のみでは不可能で、経産省、防衛省、国交省、文科省、財務省など関係省庁の協力が不可欠であるが、現在の縦割り行政のままでは不可能であろう。このような案がベストだと主張するつもりはないが、多くのオプションを想定し、国の政策を決定すべきであろう。
また補助金や開発資金に関していえば、経産省が日本航空機開発協会(JADC)、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)などただでさえ効率が悪い業界団体や特殊法人を通して行っている総花的なばらまきをやめる、あるいはボーイングの旅客機開発に対して行っている巨額の政府資金の提供を止めて国産旅客機開発に振り向けるならば容易に捻出できる。更には防衛省が海外から兵器を購入する際にオフセットを導入し、兵器を輸入する見返りに国産旅客機を買わせるといった手法などもオプションにいれるべきであろう。
このまま何の対策も講じずに放置すれば、我が国の防衛・航空宇宙産業は緩慢な死を迎えるか、外国資本の傘下に入って生き残るかしか道はあるまい。
我が国の安全保障にとって独自の防衛航空宇宙産業とその生産基盤の維持は必要である。これを維持発展させるためには民間機市場への参入が不可欠である。いまこそ内閣府あるいは首相官邸が音頭をとって政治主導で省庁の垣根にとらわれない、長期的視野に立った政策を立案実行するべきである。
編集部より:この記事は、軍事ジャーナリスト、清谷信一氏のブログ 2018年7月19日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、清谷信一公式ブログ「清谷防衛経済研究所」をご覧ください。