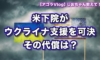12月25日、日本が国際捕鯨委員会を脱退した。
「IWCはもはやクジラ愛好家の集まりになっている」(外務省幹部、12月30日 産経新聞)との認識もあり、今後も科学的客観的な議論ももはや期待できないとの判断から、十分な検討や各国への根回しをした上での脱退表明とのこと。まずは政府の決定を支持したい。

Wikipedia:編集部
自分たちの「正義」を戦う強硬な人々
ふと思い出したのが、私が大学生の頃にアメリカで育った従兄弟が日本に一時帰国したときの出来事だった。彼は、小学校低学年の頃までは日本の普通を絵にかいたような生活だったのだが、父親の仕事の関係でアメリカに移り育った。一時帰国した頃は中学生くらいになっていたのだが早くも完全なアメリカ人になっていて驚いた。
顔は日本人だが、言葉はもはや英語ネイティブで日本語を忘れはじめていた上に、何よりものの考え方や振る舞いがいちいちアメリカ人なのである。お互い片言の英語と日本語でのコミュニケーションに苦労しながらも久しぶりの再会を喜び、ある喫茶店のようなところに入った。そうすると隣の席の集団がたばこを吸いだした。すると彼は心からの不快感と軽蔑感を顔にあからさまにしながら無言で隣の席をメニューか何かでパタパタと激しくあおぎ出したのだ。
当時まだ日本では、たばこの害とか嫌煙などという概念がまったく一般的ではない時代である。飛行機でも新幹線でも喫煙が普通だった。隣の席の集団は何が起きたのか完全に面喰ってしまってどう反応して良いかさえわからない体だった。日本人の感覚からはストレート過ぎる表現でもあり、隣がそれほど強面でなかったことを幸いに早々に席を立った記憶がある。
店を出てから、従兄弟に日本ではたばこを吸うことは成年であれば広く許されているのだから、仮に煙が不快でやめて欲しいとお願いするにしても、いきなりあんなやり方はないのではないかと質したがまったくとりつくしまがなかった。喫煙という有害な行為を不快にも他人に影響するかたちで行う野蛮人に知らしめる当然の行動であるという体であった。
彼との再会は色々とカルチャーショックもあったが、多くのことはやはり子供の頃一緒に遊んだ従兄弟同士、和気あいあいと楽しいものだった。ただこの件に関しては、どう話しても彼に日本の常識に穏健にあわせてもらうことはできないと悟らざるをえなかった。もう一度同じシチュエーションがあれば、彼は同じ行動をしただろう。いやもっと過激化したかもしれない。
その後私は海外に行く機会を多く得たが、特にアメリカで彼のようなスタンスや態度の人々に多く出会い、彼の当時の振る舞いは彼の地ではスタンダードとは言わないまでも“意識高い系の人”にとってありえるものであることに気が付いた。つまり、ポリティカルコレクトネスという言葉もあるが、歴史的に実現されていない「正義」がある時点でイシュー(起案)化されると、その「正義」の側に立って戦う人々である。イメージとしては、アルゴア的というか民主党的な人々である。
実際、彼らは女性やマイノリティの地位向上やタバコの受動喫煙問題などで多くの成果を勝ち得てきている。現時点で言えば、地球温暖化などが彼らのイシューであるだろうか。(ただし、アメリカは一部「先住民生存保存捕鯨」を容認しているので、こと捕鯨については国をあげて反捕鯨の急先鋒というわけではない)
さて困ってしまうのはここからで、その「正義」が本当に誰にとっても「正義」と言えるものであれば良いのだが、例えば「毛皮」や最近では「ニワトリ、牛、豚などの拘束飼育」などまだまだ議論の練度が低い段階のイシューについても、問題視し激しい活動を展開する人々もいたりする。
捕鯨もそうだが、それぞれ動物がからむ事案だけにセンチメント過激化しやすい傾向がある。何より、彼らはそれを「正義」と自らが定義した時点で、問答無用であり非常に強硬だ。背景としては文化思想的な違いがあると思うが、特に日本人の多くが前提とする“八百万(よよろず)の神”的な世俗的宗教観から遠い、一神教的な潔癖主義が大きく影響しているようには感じてしまう。
余談だが、IWC脱退表明が12月25日なのは、クリスマスプレゼントというアイロニーを込めているとしたら、我が政府もなかなか大人のウイットと余裕があるなとニヤリとしてしまうが、これはきっと考え過ぎなのだろう。
白人がその他の人種に対して自然体でもつ人種的な偏見や異文化への理解の低さ
さて、もう一点反捕鯨の背景にあると思われてならないのが、やはり白人がその他の人種に対して自然体でもつ人種的な偏見や異文化への理解の低さだ。IWCにおける捕鯨賛成国、反対国は一概に白人・非白人で色分けできないが、実際のところ反捕鯨を主導している人々が主に白人であることは周知の事実である。
最近の出来事としては、ミスユニバース世界大会の米国代表が、カンボジア代表やベトナム代表を「英語も話せない」と嘲笑し炎上した件があった。あのときも米国代表のかたわらで「ウンウン」とうなずいていた一人は奇しくも反捕鯨の急先鋒オーストラリア代表だった。
あまりにも分かりやすいかたちで、彼女たちの黄色人種に対する上から目線が露呈した。小学生レベルのお粗末な話であればこそ、彼女たちが生理レベルで感じている白人以外の文化を軽んじる本音が良く表れていた。
白人社会とつきあいがある日本人であれば、彼らがオフィシャルなマナーとしてもっているフレンドリーさやフェアの精神と裏腹に、ミスユニバースがいみじくも示した類の非白人文化への侮りが意外と根深いことを多かれ少なかれ感じずにはおれないだろう。
侮られている限りは何も進まない。
そうこれは良くも悪くも子供の喧嘩の縮図でもある。
バカにしてくるバカがいれば、こちらも根性を見せるしかない。頭から自分を優位と決めつけているガキ大将も相手が反撃の意志を見せればひるみもするし、そこで初めて相手が何を考えているのかを考え始めもするだろう。
まずは、日本政府が示した、IWCを脱退し理不尽をきっぱりと拒否する姿勢は是としたい。
侮られている限りは何も進まない。
しかし、ここから先対立構造が鮮明になった上での相剋には、究極国力なくして勝ち得ないだろう。最近国力の衰えを自他ともに指摘される日本でもある、たかがクジラなどと考えずこだわっていきたいものである。
自らのプライド、アイデンティや文化を守るために自己を涵養する。
国家であっても個人であっても当たり前に過ぎる結論に違いない。
最後に、矢沢永吉のエピソードを紹介したい。
子供時代、究極に貧乏だった矢沢は、金持ちのガキ大将から顔にケーキをぶちまけられる。もちろん「この野郎」と頭にきて反撃するところなのだが、その前に「このケーキをどうしても舐めたい」という気持ちが先にきてしまったと彼は振り返っている。侮れられて、ケーキをぶちまけられることも屈辱だが、そのケーキさえ舐めてみたいと思ってしまう話はどうしょうもなく切ない。しかし彼はその時その場の殴り合いの段取りを考える以上に、「これは(こいつの)上に行かないと解決しないな」と咄嗟に悟ったとのことだ。
結果は誰もが大好きな永ちゃんのサクセスストーリーだ。
もちろん私も大好きである。
—
秋月 涼佑(あきづき りょうすけ)
大手広告代理店で外資系クライアント等を担当。現在、独立してブランドプロデューサーとして活動中。