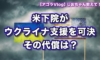公共発注において競争入札が原則とされているのは、その手続が競争させる側(ここでは発注機関)にとって最も望ましい条件での契約を可能にしてくれる、という期待があるからだ。競争のメリットは公共発注にのみ存在するのではなく、取引一般についてもいえる。売り手側にも買い手側にも競争環境を整えることにより、経済社会において最も望ましい結果が生み出される、という信頼が存在する。
会計法や地方自治法は競争入札(一般競争入札)を原則とし、随意契約を例外としているのはそのためだし、独占禁止法が競争制限行為を禁止するのもそうだ。ただ、高度成長期の成功体験があるので、当時ほとんど機能していなかった独占禁止法へのアレルギーが昭和の世代を中心に少なからず存在する。競争は日本社会に馴染まない、と。

公共工事のイメージ (はむぱん/写真AC:編集部)
かつては随意契約や指名競争入札が当たり前のように用いられていた。指名「競争」といっても名ばかりで、実質は業者間の協調によって結果(落札)が決められ、競争は骨抜きにされていた。落札価格は予定価格とほぼ一致していたが、それが「競争価格」だ、と発注機関は強弁してきた。
法令が追求する競争価格と予定価格の根拠となる発注機関の積算とを一致させることで、「予定価格=適正価格」という「神話」を作り出し、事前に計画した予算を過不足なく消化できるという「官の無謬性」の体裁を作り上げてきた。
落札率100%なのだから余ることもないがそこに抵抗感はなかった。仮に足りなかったら安い値段でどこかの業者に強引に引き受けさせることができた。このことを「請負」の文字を使って「請け負け」などと表現してきた(それができたのは随意契約や指名の裁量権を発注機関が持っていたからだ)。
単年度予算という制約の中で、競争によるメリットを捨て去ってまで、言い換えれば談合という犠牲を払ってまで、(表面的な)「予定調和」のメカニズムを維持しようとしてきたのである。それが昭和の時代だった。
かつての常識は平成の時代に通用しなくなった。一般競争は当然の前提となり、法令の要請と実態とが一致するようになった。随意契約や指名競争入札は、専ら批判の対象となり、そのメリットが指摘されることはほとんどなくなった。
各発注機関は「随意契約」といわれる手続に拒否反応を示すようになった。より正確にいうと、拒否反応を示す世論に敏感になった。形だけでもいいから一般競争入札を徹底している「体裁」を重視し、それが一者応札であろうが、予定価格ぴったりであろうが、あるいは不調や不成立であっても、一般競争入札を用いたのだから、そこで得られた結果が正しいのだ、と強弁する(せざるを得ない)発注機関も多々ある。時代は変わっても行政が「体裁」に拘るのは変わらないようだ。
随意契約のメリットは、手続にかける時間的短縮が可能であること、事前の交渉が柔軟に進められること、総合評価方式のような契約手法との比較では煩雑さを回避できること、さまざまである。そのデメリットは、競争が欠如していること、競争という手続によって満たされただろう透明性に欠けることである、といわれている。
ただ、競争入札であっても競争を骨抜きにすることは可能であるし、不透明な形で実施することも可能だ、ということには注意しておきたい。要は仕組み次第ということだ。
裏を返せば、随意契約であっても、競争的要素を組み込むことができる(事前確認公募型の随意契約、企画競争等がその例だし、見積り合わせもそうだ。公開型の見積り合わせの方式もあると聞く)し、情報公開を徹底することで透明性を確保することもできる。競争入札か随意契約か、という二元論ではなく、各方式のメリットを最大限にし、デメリットを最小限にするような「最適な組合わせ」を模索すべきだ。
しばしば競争入札のメリットを説く論者が強調するのが価格低下であるが、そもそも競争においては価格だけではなく、品質も重要だ。競争入札の組み方次第では価格よりも品質重視の契約者選定が可能となる方法もあるし、分野によっては多用されている。
特定の業者(あるいは事業者団体)が他の追随を許さない、あるいは存在する唯一の適正な契約相手であるというならば、その説明責任を果たした上で、法令の枠内で堂々と随意契約すればよい。しばしば随意契約をめぐる住民訴訟を見聞きする。地方自治体の場合、司法の判断が一つの方向性を見出す。それが適正化の担保となっている。国の場合はやや状況が異なる。会計検査院の対応の鍵となるが、議員による問題喚起も重要である。
音喜多駿氏がブログ記事(「時間がないから、競争入札は無し?!」)で、参議院議員会館の改築工事が随意契約で行われたことを問題視している。このような意識を個々の議員が先鋭化させることは大歓迎である。どんどん問題提起したらよい。それによって透明性も高まるだろう。
競争入札の場合、競争の結果が契約の合理性を自ずと説明する(但し競争のルールが適正な場合に限る)。随意契約の場合そうはいかない。発注機関が自ら積極的にその説明を行わなければならない。それは一定の知識を有する外部の人間が、その適正さをチェックできるくらいに透明である必要がある。情報公開は公共発注の適正化のための生命線だ。
欧州では、公共発注の適正化に向けて、Digital Whistleblowerという発想が広く共有されている。公共発注に係るデジタル情報へのアクセシビリティーを高めることで、誰もがその不正、不効率を指摘することができるような環境整備を行うことが重要であるという考え方がその背景にある。
実際、欧州における公共発注のデジタル・データベース化とその徹底した公開性の推進には目を見張るものがある。日本・EUのEPA(Economic Partnership Agreement)で公共発注が大きなイシューとなったが、透明性の問題について「欧州並み」を日本が実現するのはいつのことになるのだろうか。
競争入札はやり方次第でいくらでも骨抜きにできる。競争入札が実施されているからといって無批判に評価するのは危険である。同時に随意契約も必要な場合は必要であることをより正面から認めるべきだ。それを闇雲に批判するのはナンセンスである。随意契約にも競争的なそれもある。特命随意契約の候補を立てつつ公募をかけ、応募する業者が現れたら競争入札を行うという事前確認公募型の随意契約はその一例である。議員会館のケースはそれに馴染むものなのかもしれない。
時代は令和である。昭和の時代の反動から公共発注方式に対する闇雲な批判や思考停止の礼賛が平成の時代まかり通ってきたが、この新しい時代、真に納税者の利益になるものは何か、という「実質」をより深く考えて行かなければならない。

楠 茂樹 上智大学法学部国際関係法学科教授
慶應義塾大学商学部卒業。京都大学博士(法学)。京都大学法学部助手、京都産業大学法学部専任講師等を経て、現在、上智大学法学部教授。独占禁止法の措置体系、政府調達制度、経済法の哲学的基礎などを研究。国土交通大学校講師、東京都入札監視委員会委員長、総務省参与、京都府参与、総務省行政事業レビュー外部有識者なども歴任。主著に『公共調達と競争政策の法的構造』(上智大学出版、2017年)、『昭和思想史としての小泉信三』(ミネルヴァ書房、2017年)がある。