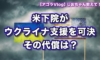大学内ネットの海外接続が不調なのを口実に、しばしブログの更新を怠ってきた。だがどうしても記録したいことがあり、なんとか困難を克服した。久しぶりに文章を書いてみようと思う。

(10月20日『岐阜新聞』県内版)


10月19日、岐阜県日中友好協会に招かれ、当地で講演をした。同協会がシリーズで行っている「ぎふ・中国くるぶ交流講座」の一コマである。「くるぶ」とは「聴く」「交わる」「学ぶ」の語尾を集めたもので、うわべだけではない、中身のある、血の通った関係を求める営みであることを、同協会理事長で元岐阜新聞論説委員の土屋康夫氏と接する中で感じた。

(閉会のあいさつをする土屋康夫氏)
土屋氏は私が3年前、東京で行った日中関係学会の講演を傍聴に来られたうえ、今年4月、私が学生を率いて日本取材ツアーを行ったときには、京都祇園の取材現場まで足を運び、講演の依頼を念押しされた。私はよき理解者に出会った縁に感謝し、交流講座をより有意義なものにしたいと気持ちが高揚した。
講演会の参加者はみな中国に何度も足を運び、日中関係に一家言を有する方々であり、また私にとっては人生の先輩も多い。そこで、ありきたりの中国観ではなく、独自の体験に基づき、自分ならではのお話をすることにした。広東省の汕頭(スワトウ)という日本人になじみの薄い土地で、元新聞記者の日本人が、中国の若者を相手にジャーナリズム、異文化交流の意義を教える中で感じたこと、考えたことを、話のテーマに絞った。
中国というとてつもなく巨大で、容易にはとらえどころのない国をつかもうと思えば、わかりやすい、平易な答えを探したくなるのが人間の心理だ。さもなければとても不安な気持ちになるだろう。だが、日本かかつてそうやってこの国を見誤り、そして自らの進む道さえ見失ったことを忘れてはならない。
異文化、特に隣人と接するにあたっては、人間関係と同様、手間暇をかけ、無駄と思えるような時間をいとわず、じっくり腰を落ち着けて向き合う必要がある。そうしてこそ、本当の素顔が見え、心を通わせることができる。これが私が体で学んだ文化コミュニケーションの心得である。
これまで留学生、特派員として北京、上海に住んだが、汕頭という地味な南方の町に暮らしてみて、改めて地方文化の根深さ、多様さに目を開かれた。ここには潮州と汕頭を合わせ「潮汕」と呼ばれる文化圏がある。広東省とはいっても、言葉、飲食、信仰など多方面にわたって広州や仏山とは異なり、福建の文化により近い。
中国は一人っ子ばかりだと思っている人は、この土地にくると一人っ子を探すのが難しいことを知ってびっくりする。伝統的な祭りがなお伝わり、祖先信仰が色濃く残っている。どこに行くにも茶道具は必需品で、お茶を飲み交わしたことが友情のあかしとなる。祖先は中原地方から逃れてきたため、方言に古代の発音を残す。だから、日本語の音読みに近い言葉が多い。「漢字」「新聞」「自由」など、発音を聞けば驚くほど似ている。
大きな概念を持ち出すと、多様な文化が見過ごされてしまう。その多様さを実感できなければ、庶民の生活や文化を理解することは難しい。テレビなどで中国を語るいわゆる専門家、評論家には、この手の例が非常に多い。ステレオタイプに甘んじ、大衆に迎合すれば楽ではある。だが、偏見や誤解を助長し、拡大させている責任は重いと言わざるを得ない。
私は大学の授業で、メディアが報じる政治家の会談や政府間の取り決めだけが日中関係ではない、と教えている。両国のトップが会えば関係が改善され、会わなければ悪化するといった単純なものではない。長い歴史の中で培われた深い交流を忘れてはならない。日本人である私が教壇に立ち、中国の若者と向き合い、議論しあうこと、これもまた日中関係のひとつである、とアピールする。
講演会後、土屋氏から、「加藤さんの話を聞いて、中国の若者が日本のアニメだけでなく、深い文化に関心を持っていることは驚きだった」と聞かされた。
私は3年前から毎年、学生を率いて日本各地を取材する「新緑」プログラムを行っており、講演でもその内容を詳しく説明した。取材テーマは、環境保護から高齢化社会、地域振興、ロボット文化、おもてなし、宗教など多岐にわたり、しかも中国国内の有力メディアに記事を発表し続けている。権威あるメディアでも、中身があれば学生の記事を掲載してくれる。
頑なに自前主義を守っている日本メディアでは考えられないことだが、中国ではできる。ネットを中心に、メディアに参画しようとする意欲は、より自由な環境にあるはずの日本よりも中国の若者の方が強いように思う。一党独裁によって画一的な言論統制が行われているというステレオタイプは、そろそろ脱したほうがいい。
講演では、学生たちの記事のほか、有力サイトで流れた映像作品も2本上映した。学生でもプロ並みのレベルを誇っていることは十分伝わったはずだ。十分に事前の下調べをし、入念な準備をし、心を開いて日本の社会に接し、それを完成された報道作品に仕上げる。その一部始終に二人三脚でかかわった教師として、彼女たちの熱意、まじめさ、真剣さをじかに感じてきた。こうした感動もまた講演の参加者と共有できたのではないかと自負している。


講演の最後に、岐阜にも「新緑」チームを連れてきたいと話すと、歓迎の声が上がった。交流のティータイムを終えた後、出席できなかった名古屋外国語大教授で元中日新聞論説委員の川村範行氏が名古屋で一席を設けてくれ、土屋氏も合流した。熱心に、地道に日中交流を続けている川村氏は、力強い味方だ。土屋氏からは、学生を何組かに分けてホームステイを引き受けてもよい、とのありがたい提案もいただいた。大学で待つ学生たちには、なによりもの手土産になった。
土屋氏は、実はこの日の講演会をもって一線から退くことも考えていたというが、この夜の会食では、引き続き頑張るとの決意を聞くことができた。もし、私の話が少しでも影響していたのだとしたら、ありがたい限りである。私にとっても、「新緑」の訪日活動を続ける元気をいただいた。
森ビル名誉顧問の星屋秀幸氏、トヨタの阪本敦氏ら、懐かしい方々と再会できたのも望外の喜びだった。南京の旧友、韓金竜氏は、自分の代理として名古屋にいる長女を参加させてくれた。忘れがたい、実りの多い岐阜、名古屋行だった。

編集部より:この記事は、汕頭大学新聞学院教授・加藤隆則氏(元読売新聞中国総局長)のブログ「独立記者の挑戦 中国でメディアを語る」2019年10月22日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、加藤氏のブログをご覧ください。