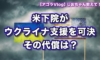>>>世界のラグビー事情:フランス編はこちら
>>>世界のラグビー事情:イングランド編はこちら
アイルランド、スコットランド、ウェールズの三国を「ケルト三国」とまとめてしまうのは、いささか乱暴ですが、ことラグビーに関してはこの三国が置かれた状況は共通していることが多いです。
その一。ラグビー競技人口が少ない。
アイルランド:10万人
スコットランド:5万人
ウェールズ:8万人
(参考:フランス:54万人、イングランド:38万人、日本:10万人)
その二。人口そのものが少ない。つまりファン人口の「のびしろ」が限られている。
アイルランド:480万人
スコットランド:540万人
ウェールズ:300万人
(参考:フランス:6700万人、イングランド:5600万人、日本:12000万人)
その三。イングランドには負けられない。
この三国は、1995年以降のラグビー・プロ化の波を乗りきるにあたっても、似たような課題を抱え、最終的には共同で現在Pro14とよばれるプロ・ラグビー・リーグを創設することで対処していくことになります。
クラブ・ラグビーからの発展
プロ化によって三国でまず表面化したのは、フランスやイングランドと異なり、従前のクラブ組織では対応できないという事実でした。個々のクラブの限られた資金力やサポーター層に頼っていたのでは、みんなジリ貧になってしまう。結果として将来有望な選手たちは海外クラブに引き抜かれてしまい、自国のラグビーはヨーロッパにおける実質2部リーグという存在に甘んじなければならない。三国のラグビー協会は、こうしたシビアな現実に直面することになるのです。
この逆境に対して、一番恵まれた素地をもっていたのはアイルランドでした。アイルランドの国内ラグビーにも、クラブ・チームをベースとしたリーグ組織がありましたが、1920年代からすでにアイルランドの4地方(レンスター、マンスター、アルスター、コナハト)それぞれの代表チームによる対抗戦(Interprovincial Championship)の伝統がありました。
アイルランドのプロ・ラグビーはこれらの地方代表チームを、アイルランド協会を最終的オーナーとしてプロ組織化することにより発展成長します。これにより各地方チームはサポーターを継承するとともに、それぞれの地域におけるラグビー普及と、ジュニアからシニア、そして代表候補という、プレーヤーのキャリアをサポートし、代表チームへの健全な選手供給源となります。
結果として、以前はヨーロッパ5カ国対抗(現6カ国)大会で弱小であったアイルランドは、優勝候補の一角をしめるようになり、現在のワールド・ランキングでは南ア、ニュージーランド、イングランドに次ぐ4位を占めるまでになりました。
アイルランドの幸運の裏返しがウェールズです。1970年代に黄金時代を築いていたウェールズのラグビーは、個々のクラブ組織とその伝統が強力すぎるというレガシー問題を抱えています。
その結果、従前のクラブ組織から、地域ベースのプロ・チームへの移行に手間取ることになります。以前はウェールズ・プレミア・ディヴィジョンとして10のクラブ・チームが存在してたのを、紆余曲折を経て、現在Pro14に参加する4チーム(カーディフ・ブルーズ、ドラゴンズ、オスプレイズ、スカーレッツ)に統合したのですが、アイルランドと異なり、これらの新チームは協会から独立した団体。そしてクラブとしての伝統を持たない新チーム内では、現役選手はさておき、スタッフや経営陣の間に前身クラブへの帰属心からの派閥間摩擦が絶え間ない。

アラン・ウィン・ジョーンズ(Wikipedia:編集部)
この内幕事情はウェールズ協会(ひいては代表チーム)との関係、そして各チームの運営とパフォーマンスに直接影響を与えることとなります。かつての日本のプロ野球ではないですが、「フロントがアホやから...」的発言が、なんと現代表キャプテン(オスプレイズ所属)のアラン・ウィン・ジョーンズから出てくる始末。ウェールズのプロ・チームが落ち着くまでにはまだしばらくかかりそうです。
競技人口で圧倒的に劣るスコットランドの事情は、ますます深刻。もともとスコットランドのラグビーは「ボーダー」と呼ばれる南部、イングランドとの国境近い地域がハートランドで、以前のトップ・クラブもそのほとんどがこの地域に集中し、隣り同士の村対抗的なものだったのです。
プロ化にあたってスコットランド協会は、アイルランド同様に協会自体を母体としてエディンバラ、グラスゴーの2大都市と、このボーダー地域のチームをボーダー・リーヴァーズ、そしてその他地域をカレドニアン・レッズとして4チームまとめますが、たちまち立ち行かなくなり、結局エディンバラとグラスゴーの2チーム体制になりました。
2017年のWalesOnllineサイトの記事によると、Pro14所属チームのチーム予算推定額は以下の通り。
アイルランド:協会から4チームへ、年間総額約3000万ポンド(約43億円)が支給。各チームの年間チーム予算は約650万〜700万ポンド(約9億〜10億円)。
ウェールズ:カーディフ・ブルーズ、オスプレイズ、スカーレッツの年間チーム予算は約500万ポンド(約7億円)。ドラゴンズは約350万ポンド(約5億円)。
スコットランド:エディンバラは年間約450万ポンド(約6億円)。グラスゴーは約510万ポンド(約7億円)。
WalesOnlineの報道によると、Pro14は2018年、試合の英国向け放映権を年間3000万ポンド(約43億円)で売っています。
代表ヘッド・コーチの重要性
多くの競技人口と、さまざまな問題を抱えながらも、まがりなりにも自国プロ・リーグが活動しているフランスやイングランドは、例えるなら大容量エンジンでパワー勝負するフェラーリ型のレーシング・カー。
ひるがえって、これらのケルト三国は、いうなれば比較的小さな排気量のエンジンを高回転させるポルシェ型。この高回転エンジンを効率よく回していくためには、それぞれの国民の挙国一致的なラグビー・ファンの盛り上がりによる燃料噴射装置が必要不可欠。したがって国代表チームのパフォーマンスが直接的に大きな影響力を持つことになり、代表ヘッド・コーチの重要性が増すことになります。
もちろんそれを理解している三国の各協会は、ヘッド・コーチの人選に意を尽くし、結果として自国民ではないけれど、コーチとしての手腕と実績を世界的に認められたヘッド・コーチを海外から招聘。元日本代表ヘッド・コーチで、今はイングランドを率いるエディ・ジョーンズ氏に代表されるような、いわゆる「プロ・コーチ」の時代に先鞭をつけることになります。
ワールドカップ日本大会までウェールズを率いたウォーレン・ガットランド氏はその代表。2007年から12年間にわたってウェールズのヘッド・コーチを務め、その任期中、6カ国対抗優勝4回、その内3回を全勝で飾るいわゆる「グランド・スラム」をものにするという好成績を収めました。ウェールズ協会とその傘下チームのゴタゴタが続く中で、代表チームの活躍は、ウェールズのラグビーにとって貴重な元気のもとだったのです。

ジョー・シュミット(Wikipedia:編集部)
同じく、日本大会を最後に退任したアイルランドのヘッド・コーチ、ジョー・シュミット氏は2013年からアイルランドを指導。6カ国対抗優勝3回、グランド・スラム1回、そしてそれまでどうしても勝てなかったニュージーランドに2勝(2016、2018)するという偉業を成し遂げました。
しかし、対戦相手にそのプレー・スタイルを徹底的に研究され、前評判が高かったワールドカップ日本大会では、予選リーグで日本戦を落とし、準々決勝でニュージーランドに完敗するという、残念な幕引きになってしまいました。
日本に敗戦した際のアイルランドのラグビー関連メディアの落胆ぶりはおそろしく、その悲壮感はサッカーに負けた南アメリカの国情につながるものが感じられるほどでした。

ヴァーン・コッター(Wikipedia:編集部)
スコットランドは2014年から、ガットランド氏やシュミット氏と同じくニュージーランド出身のヴァーン・コッター氏をヘッド・コーチに迎えます。それまで散々な成績で以前のヘッド・コーチたちが2シーズンともたなかったスコットランド・チームを任されたコッター氏は、2015、2016、2017と着実に好成績を収めていたのですが、2017年に元スコットランド代表のグレガー・タウンゼンド氏にとって代わられます。
ニュージーランドからフランス、スコットランドと、いわばコーチ職の他流試合を重ねてきたベテラン、コッター氏に比べると、タウンゼンド氏はそのコーチとしてのキャリアを常にスコットランドで積んできたスコットランド協会の箱入りコーチ。就任直後の2017〜18年シーズンこそはコッター氏の遺産で好成績を収めますが、2019年日本大会では初戦アイルランドに圧倒され、日本戦では選手たちの最後の奮闘もむなしく、予選敗退となったことはみなさんもよくご存知。
その後、タウンゼンド氏はチームのスター選手であるフィン・ラッセル選手とウマがあわなくなり、フィン選手が代表召集されない事態に発展。タウンゼンド氏の苦闘は、今のラグビーにとってヘッド・コーチ職がいかに高度なスキルと経験、そしてそれらを総括した資質を要求するものかということの証左と言えると思います。
日本ラグビーの好ライバル
様々な課題を抱えたこれら三国のラグビーは、そのおかれた環境条件からくる制限から、常に改善への努力と試行錯誤を必要としています。そうした意味で、日本のラグビーにとっては現時点における格好のライバルであり、学ぶべき対象なのです。