
ロンドンのウォータールー駅構内は公共空間の1つ(撮影筆者)
「実名報道を考える」では、共同通信編集局特別報道室の澤康臣編集委員(当時。4月から専修大学文学部ジャーナリズム学科教授)に聞いた現場の話を数回に分けて紹介している(澤氏の経歴は記事の最後に付記)。
第1回目:新型コロナ実名報道を考える:なぜどのように匿名志向が生まれたか
第2回目:新型コロナ実名報道を考える:なぜ実名報道が基本になっていくのか
今回は、匿名志向の背後にある考え方、これまでの教育、そして当局と報道機関との緊張関係、リークの意味について聞いてみた。
なお、同氏の話はあくまで個人的見解であり、所属組織とは関係ないことを付記する。
「出るくいは打たれる」という空気
―日本での実名・匿名報道の議論について、普段から思っていらっしゃることをお聞かせ願えますか。
日本の「出るくいは打たれる」空気は非常に大きな影響を与えていると思います。注目を浴びたり、目立ったりは特別なこと、危険で怖いこと、攻撃を受けることだと感じる人は少なくないのではないでしょうか。私自身もそういう感覚はあります。
教育の過程で「意見を言う」「思ったことを言う」ことが十分に推奨されず、「おとなしく聞いている」ことのほうが安心な教室になっているのではないかと思います。英国、米国など英語圏では「ショウ・アンド・テル」(見せて語る)という授業が小学校低学年などで広く行われているんだそうですね。何かをみんなの前で説明し、質疑もあるとか。
「これは真似したい!欧米では定番の“Show and Tell”って知ってる?」
パブリックスピーキングは出来て当たり前? アメリカの学校における取り組み
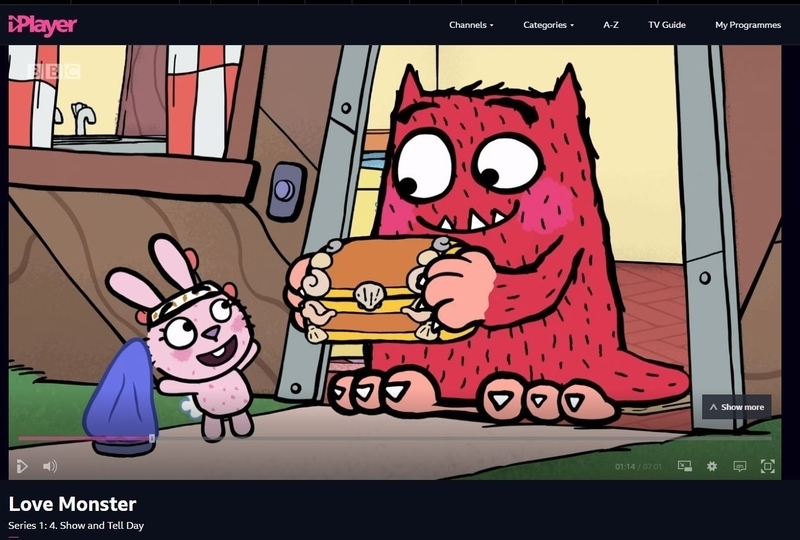
BBCの子供番組「ラブ・モンスター」の「ショー・アンド・テル」の画面(BBCのウェブサイトから)
パブリック・スピーキング(公共公開の場でみんなに話すこと)に子どもの頃から慣れていくのだと思います。民主主義の主権者として意見を考え意見を言う訓練は、とてもすばらしいと思います。記者として赴任した米国では本当に街角取材が楽で、政治、社会問題についてほぼ誰でも実名OKでどんどん語ってくれます。それにはこんな基礎があるのでしょう。
どんな子も一人一人みんなの前で自分の意見を言う、つらい目に遭ったことを表明した子はブレイブ(勇敢)でありヒーローである、というようなことは日本ではどうなんでしょう。少なくとも私の子ども時代は、目立たず、はみださず、それが安全安心--という学校でした。もっとも私はお調子者で、当時でいう「目立とう精神」がある例外的なヘンな子だったのですが…。
今はどうなんでしょう。アクティブラーニングが取り入れられつつあるそうなので、意見を言ったり質問したりが活発化するといいと期待しています。
それにしても、日本では名乗って話すという文化がとても弱いと感じています。講演会やシンポジウムで質問をする人も、英語圏だと「私の名前はジョン・スミスで、何々の仕事をしています。私の質問は…」と話し始める人が多いのに対し、日本では全く名乗らなかったり「一般のもので…」と言ったりというようなことがふつうの風景です。「属性で判断するから属性情報には価値があるが、誰々という一個人であることの価値はない」、そういう感じです。
一個人であることの価値、一個人として認識することの意味が無いのなら、出る杭が打たれたり、目立って気恥ずかしい思いをするマイナス面のほうがずっと深刻です。名前を呼んだり知らせたりすることは「尊重」ではなく「攻撃」というのが、日本の匿名社会に流れる空気なんでしょうか…。
だから、できごとを語るときも固有名詞を「某」にしてみたり、匿名、イニシャルにしてしまうことが「配慮ある語り方」「品格ある者の振る舞い」となるのかも知れません。
例えば、明らかに槇原敬之さんの事件のことを論評しているのに、ことさらに「覚醒剤所持の罪で起訴された人気男性アーティストが…」と表現し、「槇原敬之さん」という名前を避けるというような具合です。明らかに槇原さんの個別ケースを指していて、書き手も読み手も槇原さんのことだと分かっていることが前提になっている文章でもです。それが何となく上品なしぐさであるかのような共通認識があります。
あるいは、虐待関係だったと思うのですが、ある学会に取材を兼ねて出席したとき、米国からのゲストが米国で実際に起きた虐待事件のいくつかを紹介しました。パワーポイントを使い、加害者や被害者の名前、写真なども明示されたのですが、主催者の日本側学者はちょっと慌てたように「この個人情報などはここ限りで」と注意していた場面が印象的です。米国のゲストスピーカーはそんなことは一切求めていなかったのに、です。
―あるエピソードを思い出します。昨年、日本に一時帰国していたのですが、性被害者が体験を語る集会(「フラワーデモ」)がありまして、行ってきました。記録にしたいと思い、スマートフォンで写真を撮ろうとしたら、「ダメ、ダメ」「そっちから撮ってはダメ」と言われて、驚きました。
被害者の顔を出さないようにという配慮からでしたが、公空間での集会でしたので撮影は自由なはずで、それが駄目であることを理解するのに時間がかかりました。被害者への配慮が悪いというのではもちろん、ありません。ただ、公空間での撮影が駄目ということがすぐには呑み込めなかったのです。

ロンドンのウォータールー駅構内を歩く人々。公共空間であり、撮影は自由だ(撮影筆者)
実際、「公空間」など「パブリック」(公共公開の、みんなの)という概念が日本にはなかなか見当たらなかったり、あってもごく限定的だったりするように思います。
米国であれば、報道された事件や公開裁判になった事件であれば加害者名や被害者名も「パブリック・インフォメーション」(公共公開情報)となり、隠す必要がないし、隠すのはおかしいという感覚があります。
日本の場合は広く報道され公共公開情報となったような事件でも、名を呼ぼうとせず「千葉県野田市の10歳女児」という表現にこだわる人はいますし、とくに研究者や法律家の間に人名回避の傾向があるような印象を受けます。
実際のところ、虐待を受け死亡した千葉県野田市の栗原心愛さん(当時10歳)、東京都目黒区の船戸結愛さん(当時5歳)の事件は広く報道され、関係者や関係官庁の人々をはじめ多くの市民の努力を生みだし、虐待防止法が強化されました。
米国や英国は「メーガン法」など、法律制定の原動力になった市民の名を法律の略称にすることがありますから、彼の地ならこの改正虐待防止法は「心愛・結愛法」と名付けられたに違いないと思っています。
日本では法律や制度を作ると言えば国会議員や官僚であって、心愛さんや結愛さんという幼い市民が社会を変えたと受け止めることは、あまりなじまない社会なのかも知れません。
―この問題で、当局側(警察・検察・政府、企業他)が情報を握っていることを問題視する指摘もあります。メディアは当局からの情報のアクセス権を維持したいので、当局の情報拡散・あるいは隠すことに翻弄されている、と。これはどんな状況なのでしょう?問題だと思われますか?(「なぜマスコミは実名報道にこだわるのか? メディアと社会との間にある意識のズレ 」- 佐々木 俊尚)
佐々木さんが書かれた当局とメディアの「情報闘争」については自分の実感と重なる部分も一部あります。記者が当局内に秘密情報源をつくって「密かに当局の動きを把握できる」状態に置くこと、そうすると当局は「メディアが何を知っているのか」掌握しきれずそこが不気味で、自制にもつながることは確かにそうだろうとおもいます。
佐々木さんの記事では、当局に被害者の実名を含む事件事故や捜査内容の詳細を「公表」させようとすることと「情報闘争」との関係についてはあまり詳細に書かれていません。
が、事件事故や捜査内容に関して実名を含む詳細情報が公開、公共の情報となることは、当局が情報をコントロールしている状態から市民が情報を持つ状態に切り替わることです。とくに実名など固有名詞情報は事案検証に不可欠な「タグ」となります。しかし、これが「公表」されなければ、記者に限らず、研究者にせよ社会運動をする人にせよ、「当局だけがもつ情報」を知るためには「厚意」や「リーク」に頼るほかありません。
リークの本来の意味とは
なお「リーク」というと当局が都合の良いことを記者に流してメディアをコントロールする不公正な手法のように思われがちですが、それはどちらかというと「リーク」つまり情報漏洩じたいではなく、情報コントロール、英語で言うと「スピン」ではないでしょうか。そして、取材については佐々木さんが書かれた内容には現実味があり、逆に突然記者に声がかかり「良いことを教えてやろう」みたいなことが起きるわけではありません。
最近ですと、東京高検の黒川弘務検事長が63歳の定年を超えて雇用が延長されたことが「官邸お気に入りの黒川氏を検察の中心に置くための特別扱い」と批判を受けた問題がありますが、この延長について、検察幹部会議で疑問の声が上がったという異例の事態が報じられました。こんな非公開会合の中身が出ることもリークの一種です。
これも検察による官邸とのバトルの一環という見方はできますが、市民にとっては必要な情報が法の網をくぐって漏洩された意義は軽視できないと思います。
どんな情報であれ、当局が秘密として独占する情報が多ければ多いほど、メディアにせよ研究者にせよ、市民と当局との力関係は平等ではなくなります。
検証に不可欠なタグである「誰が」という基礎情報すら当局者に頭を下げ「厚意」や「リーク」に頼らないと得られないとなると「人間関係を良好にしておかねばならない」事態に陥ってしまいます。
こうなると、かみつくべき時にかみつけないという危険も出てきます。そうならないように記者は訓練を受け、デスクから厳しく指導されますが、何事もパーフェクトにはいきません。
ところで捜査当局の場合、通常「報道発表」というと新聞・通信・放送などのメディアに情報提供することをいうことが多いと思うのですが、ほんとうに「公表」「発表」という趣旨に沿うなら、社会全体に公表するのであって、メディアであれノンメディアであれ、市民の問い合わせに対し広く開示するのが本来の筋で、アメリカやイギリスの警察のように、被害者名を含め基礎的公表情報はウェブに掲載することもあるべき態度ではないかと思います。つまり情報を言葉通り「パブリック(みんなの、公共公開の)」にするということです。(続く)
***
澤編集委員は社会部で司法取材を長く担当し、英オックスフォード大学ロイタージャーナリズム研究所への留学を経て、『英国式事件報道 なぜ実名にこだわるのか』(文藝春秋、現在は金風舎から「イギリスはなぜ実名報道にこだわるのか」としてペーパーバック版で発行)を上梓。その後、ニューヨーク支局に勤務し、アメリカや世界のジャーナリズムの現場を体験した。パナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」から流出した機密文書「パナマ文書」の国際的な調査報道に参加し、「グローバル・ジャーナリズム 国際スクープの舞台裏」(岩波新書)を出版。4月から専修大学文学部ジャーナリズム学科教授。
編集部より;この記事は、在英ジャーナリスト小林恭子氏のブログ「英国メディア・ウオッチ」2020年4月7日の記事を転載しました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、「英国メディア・ウオッチ」をご覧ください。













