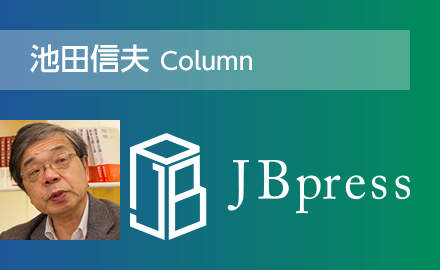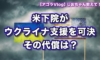マリー・アントワネット(Wikipedia)
「マリア・テレジア女系相続でハプスブルク家は終焉」を書いたら好評だったので、女帝マリア・テレジアと王妃マリー・アントワネットの生涯について紹介しておく。これは、『日本人のための英仏独三国志 ― 世界史の「複雑怪奇なり」が氷解!』でも扱っているが、ここでは『愛と欲望のフランス王列伝』 (集英社新書)もあわせ使って紹介しよう。両書で少し視点が違うし、後者はより詳しい。
保守的で軽薄?マリーの人となり
王妃マリー・アントワネットの両親は、ハプスブルク家のマリア・テレジアとロレーヌ(ロートリンゲン)家のフランツである。こうした実質上の入り婿結婚の場合、2つの姓を重ねることが多く、「ハプスブルク・ロートリンゲン家」と呼ばれることが多い。
フランツのほうではロレーヌ領(ロートリンゲン公国)を棄てるつもりなどなかったのだが、オーストリア継承戦争の結果、ロレーヌ領をフランスに渡し、代わりにメディチ家がこのころ断絶したのを受けてトスカーナ大公国をもらった。しかも、フランツはしばらくして神聖ローマ皇帝になれたからよかったものの、彼の母(ルイ14世の弟オルレアン公フィリップ1世の娘)らロレーヌ家一門の憤激は凄まじかった。
この両親のうち、マリア・テレジアは保守的だったが、沈着で威厳と政治力があり、フランツは軽薄だったが、良き家庭人で、進歩的で財務など実務的手腕があった。だが、娘マリー・アントワネットは、保守的で軽薄でいい加減だった。つまり、王妃としては両親の悪いところを集めていたのだ。
彼女が王妃でなければ革命はなかった
突飛なファッションで話題になったりしたのは、それまでの寵姫たちの役割を引き継いだようなものだし、プティ・トリアノンで個人的な友人だけと当時流行だった田園風生活を送ったことは、時代精神の先端を行くものではあったが、王妃としては職務放棄に近かった。
古今東西どこでも、芸能人まがいのセレブ生活を自由に楽しんだプリンセスたちは、ある種の人気を得るが、そのことが政体の安定に役立ったことは一度もなく、国家にとっても王室にとっても百害あって一利なしだった。マリー・アントワネット妃についても、彼女の浪費が財政を傾けたというのは誇張だが、フランス革命を引き起こした責任の大きな部分が彼女にあることを否定できない。
王妃マリー・アントワネットの兄である神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世は、やや軽薄で母との仲はよくなかったが、典型的な啓蒙君主として一般の人気を博した。モーツァルトを、そのライバルであるサリエリほどではないが、それなりに引き立てたことは、映画『アマデウス』でもお馴染みだ。パリを訪問し、妹に有益な忠告をしたが、あまり理解されなかったようだ。
ルイ16世の結婚相手に初め予定されていたのは、マリー・アントワネットの姉であるマリア・カロリーナだったが、そのまた姉が急死したので、両シチリア王妃となり、玉突きで妹に白羽の矢が立った。マリア・カロリーナは母に似た政治センスの持ち主で、彼女がフランス王妃なら革命は起きなかっただろう。
王ルイ16世は父が早世したので、祖父ルイ15世から王位を継いだ。先天的に男性器に欠陥があり、結婚後もしばらくは夫婦生活が望めなかったが、外科手術を受けて治癒し、子供を得ることができたという。趣味は狩猟や鍛冶仕事であった。心優しく、啓蒙思想の影響をある程度受けて、穏健な改革を指向したようだが、優柔不断で王妃を中心とした保守派に振りまわされた。
愛人の忠告を聞かず逃亡に失敗
フランスでは、統一国家への変身はルイ14世らによって完成していたが、その過程で妥協の産物として温存された貴族階級などの特権や官職売買があり、それが財政の収入不足や社会的な不公正感の温床になっていたことは、これまでにも書いてきた。
当然、貴族や教会の特権の縮小や廃止をどう進めるかが課題だったが、全国三部会をルイ13世の治世の1614年、から久しぶりに招集して討議することにした。

ルイ16世(Wikipedia)
国王にとってこの開催は、第三身分(ルビ=ティエール・ゼタ)(平民)を味方につけて貴族や聖職者を押さえ込むためのもののはずだった。だが、王ルイ16世にそこまで明確なビジョンはなかった。
だが、王妃や貴族たちは、王妃を通じてルイ王を動かし、軍隊をパリとヴェルサイユのまわりに配した。これに反発した民衆が、1789年7月14日にバスティーユ牢獄を攻撃、解放した。やがて、国王一家はヴェルサイユ宮殿からパリ市内のテュイルリー宮殿に移され、民主主義の原点になった「人権宣言」(ルビ=デクララシオン・デ・ドロワ・ド・ロム・エ・デュ・シトワヤン)が出された。
国王一家は国民を裏切り、国外への逃亡を企てた。もし、巧妙に変装すれば成功しただろうが、王妃は『ヴェルサイユのばら』でもお馴染みの愛人フェルゼン伯爵の忠告にもかかわらず大型馬車での移動にこだわり、国境に近いヴァレンヌ村で捕らえられた。
国王がパリを脱出するなら、王党派的な地方や部隊はいくらでもあったから、そこに合流すれば成功した可能性も強いし、裏切り者とはいわれなかっただろう。だが、祖国フランスを棄てようとした王に居場所はなかったのだ。
前王ルイ15世も16世も政治に無関心で、啓蒙思想(ルビ=エヴェイユ・スピリテュエル)という新しい流れの震源地でありながら王室がそれを利用するとか、打倒の標的にならないために工夫することがまったくなされていなかった。ポンパドゥール夫人は啓蒙思想の良き理解者であったが、寵姫という立場では、ルイ15世に対して、新しい思想を弾圧することを少し控えさせるのが限度だった。
「ベルサイユのばら」の真実
国王ルイ16世は、その優しい性格から国民から愛されうる存在ではあった。したがって、彼自身が啓蒙君主にならなくとも、良き宰相を持つか、大失策をせずに、柔軟に対処しさえすれば、どこまで成功したかはともかく、少なくとも、ギロチンの露と消えることはなかったであろう。
王妃マリー・アントワネットについては、頑迷な保守派と組んで改革を妨害して革命を不可避にし、実家の利益を頼って外国に通じるなどしたのだから、その夫を死に追いやった主要な責任がある。彼女への死刑判決は、『ベルサイユのばら』にヒントを与えたと見られる有名な伝記を書いたツヴァイクがいうように、法廷に外国との共謀についての証拠が十分に示されていなかったことにおいては不当だったかも知れない。
だが、今日の我々は彼女のフランスへの裏切りが事実であった数々の証拠を得ている。彼女へのいかなる同情も正当なものとはいえないし、フランス革命の血なまぐさい犠牲は、王家の人々のひどい愚劣さの結果なのである。
スウェーデン貴族のフェルゼン伯爵は、スウェーデン王グスタフ3世(その暗殺事件が、ヴェルディのオペラ『仮面舞踏会』のモデルになった王だ)の意向を受けてフランス宮廷で工作をしていた。王妃救出のために、誠心誠意の努力を行ったのは事実だが、その思想は極端な保守派で、政治的に見れば、王妃にとっていささか困った助言者だった。