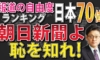(つづき)
以上の山本の分析を通して、私は、浅海記者の書いた「百人斬り競争」は、まずその構想が浅海氏にあり、その協力者を探すため無錫で両少尉に近づき、両少尉の里心(これが軍隊では実に強烈な誘因となったらしい参照:戦場の精神的里心)や手柄意識を、”新聞に載る――それによって無事を親元に知らせることができる”ことでくすぐり、架空の「武勇談」を両少尉に語らせ、それを聞き取る形で戦意高揚の記事を作成した。あわせて、戦場のまっただ中で取材活動をしている?自分をアピールしようとしたのではないかと思いました。
その様子は、先に紹介した「上訴申弁書」に次いで作成された「第二上訴申弁書」に付された、次の野田少尉の「百人斬り競争記事の真相」の内容とほぼ符合します。ただし、常州と紫金山周辺における会見が漏れているのは、前回説明した通り、「やらせ」で喋らされ、あるいは創作された会話が、裁判で「自白」と見なされたためです。また、この「真相」は「第二上訴申弁所」に付したものでしたので、この事実は隠さざるを得なかったのだろうと私は推測します。(参照:「戦場におけるホラ・デマ」)
野田少尉の「百人斬り」新聞記事の真相
〈「被告等は死刑判決により既に死を覚悟しあり。「人の死なんとするや其の言や善し」との古語にある如く、被告等の個人的面子は一切放擲して、新聞記事の真相を発表す。依って中国民及日本国民が嘲笑するとも、之を甘受し、虚報の武勇伝なりしことを世界に謝す。十年以前のことなれば、記憶確実ならざるも、無錫に於ける朝食後の冗談笑話の一節、左の如きものもありたり。
記者「貴殿等の剣の名は何ですか」
向井「関の孫六です」
野田「無名[銘]です」
記者「斬れますかね」、
向井「さあ未だ斬った経験はありませんが、日本には昔から百人斬とか千人斬とか云ふ武勇伝があります。真実に昔は百人も斬ったものかなあ。上海方面では鉄兜を斬ったとか云ふが」
記者「一体、無錫から南京までの間に白兵戦で何人位斬れるものでせうかね」
向井「常に第一線に立ち、戦死さへしなければね」
記者「どうです、無錫から南京まで何人斬れるものか競走[争。以下、同じ]してみたら。記事の特種を探してゐるんですが」
向井「そうですね、無錫附近の戦斗で、向井二〇人、野田一〇人とするか。無錫から常州までの間の戦斗では、向井四〇人、野田三〇人。
無錫から丹陽まで六〇対五〇、
無錫から句容まで九〇対八〇、
無錫から南京までの問の戦斗では、向井野田共に一〇〇人以上と云ふことにしたら。おい、野田どう考えるか。小説だが」
野田「そんなことは実行不可能だ。武人として虚名を売ることは乗気になれないね」
記者「百人斬競走の武勇伝が記事に出たら、花嫁さんが刹[殺]到しますぞ。ハハハ。写真をとりませう」
向井「ちょっと恥づかしいが、記事の種が無ければ気の毒です。二人の名前を借[貸]してあげませうか」
記者「記事は一切、記者に任せて下さい」
其の後、被告等は職責上絶対にかゝる百人斬競走の如きは為ざりき。又、其の後、新聞記者とは麒麟門東方までの間、会合する機会無かりき。
したがって常州、丹陽、句容の記事は、記者が無錫の対話を基礎として、虚構創作して発表せるものなり。尚、数字に端数をつけて(例、句容に於て向井八九、野田七八)事実らしく見せかけたるものなり。
野田は麒麟門東方に於て、記者の戦車に搭乗して来るに再会せり。
記者「やあ、よく会ひましたね」
野田「記者さんも御健在でお目出度う」
記者「今まで幾回も打電しましたが、百人斬競走は日本で大評判らしいですよ。二人とも百人以上突破したことに【行替え後、一行判読不可能】
野田「そうですか」
記者「まあ其の中、新聞記事を楽【し】みにして下さい。さよなら」瞬時にして記者は戦車に搭乗せるまま去れり。
尚、[当]時該記者は向井が丹陽に於て入院中にして不在なるを知らざりし為、無錫の対話を基礎として、紫金山に於いて向井野田両人が談笑せる記事、及向井一人が壮語したる記事を創作して発表せるものなり。
右述の如く、被告等の冗談笑話により事実無根の虚報の出でたるは、全く被告等の責任なるも、又記者が目撃せざるにもかかわらず、筆の走るがままに興味的に記事を創作せるは一半の責任あり。
貴国法庭[廷]を煩はし、世人を騒がしたる罪を此処に衷心よりお詫びす。〉
この「百人斬り競争記事の真相」は、死刑判決が12月20日にあり、12月22日に先に紹介した第一回「上訴申弁書」を書き、それでも再審が認められなかったので、最後の望みを託して、「自分の個人的面子は一切放擲」して新聞記事の真相を打ち明けたものです。しかし、残念ながらこれは提出には至らなかったようです。しかし、なんとしても自分らに着せられた住民・捕虜虐殺の汚名だけは晴らしたいと思いこれを後世に残したのです。
なお、この「真相」の末尾には、記者の責任に言及する部分が出てきます。これは、二少尉以外で事実を知る者は浅海記者だけで、彼だけが、この記事が創作であることを証言できる。しかし、氏はついに、この事実を証言せず、「記事は両少尉から聞いたままを書いた、ただし見ていない」としか言いませんでした。つまり、両少尉は浅海記者に裏切られたわけですが、そのことへの不満が、ここでようやく表出したのではないかと思います。俺たちが死ねば「死人に口なし」ということかと・・・。実際、この事実は、本多勝一氏が朝日新聞の「中国の旅」で「百人斬り競争」(s46)を報じ、これをベンダサンがフィクションと断定(s47)するまでは誰も知らなかったのです。この点で本多氏は、一定の役割を果たしたといえるのかも知れませんね。
その後、両少尉は遺書を書き始めました。両氏ともかなりの分量になりますが、その内容には全く驚かざるを得ません。自ら「南京大虐殺」につながる住民・俘虜の「百人斬り競争」の汚名を着せられ死刑判決を受けながら、公判中も堂々たる態度を崩さず、日本及び日本人に対する警鐘を行い、日中両国の友好親善を祈りつつ、なお自分の死を以て今後日中間に怨みを残すなと伝言するなど、戦後生まれの私たちには到底まねの出来ない立派な態度だと思いました。なお遺書は、向井少尉の立派な遺書も沢山ありますが、紙面の都合上、野田少尉(終戦時は大尉)の「日本国民に告ぐ」を紹介します。
参照:「百人斬り競争」資料
(つづく)