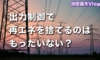有馬純 東京大学公共政策大学院教授
12月8日(土)~15日(土)、経団連21世紀政策研究所研究主幹として、ポーランドのカトヴィツエで開催されたCOP24に参加してきた。今回のCOP24の最大の課題はパリ協定の詳細ルールに合意することにあった。厳しい交渉を経て2015年に合意されたパリ協定はそれだけでは機能しない。パリ協定の根幹をなすNDCの範囲、透明性の手続き等について詳細ルールを固める必要がある。トランプ大統領がパリ協定離脱を表明する中で、温暖化防止の国際的モメンタムを損なわないため、詳細ルールの合意期限であるCOP24の失敗は許されず、何らかの合意は得られるであろうというのが事前の見通しであった。とはいえ、交渉は難航し、会期を丸1日以上延期し、15日夜に詳細ルールが全員総立ち拍手の中で採択されたことは喜ばしい。

本稿では詳細ルールをめぐって何が争点になったのか、どのように決着したのか、今後の課題は何かについて振り返って見たい。
1.今次交渉の主な争点と結果
今次交渉の大きな構図は、第1に共通のルールを重視する先進国と先進国・途上国間の二分法を可能な限り持ち込みたい途上国、特に中国等の有志途上国(LMDC)の対立であり、第2に先進国からの資金援助を確保したい途上国(特に低開発国、アフリカ等)と資金援助の野放図な拡大に慎重な先進国の対立であった。これを主な論点ごとに争点と決着を示す。
(1)国別目標(NDC)の対象範囲に緩和以外(適応、資金等)を含むのか
【争点】
パリ協定第4条では先進国、途上国問わず、緩和(温室効果ガス削減、抑制)のための国別目標(NDC)を設定することとなっている。しかしLMDC等の途上国はNDCの対象範囲に緩和に加え、適応や資金支援も含めることを主張してきた。NDCに目標を書き込むと定期的な報告、レビューの対象となり、段階的な引き上げを求められることになる。途上国はNDCに先進国からの資金援助を含めることにより、継続的に資金援助拡大のプレッシャーをかけることを狙ったのである。他方、先進国はパリ協定上、NDCの対象範囲は緩和のみであることは明らかであり、支援や適応を含めることはパリ協定のリオープンであるとして強く反対してきた。
【交渉結果】
決定文書ではNDCの内容はパリ協定4条に則り、緩和に特化されることとなり、パリ協定のリオープンにつながるLMDCの主張が斥けられた。
(2)NDCの緩和目標に関する補足情報をどの程度求めるのか
【争点】
先進国のNDCは現状からの総量削減目標を設定しているのに対し、途上国のNDCは原単位目標や自然体(BAU)からの相対的な削減目標が中心である。特に中国、インド等の新興国がどのような前提条件の下で目標を設定しているのか等を明確化することはその後の進捗状況報告、レビューにおいても非常に重要となる。このため、先進国はNDCに関し、詳細な補足情報の提出を主張してきた。他方、中国はそうした詳細情報の提出に強く抵抗しており、先進国と途上国の間で要求される補足情報のガイドラインを分けるべきであると主張していた。
【交渉結果】
決定文書では、NDCの通報に当たり、目標を明確化するための追加情報(例:目標設定の方法論、前提、対象分野、参照指標)、計算方法等の指針が定められた。これはすべての締約国に適用されるものであり、LMDCが主張していた先進国、途上国別々の指針という二分法は斥けられた。NDCに適応や途上国支援も含めるべしという主張とあわせ、パリ協定の時計の針を逆行させるような議論が採用されず、パリ協定の基本原則が維持されたことは大きな交渉成果といえよう。
(3)透明性ルールの差異化をどの程度認めるのか
【争点】
NDCの進捗状況に関する報告、レビューを内容とする透明性ルール(パリ協定13条)はボトムアップのパリ協定の実効性を担保する上で最も重要な部分である。パリ協定13条第2項では能力に制約のある途上国に対してある程度の柔軟性を認めることが規定されており、第3項では低開発国、島嶼国の置かれた特殊な状況に配慮することが規定されている。先進国はこれら諸国への配慮は当然としつつ、それ以外については可能な限り先進国、途上国で共通なルールを設けることを主張してきた。他方、中国等のLMDCは途上国全体について柔軟性を付与し、先進国と途上国で別途のルールを定めることを主張してきた。先進国、途上国(特に中国)の共通ルールは米国が特に重視している点であり、中国が米国に比して柔軟な扱いを受けることになれば、トランプ政権のパリ協定離脱方針を更に確固たるものにするのみならず、トランプ政権後のパリ協定復帰をも困難にすることとなる。米国を国際的な温暖化防止努力に関与させるためにも、新興国とのレベルプレーイングフィールドを確保するためにも先進国全体として最重要イシューであった。
【交渉結果】
合意文書では報告様式、内容(排出量データ、削減目標の進捗状況等)につき、全締約国に共通のガイドラインが定められた。温室効果ガス排出量の計測方法についてもこれまでは途上国がIPCC1996年ガイドライン、先進国が2006年ガイドラインを適用していたが、今後、先進国、途上国共にIPCC2006年ガイドラインを適用することとされた。争点となった柔軟性の適用については、途上国が自ら決定し、専門家レビューチームは当該途上国が柔軟性を自己適用することの是非、理由については立ち入らないこととされた。柔軟性の付与をレビュー対象とし、期限を設けるという先進国の主張は通らなかったが、一方で途上国が柔軟性の適用を自己決定するに当たり、個々の報告項目につき、柔軟性を必要とする理由、具体的な制約要因、状況改善の期限を説明することが義務付けられることとなった。中国のような大排出国が柔軟性を理由に情報開示を拒んだ場合、国際的に説明責任を厳しく問われることになる。また2020年までの枠組みであるカンクン合意においては先進国と途上国とで別々の報告様式・手続きが設けられていたが、合意文書では遅くとも2024年末には先進国、途上国共通の報告様式に移行することが定められた。途上国の柔軟性を認めつつもパリ協定の共通フレームワークの原則が堅持されたことは大きな成果である。中国等、新興排出国とのレベルプレーイングフィールド確保に向けて一歩前進したと言え、本件を最重要視してきた米国もCOP24後に発表された国務省プレス資料を見ると「大きな前進(significant step forward)」と評価している。
(4)市場メカニズム
【争点】
パリ協定では2種類の市場メカニズムが規定されている。1つは締約国がNDCを実施するに当たって環境十全性、透明性を確保し、ダブルカウントを排除しつつ、自主的な協力的アプローチに基づき緩和成果の国際的な移転を含む6条2項メカニズム、もう1つは京都議定書のCDMの後継として国連管理の元に設立される6条4項メカニズムである。JCM(Joint Credit Mechanism)を進めている日本にとって関心が高いのが6条2項メカニズムであることは言うまでもない。市場メカニズムに関する交渉は極めてテクニカルであるが、政治的イシューとなったのは6条2項メカニズムに対するShare of Proceeds適用と監督機関(Supervisory Body)の設立の是非である。途上国は6条2項に基づく自主的メカニズムについても国連直轄の6条4項メカニズムと同様、Share of Proceeds と呼ばれる運営経費徴収対象とし、国連主導の監督機関を設立することを主張してきた。これに対し、先進国はパリ協定上、Share of Proceeds の適用は6条4項メカニズムに限定されているのだから、6条2項メカニズムへの適用はパリ協定のリオープンであると反対し、監督機関の設置も締約国間の自主的な合意に基づいて行われる6条2項メカニズムの性格上、不要であると主張してきた。
【交渉結果】
結論から言えば、今次交渉では、市場メカニズムの詳細ルールはCOP25に先送りとなった。これは上記の政治的イシューの交渉がデッドロックになったというよりも、専らブラジルのCDM問題が原因である。多量のCDMプロジェクトを抱えるブラジルは今次交渉において京都議定書に基づくCDMをパリ協定下の6条4項メカニズムに移管すべきだと主張してきた。この点については経過措置として一定の期限付きで移行を認める方向で妥協が形成されつつあった。しかしここでダブルカウント禁止条項の問題が生じた。先進国も途上国も温室効果ガス目標を有するパリ協定の下では削減分を国際的に移転する場合、移転元の国の排出削減量からその分を差し引く必要がある。他方、CDMは途上国が削減目標を持たない京都議定書のメカニズムであるため、こうしたダブルカウント禁止条項は適用されてこなかった。ブラジルはそれを理由にパリ協定に移管されるCDMを適用除外とすべきと主張したのである。この点についての調整がつかず、6条の詳細ルール全体が来年に持ち越されることになったというわけだ。6条2項メカニズムに対する監督機関の設置については、専門家レビューという6条4項メカニズムに比して軽微なものとする方向が固まっていた。運営費課金問題についても6条4項メカニズムのみを対象とするというパリ協定の規定に則っていずれ収束すると見られていた。それだけにブラジルのCDM問題によって6条全体が先送りになってしまったのは残念である。
(5)資金問題
【争点】
先進国が緩和や透明性の共通ルールを重視している反面、低開発国を中心に途上国が最も重視しているのが資金問題であった。特に争点となったのが途上国支援情報の取り扱いと新資金支援目標設定である。パリ協定9条5項では将来の資金支援の見通し情報を提供することとなっているが、途上国は今回の交渉でこの手続きをルール化し、資金支援見通し情報をレビューの対象とすることを主張してきた。またパリ協定採択時、2020年までに1000憶ドルという資金支援目標に代わる新たな資金目標(1000億ドルを下限とする)を2025年までに決めることが決議されたが、途上国はCOP24で議論開始を決議し、2023年までに新目標を決定すべきであると主張してきた。これに対し、先進国はこうしたレビューを含む9条5項の手続きのルール化はパリ協定の詳細ルール交渉のマンデート外であるとしてこれに反対し、2025年までの新資金目標についてもCOP24で議論開始を決議するのは時期尚早であり、また新目標を議論するならば先進国のみならず、途上国支援を拡大している中国等もドナーとして関与すべきであると主張してきた。
【交渉結果】
9条5項の資金支援情報については、途上国が要求していたレビュープロセスは盛り込まれなかったが、事務局が統合報告書を作成し、それを踏まえ隔年でワークショップ、閣僚会議を開催し、議論することとなった。新資金目標については、2020年に検討を開始することが合意された。更に合意文書では適応を含む途上国の資金ニーズをアセスした報告書を事務局が作成することが決まり、先進国の資金支援に関する統合報告書と共にグローバルストックテークのインプット情報とされることとなった。全体としてみれば資金支援を重視する途上国に配慮した内容となった。冒頭の2つの対立軸を考えれば、共通ルールで先進国の主張がある程度通った以上、資金面で途上国の主張が通ることは当然の帰結といえよう。
2.COP24の評価と今後の課題
(1)詳細ルール交渉は成功
COP24は成功であったと言ってよい。何よりも今回の詳細ルール合意によって二分法に基づく京都議定書から全員参加型のパリ協定への移行が動き始めることには大きな意義がある。
今次交渉においては、「二分法を導入したいLMDC vs 共通フレームワークを主張する先進国」、「資金援助拡大を要求するアフリカ諸国、低開発国 vs 資金援助に慎重な先進国」という二重の対立構図が存在した。こうした中でNDC、透明性フレームワークにおいて共通のガイドラインが設定されたことは二分法に固執するLMDCの攻勢に屈せず、全員参加のパリ協定の精神を堅持したことを意味する。透明性フレームワークにおいて、柔軟性の付与が途上国の自己決定となったものの、説明責任を義務付けたことは成果である。中国等の大排出国が柔軟性を「悪用」しないよう、米国等との連携がカギとなる。
他方、2020年の長期資金目標の検討開始、ニーズアセスメント報告の作成等、アフリカ諸国、低開発国等の求める資金援助拡大では途上国に一定の譲歩をすることとなった。特にニーズアセスメント報告書はグローバルストックテークの材料とされ、今後、途上国の支援ニーズと先進国の支援オファーの間のギャップがクローズアップされることになるだろう。先進国にとって頭の痛い問題ではあるが、先述のとおり、資金支援と共通フレームワーク(二分法の排除)がパッケージである以上、合意形成のためには避けられない道であったともいえる。
巨視的に見れば、パリ協定のリオープン(NDCの範囲、二分法等)につながるLMDCの主張を斥ける一方、資金支援面で貧しい途上国に配慮したものとなっており、全体としてバランスのとれた合意結果であると評価できる。
今回、米国は最も重視していた透明性の共通ルールで一定の成果を得た。しかしこのことをもってトランプ政権がパリ協定離脱方針を翻意するかは不明である。先述の国務省ステートメントでも「米国民にとって有利なディールがない限り、パリ協定離脱に関する政権のポジションは変わらない」と明記されている。むしろ「トランプ後」をにらんで米国が復帰できる基盤ができたことを評価すべきであろう。
(2)1.5℃目標により現実とのギャップが更に拡大
今回の合意によって2020年以降、パリ協定体制が動き出すことになるが、懸念されるのは「COPの世界」と現実世界とのギャップの広がりである。COP24でNGOをはじめとする環境関係者が専らプレーアップしたのは詳細ルール交渉よりも10月に発表されたIPCC1.5℃特別報告書であった。タラノア対話では多くの閣僚が1.5℃報告書に言及し、ノルウェー、島嶼国連合のように1.5℃報告書を踏まえたNDCの引き上げを唱道する「High Ambition Coalition」も発足した。第1週の補助機関会合最終日では1.5℃特別報告書の扱いにつき、歓迎(welcome)を主張する島嶼国、EUと留意(note)を主張する米国、ロシア、サウジ、クウェートの対立が顕在化し、物別れとなった。COP24の決定文書では「COPの要請に応じて特別報告書を作成したIPCCに対して感謝を表明する」との中立的表現が採択された。しかし来年の補助機関会合では1.5℃特別報告書について検討(consider)することになっており、その結果をどう表現するかが改めて争点となろう。
2050年近傍にネットゼロエミッションという1.5℃特別報告書で描かれた削減パスと現実との間には途方もないギャップがあり、世界第1位、第2位の排出国である中国、米国や今後排出が急増するインドやASEANがそれに見合ったNDCを引き上げるとは考えにくい。事実、COP24でNDC引き上げると表明したのはマーシャル諸島くらいであり、逆にドイツは2020年目標を断念し、EUはドイツ、東欧諸国の反対により2030年目標の引き上げを見送っている。また1.5℃特別報告書では2030年に世界全体で135~5500ドルの炭素税が必要とされているが、パリではたかだか10数ドルの炭素税引き上げがイエローベストの大規模騒乱を招いている。先進国のフランスですらこうなのだから途上国においては炭素価格引き上げへの受容性は更に低いのは当然だ。しかしCOPに集う環境関係者は2℃目標にかえて1.5℃目標をデファクトスタンダードにしようとしている。2℃目標ですら現実との乖離が明白であったのだから、1.5℃路線に基づく野心レベル引き上げキャンペーンは早晩、破綻することになろう。フィージビリティを考えないスローガン先行の議論がプロセス全体に対する信頼性を損なうことが懸念される。
(3)掛け声の削減目標よりも技術による解決を
我が国にとっての課題も多い。1.5℃特別報告書が大きくクローズアップされる中で、まず2020年のNDC提出の際に2030年26%減目標を引き上げろという議論が内外で発生するだろう。しかし原発の再稼働が順調に進まず、26%目標の達成見通しが厳しくなった場合、更に目標を引き上げることは合理的ではない。日本の限界削減費用も産業部門のエネルギーコストも主要国中最も高い。国際的な掛け声に乗って非現実的な目標を設定することは日本の産業競争力、経済に多大な悪影響をもたらすことになる。1.5℃特別報告書は2023年のグローバルストックテークでも大きく取り上げられ、2025年の目標改定時にも影響を及ぼすことになるだろう。筆者は1.5℃~2℃目標達成については懐疑的であるが、究極的に脱炭素化を目指すのであれば、空虚な掛け声やフィージビリティスタディを伴わない気合の数字ではなく、経済と両立した形で脱炭素化を可能にする技術の開発と普及の面できちんとした目標、戦略を立てるのが日本の取るべき道であると考える。日本は京都議定書策定交渉に当たり、プレッジ&レビューというボトムアップの枠組みを先行して提案した。結果的に国際的枠組はトップダウンの京都議定書という壮大な「回り道」を経ることになってしまったが、最終的にはボトムアップのプレッジ&レビューをコアとするパリ協定に到達した。脱炭素化の道筋についても数値目標ではなく技術重視というアプローチを世界に打ち出していくべきである。