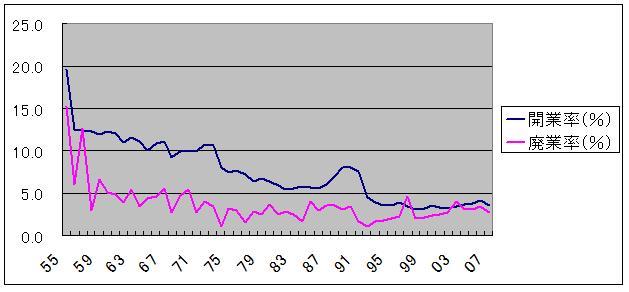数学嫌いは法学部を選択する傾向があると言われます。文系では法学と経済学が実学の主流ですが、経済学にはある程度の数学が必要ですから、法学部には数学嫌いが集積している可能性があるというわけです。むろん法律家は数学に弱いなどと一般化するつもりはありませんが、裁判員制度を見る限り、これは数学嫌いの人たちが作ったのではないかという印象を強く受けます。
この制度は、以下に説明するように数量や確率といった数学的な思考を欠くだけでなく、基本的な論理にも疑問があります。
そして現実から遊離した、原理主義的な理念ばかりが目立ちます。ここではそういった視点を中心に、裁判員制度を見ていこうと思います。
『民主主義は最悪の政治形態と言うことが出来る。これまでに試みられてきた民主主義以外のあらゆる政治形態を除けば』
このチャーチルの有名な言葉は民主主義を盲信する者に対する警告と受けとることができます。 そして、民主主義は最終目的ではないということにも留意する必要があります。最終目的は最適な社会を実現することですから、民主主義はそのための手段に過ぎません。この自明のことをここであえて言うのは、裁判員制度はまるで民主主義そのものを最終目的としているかの印象を受けるからです。
裁判員制度は国民主権を司法に実現するという理念のもとに作られました。司法制度改革審議会の意見書には、裁判員制度の意義は国民が国民主権に基づく統治構造に参加するという理念の実現であって、被告人のためではないという意味のことが書かれています。 実際、被告人の利益に対する配慮は見られません。無作為で選ばれる6人の裁判員の判断能力のバラつき、時間短縮のために犠牲にされる精密な審理など、裁判の公平性に関わる問題点が明らかになりつつあります。
国民主権という民主主義の理念が実現したとしても、裁判の公平性などの機能が損なわれてはまさに本末転倒です。裁判員制度はまさに机上の空論から生まれたもので、以下にその様々な問題点を述べます。
民主主義への盲信と数学的思考の欠如
裁判員制度は矢口洪一元最高裁長官や司法制度改革審議会の中坊公平氏らの国民参加制度論者が熱心に導入を図り、国民に詳しい説明もされず、また国会でも実質的な論議をされず04年夏、成立したとされています(文芸春秋07/11月号)。
2001年6月の司法制度改革審議会の意見書第IV章のはじめには次のように謳われています。
『国民主権に基づく統治構造の一翼を担う司法の分野においても、国民が、自律性と責任感を持ちつつ、広くその運用全般について、多様な形で参加することが期待される』
つまり、裁判員制度の意義は国民主権を司法の場に実現するということのようです。この制度の推進者には一般国民の判断というものに対する盲目的な信頼があるのではないでしょうか。言うまでもなく、民主主義は国民の判断への信頼を基盤としています。しかしそれは集合(マス)としての平均化された国民の判断です。
よく言われることですが、民主主義のワイマール体制がヒトラーを生んだように、集合としての判断であっても間違いはしばしば起ります。決して妄信してよいものではありません。
裁判員制度は僅か6名の平均化されない人たちが直接被告を裁くものです。この制度において6名は国民という民主主義の主体、一様な抽象概念として扱われます。個々の裁判では、6名の素人が国民主権を担うわけです。
能力も考え方もバラバラの国民のなかから無作為に選んだ6名が果たして偏りのない公平な判定者と言えるのでしょうか。もし1名とか2名なら大きな偏りが生じるのは明白です。100名ならかなり平均化できます。世論調査のサンプル数は1000以上が普通ですが、これは集団の偏りを避けるための必要数であり、サンプル数が少なければ誤差は大きくなります。もしサンプル数を6とした調査をすれば、調査によるバラつきが大きく、とても使いものにならないでしょう。6名という数は平均化には少なすぎるもので、判決のバラつきは当然起こります。6名という数の根拠は示されませんが、統計の基本的な問題に対する配慮がないことだけはわかります。6名で許容される誤差の範囲内に収まるのか、その根拠を示すべきす。
一方、裁判員は選挙権名簿に載っているすべての義務教育終了者が対象で、300万人ともいわれる知的障害者、精神障害者も、認知症の人も裁判員になることが求められます。知的障害者、精神障害者が裁判員候補者に選ばれた場合の対応が既に始まっており、推進する弁護士は「健常者が気づかないことに気づき、裁判員全体として真実に近づくこともあるはずだ」、と述べ、最高裁も「障害によって職務に支障がでないよう、できる限り配慮する」という積極的な方針を示しています。
裁判員の選定にはごく簡単な面接があるだけで、見識や判断力を客観的にチェックする有効な仕組みは事実上ありません。選定は面接者の主観が頼り、という頼りないことになっています。基準も示さない、主観だけによる選別は国民にとってたいへん不透明なものです。ふさわしい判定者を選び、より適正な裁判を目指すという姿勢は残念ながらまったく感じられません。
もう一点、これは数学的思考というより単に「数」の理解の問題です。最高裁事務総局刑事局の平木正洋総括参事官は裁判員制度の意義について『裁判に対する国民の理解が深まり、裁判が身近に感じられるようになって、司法への信頼が高まることが期待されています』と述べています。
注意したいのは裁判員を経験する国民は年間6000人に1人、つまり0.017%にすぎないということです。ごくごく僅かの人間が裁判員を経験するだけで「裁判に対する国民の理解が深まり、裁判が身近に感じられる」ようになるでしょうか。しかも裁判員には守秘義務があるので経験の波及効果は期待できません。
国民の理解という問題においては、6000人に1人はあまりにも実効性に乏しく、ゼロに等しい数値です。全員が経験するのには6000年が必要であり、その頃には人類が存在するかどうかもわかりません。裁判員制度の主要な意義、「裁判に対する国民の理解」とは国民に対する欺瞞と言えるでしょう。
それが、関係者の「数」に関するひどい無知のためか、あるいは欺瞞と知りながらも他にめぼしい意義がないので無理やり出してきたのかわかりませんが、どちらにしても信頼に値するものではないと思います。
殺人事件に無罪から懲役14年まで―バラバラの判決が想定通りとは?
次は論理に関する疑問です。数学以前の問題だと言ってもいいでしょう。
一昨年、裁判員制度による模擬裁判が8箇所の地裁で実施されました。同一の想定事件に対する8つの判決は、無罪判決から懲役14年まで、大きな差がつきました。無罪判決は3件、懲役刑は6年から14年まであり、懲役6年の2件以外はすべてバラバラの結果です。(朝日新聞07/12/02)
もし無罪判決が正しければ懲役14年は誤判ということにならないのでしょうか。一方が正しいなら他方は誤りという関係です。この大差が出たことに対する最高裁の見解は「当然、想定していた」であり、最高裁は判決のバラつきを予想して、この裁判員制度を推進してきたようです。
被告人にとって、いや裁判にとってもっとも大切なことは公平性だと思います。つまり同じような犯罪には同じような刑が科せられることです。判決にこのような大差がでても「当然」とする最高裁の感覚は凡人の常識では理解できません。
裁判を受ける身からすれば、そのときの裁判員次第で、判決が無罪から懲役14年までブレては、くじや占いで刑を決めるのと大差ありません。判決が一定範囲に収束してこそ裁判に信頼性が生まれるのではないでしょうか。
この最高裁の特殊な感覚の謎を解くヒントは但木敬一前検事総長の次の発言にあります。
『(裁判官と裁判員の協働)作業の結果、得られた判決というのは、私は決して軽くもないし重くもない、それが至当な判決であると・・・』(論座07/10月号)
つまり国民が参加する裁判員制度による判決を無条件に「至当」とする根拠不明の認識は次の例にも見られるように、この制度の推進者に共通するらしく、これを前提として裁判員制度が作られてきたと考えられます。本当に「至当」なら従来の制度より判決が収束してしかるべきです。 バラバラな判決がそれぞれ「至当」である、つまり異なる「至当」がいくつもある状態とはどう理解すればよいのでしょうか、たいへん不思議な論理です。
次の四宮啓早大法科大学院教授の発言も理解不能です。
『模擬裁判で量刑がばらつき、公平な裁判ではないという声があるが、裁判官と裁判員が当事者の意見を聴いて十分に議論した結果は、適正な刑罰だ。それがプロの裁判官の相場とずれているなら、相場が見直されるべきで国民が議論した末の結論こそ「真実」だという考え方を日本社会は身につけていくだろう』-四宮啓早大法科大学院教授(07/12/30朝日新聞)
量刑がばらついたとき、「(裁判員制度による判決が)プロの裁判官の相場とずれているなら、相場が見直されるべき」との四宮氏の主張は理解困難です。ばらついた判決に相場を合わせろとはちょっと論理的に不可能であると思います。裁判員制度を推進されるお二人に共通する「高級」な論理を私は理解することができません。
また、裁判員制度による判決が「至当」「真実」というならば、上級審の存在理由がなくなるのではないでしょうか。一審の方が優れているのなら上級審の判決が優先されてはおかしいことになります。逆に言うと、上級審を従来のままにしているという事実は、本音では裁判員制度にあまり信頼を置いていないということを示唆しています。
また、裁判員制度による判決が「至当」「真実」というならば、上級審の存在理由がなくなるのではないでしょうか。一審の方が優れているのなら上級審の判決が優先されてはおかしいことになります。逆に言うと、上級審を従来のままにしているという事実は、本音では裁判員制度にあまり信頼を置いていないということを示唆しています。それほど優れたものなら高裁、最高裁も裁判員制度を取り入れるべきです。
理解不能の論理、「至当」や「真実」という断定的な言葉を根拠も示さず、簡単に使う態度は原理主義や信仰とそっくりで、とても社会科学の記述とは思えません。
また、この大差を「当然、想定していた」という最高裁の発言は、とにかく国民主権に基づいて国民が参加した裁判の結果は「真実」であり「至当」であるから、差など気にしないということでしょうか。誤判など当然あるもので、仕方がないという無責任な態度とも解釈できます。
米国における陪審員制の信頼度
国民が参加する判決は「至当」であるとする根拠不明の認識が裁判員制度の基礎になっているようですが、米国の事情にも触れたいと思います。
米国は日本のように参審制ではなく、12名による陪審員制が採られているところが異なります。そして被告は陪審員制の裁判と職業裁判官による裁判を選択する権利が与えられています。しかし陪審員制は素人判断による「偶然司法」になっているという批判が根強く、連邦地裁における刑事事件の陪審利用率は5.2%、民事では1.7%(97年10月1日から98年9月30日までの統計)という低率になっています(第30回司法制度改革審議会配布資料より)。
陪審員制は裁判員制度とは同じではありませんが、「国民の判断」が支持されているのは僅か刑事事件5.2%と民事事件1.7%に過ぎないことに注目すべきです。刑事事件で陪審員裁判を選ぶのは20人のうちの1人にすぎません。これが「国民の判断」に対する現実の信頼度と言えるでしょう。また英国の陪審員制は縮小傾向にあるそうです。
国民の判断に絶対の信頼を置くお二人の発言とは逆に米国の被告人は国民の判断をあまり信用していないようです。米国の国民は信用できないが、日本国民は信用できるという根拠でもお持ちなのでしょうか。
裁判員制度は裁判官が加わる参審制なので、知識や経験で圧倒的な差のある裁判官が評議に支配的な影響力を持つ可能性があります。「国民の判断」は裁判官によって修正を受け、偏りは抑制されると期待できます。しかしそうなれば裁判員の参加の意味が減少するというジレンマを抱えることになります。形だけの国民参加になりかねません。
スピード裁判のいい加減さ
広島の女児殺害事件の一審では裁判員制度を意識した短期間の審理が行われましたが、08年12月9日、二審の広島高裁は審理が尽くされていないとして差し戻しました。この事実は短期間の審理に疑問を投げかけるものとして重要な意味を持ちます。
裁判員は時間に制約のある場合が多く、早く評決を出そうとする力が働く可能性があります。最高裁、法務省、日弁連共同の広告には「多くの場合、裁判員の仕事は3日以内で終わる」と書かれています。詳しく見ると「約7割の事件が3日以内で終わると見込まれています。事件によっては,もう少し時間のかかるものもあります(約2割の事件が5日以内,約1割の事件が5日超)」と書かれています。
事前の予想より長くなり、予定日数を超えたりすると、「早く終わらせよう」という強い圧力がかかるでしょう。 また予定通り進めるためには全員が理解するまで待っていられないということも起こり得ます。議論は収束していないが、これ以上仕事を休めないので多数決で判決を出しましょう、では被告はたまりません(時には被告人の命にかかわる判決を素人らの多数決で決めるのは抵抗があります)。裁判員制度は実質的に裁判に時限を切るものとなります。
陪審員制を採用しているカナダや米国は刑事事件の評決は全員一致が原則ですが、これはより多くの時間が必要です。参審制を採用している独や仏では有罪には2/3の多数を必要としています。これらは誤判をできる限り避けるためだと思われます。それに対してわが国は1/2の単純多数決ですから、終了予定時刻がくれば、「はい、時間がきました。死刑に賛成の方、手を挙げてください」で終わることができます。 たいへん効率的ですが、被告人の利益を軽視した制度だと思わざるを得ません。
時間の短縮に加え、裁判員に理解してもらうための説明に余計な時間を取られますから、本来の評議にかけるべき時間がさらに削られるのは避けられないと思われます。 中には理解してもらうのに何倍もの時間を要する人もいるでしょう。裁判員制度の利点として裁判の迅速化が言われていますが、時間の制約を設けて迅速化を図るのは本末転倒です。
別の迅速化の方法として、公判前整理手続きの導入と「核心司法」呼ばれる核心部以外を省いた形の裁判をやる方向が出されています。公判前整理手続きとは審理期間の短縮を目的に、初公判前に検察側と弁護側が争点と証拠を整理することで、05年11月から実際に導入され06年では40%程度の短縮効果を上げていますが、これは裁判員制度とは関係なく実施できるものです。
また、時間短縮と裁判員の負担軽減にもっとも効果があるといわれている「核心司法」の導入が考えられています。これは従来の「精密司法」と呼ばれる、事件の全容を背景から精密に解き明かしていく方法に代えて、核心部のみを審理することで審理時間を大幅に短縮するものとされ ますが、それで審理の精度を保てるのでしょうか。
というのは核心部だけの審理でよいのなら裁判員制度と関係なく実施できるものであり、裁判の長期化が以前から問題になっているのに、なぜ採用しなかったのかという疑問が生じます。核心部だけで周辺部をそぎ落として同じ精密な結果が得られるのなら、今まで膨大な時間を浪費してきたことになります。裁判制度を導入するため ご都合主義による簡易化であり、ここでも裁判の公平性が犠牲になりはしないかという疑問が残ります。
裁判の沙汰もカネ次第・・・弁護士の演技力が判決を左右する
1994年のO・J・シンプソン事件をご記憶でしょうか。元プロフットボール選手で俳優のシンプソンが元妻とその友人男性を殺害したとして逮捕された事件です。ドリームチームと呼ばれる有力弁護士団によってシンプソンは無罪を勝ち取りました。彼は弁護費用に5億円をかけたとそうです。ところが被害者遺族が起こした民事訴訟では敗れるという、妙な結果になりました(民事訴訟では遺族側の弁護士は最強のチームであったのに対し、シンプソンは一流の弁護士を雇う金がなかったとされています)。その後シンプソンは強盗や武器の不法所持などにより、08年に懲役刑15年の判決を受けました。
シンプソン事件は弁護士の力量が裁判を大きく左右することを示唆しています。有罪無罪を決めるのは12名の陪審員なので弁護士の腕は彼らを如何に説得できるかにあります。職業裁判官は論理的な判断が主になると期待できますが、素人は感情的な判断を優先させる可能性があります。
否認事件で検察側と弁護側が対立するとき、どちらかがウソをついているとき、そのウソを見破るのは簡単ではないありません。被告人が涙ながらに語る若い美人なら有利になるでしょうし、悪人面の無愛想なオヤジならきっと不利になるでしょう。
弁護士にも検察官にも演技力が要求されることになります。すでに陪審員の感情に訴えるアメリカ流の弁護術の講習会をやっているそうです。素人の裁判員を弁護側の主張に誘導するには論理だけでなく、感情に訴えることが重要というわけです。一方、裁判所側も被告にネクタイや靴らしく見えるものの着用を認めるなど、裁判員が感情に左右されないような対策が講じられています。
これらはいずれも裁判員の感情が裁判を左右する危険を認めていることを前提としています。裁判員による裁判では、被告の話しぶりや顔立ち、演技力が大きい要素となるでしょう。有能な弁護士を雇うことができる、資金力のある被告人と国選弁護人だけの被告人に大きい差ができる可能性があります。
裁判員制度を決める前に、なぜ実験をしない
自然科学の分野における因果関係の解明は社会科学の分野に比べると簡単です。それでも実験は欠かせない手段で、化学装置や機械の分野でも「やってみなけりゃわからない」ということがいっぱいあります。
社会政策の分野では定量できない要素が多く、予想は一層難しいことです。それにもかかわらず、実験という発想がほとんどありません。安易な予想に基づいて実行し、結果が失敗であっても、因果関係がはっきりしないために誰も責任を負うことがないためでしょうか。近年では実験せず 、安易な期待に基づいて実施された「ゆとり教育」の失敗が好例です。
残念なことに裁判員制度では決定をしてから模擬裁判という実験をやっています。これは逆さまです。大規模な模擬実験をして裁判の公平性をはじめ様々な問題点を解決できる見通しが立ってから制度の導入を図るのがまともなやり方です。
素人の裁判員が出す判決はブレが大きくなりやすいことくらいは事前に予想できますから、ブレが許容範囲になるかを実験で確かめることは可能の筈です。 例えば同一の想定事件で、悪人面の被告と善人面の被告の場合、また演技の巧みな被告とそうでない被告の場合を比較したりすると有益なデータが得られるでしょう。このようなデータは実際の裁判を多く経験しても得られません。
さらに、いま各地の地裁で模擬裁判をやっていますが、裁判員の選定方法が実際と違うという問題があります。現在、裁判員は大企業などに依頼して社員から選定するという方法をとっているところが多いようです。選挙人名簿から無作為抽選で選定した裁判員と大企業 などの社員では裁判に対する適性が違うことが考えられます。本来の無作為抽選による裁判員で模擬裁判を実施すれば、ブレがさらに大きくなる可能性があります。
実験が可能なものは、実験によって問題点をできる限り解決してから実施に移す、というのが本来のやり方です。実験をせずに机上だけで進める方法は失敗の可能性が高くなるのは間違いなく、結果に対して責任を持つ気持があるとは思えません(誰も責任を問われることがない仕組みですが)。
終わりに
以上述べてきたように、裁判員制度は民主主義や国民主権を実現するという空虚な理念ばかりが重視され、裁判で最も大切な公平性や精度を軽視していると考えざるを得ません。
裁判員制度では、不適切な判決が出た場合も裁判官の責任を問うことは困難です。裁判官は、「今度の裁判員は奇人・変人が多くて、あんなひどい判決が出ちゃいました 」と弁解することが可能になります。のちのち責任を問われることのない「行きずりの6名」が大きな決定権を持つわけで、判決の責任所在は不明確になります。裁判官は気楽になりますが 、最適な判決を出そうというインセンティブは弱くなります。
一方、過去のどの調査でも「裁判員として参加したくない」は7~8割を占めています。朝日新聞が08年12月に実施した面接調査では59%が裁判員制度は根づかないと考え、裁判員制度そのものに対しても、反対が52%で賛成の34%を大きく上回っています。
民主主義や国民主権の実現をふりかざして登場した裁判員制度が国民の意に反して、つまり非民主的に強行されるのはなんとも皮肉なことです。法案は国会を通り、形式上は民主的な手続きを経ていますが、国民の多くが知らないまま決まりました。国民の意向は調査の方により反映されていると考えられます。
裁判員制度という重要な制度がほとんど議論もされずに実施されるに至った背景にはマスコミと野党の無能があります。マスコミが食品の消費期限や産地偽装の問題に払った努力の十分の一でも成立前の裁判員制度に払っていれば違った結果になっていたかもしれません。また国会では全党一致で可決されましたが、少なくとも議員達は国民の意向を反映していたとは言えません。
国民に負担を強いるだけでなく、被告人の利益に対する配慮が感じられない裁判員制度ですが、被告人は裁判の主人公であり、国民でもあります。そして無罪かもしれないのです。