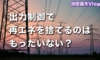最近気づいたのですが、「百人斬り競争」は「非戦闘員殺害」だったと思い込んでいる人が意外と多いようですね。また、こういう人たちは、論争によってそれが事実でないことが分かっても、その話(=自白)をしたのは両少尉であり、記者はそれを記事にしただけ。従って、それが「非戦闘員殺害」の証拠となり処刑されても、それは、自業自得、と考えるようです。
おそらく、これは「百人斬り競争裁判」の結果がもたらした印象なのではないでしょうか。私自身のこの裁判についての感想は、裁判所が相変わらず「雲の下論」(*本稿3で説明します)的な事実認定をしていることの驚き。もう一つは、この裁判では、この事件の事実関係について、それまでの論争で積み上げられた論証が、ほとんど生かされなかったということです。
というのは、それまでの「百人斬り競争」論争における議論の焦点は、記者が両少尉から「百人斬り競争」の話を聞いたことは明らかだが、では、記者はその話を事実として聞いたか、それともフィクションとして聞いたか、ということでした。そして、この点については、イザヤ・ベンダサン、鈴木明、山本七平らの研究によって、記者が両少尉の戦場心理を利用して武勇伝の”ヤラセ”をさせ、それを取材したように見せかけて戦意高揚記事を書いた、ということでほぼ決着していました。
この論争で本多勝一記者は、論争の開始当初、氏が中国で聞いてきた「殺人ゲーム」が事実であることの証拠として、この新聞記事を掲げていました。従って、論争の結果、この新聞記事が上述したような”ヤラセ”記事であったことが判明した段階で、その新聞記事を「元ネタ」にした「殺人ゲーム」は、いわゆる「虚報が生み出した悲劇」とすべきでした。
ところが、本多記者及びこれを支援する朝日新聞は、その後の論評でも、また「百人斬り競争」裁判でも、いわゆる志々目証言の他、中帰連メンバーであった鵜野晋太郎の捕虜殺害体験談、それに新たに発見された望月五三郎の私家本『私の支那事変』の記述などを証拠として、「百人斬り競争」は「捕虜(据えもの)百人斬り競争」であったと主張しました。
そもそも、小学生の頃に野田少尉の話を聞いたという伝聞証言や、両少尉とは無関係な残虐兵士の証言、それに「据えもの百人斬り競争」説登場後に書かれた私家本の記述などが、人権尊重第一、「疑わしきは罰せず」を基本原則とすべき今日の裁判において、証拠になるのでしょうか。
この裁判における最終判決は次のようなものです。
「南京攻略戦闘時の戦闘の実態や両少尉の軍隊における任務、1本の日本刀の剛性ないし近代戦争における戦闘武器としての有用性等に照らしても、本件日日記事にある『百人斬り競争』の実態及びその殺傷数について、同記事の内容を信じることはできないのであって、同記事の『百人斬り』の戦闘戦果ははなはだ疑わしいものと考えるのが合理的である。
しかしながら、その競争の内実が本件日日記事の内容とは異なるものであったとしても、次の諸点に照らせば、両少尉が、南京攻略戦において軍務に服する過程で、当時としては、『百人斬り競争』として新聞報道されることに違和感を持たない競争をした事実自体を否定することはできず、本件日日記事の『百人斬り競争』を新聞記者の創作記事であり、全くの虚偽であると認めることはできないというべきである。」
前段は、新聞記事に記された戦闘行為としての「百人斬り競争」について、「その内容を真実ことができず」「はなはだ疑わしいと考えるのが合理的」というのですから、それでよろしいと思います。しかし、後段の、両少尉が「『百人斬り競争』として新聞報道されることに違和感を持たない競争をした事実自体は否定できない」というのは、一体どういうことでしょうか。
これは、この「百人斬り競争」の新聞記事中で、両少尉が「百人斬り競争」を肯定する会話をしている、ということでしょう。つまり、「この記事の全てが記者の創作」とは言えない、といっているのです。実は、ここに、原告側の”新聞記事は全て記者の創作”とする「事実の摘示」の誤りがありました。事実は、先に述べた通り、これは「ヤラセ」記事だったのですから。
つまり、記者は、両少尉に武勇伝としての「百人斬り競争」の「ヤラセ」をさせ、その会話を巧みに記事に織り込んで戦意高揚記事を書いたのです。ところが、原告側が、この記事の全てを記者の創作とし、両少尉は常州以外では記者と会っていないとしたため、次のような問題が起こりました。
第一に、両少尉のいう無錫郊外での記者との三者談合(そこで”ヤラセ”談合が成立した)の存在が不明確になったこと。次に、第四報の舞台となった紫金山に、両少尉が行っていないことを証明しなければならなくなったことです。(もっとも、これは記事中の紫金山の戦闘地域には行かなかったという意味かも知れませんが・・・)
そして、こうした両少尉のアリバイ主張が、それぞれの属した部隊の作戦地域の検証でくずれた結果、記事中の両少尉の会話の「ヤラセ」部分と、記者による創作部分の腑分けができなくなったのです。そのため、全体的な印象として、両少尉が「百人斬り競争」を「自白したのは事実」→自業自得との印象を持たれることになったのです。
また、それと同時に、そうした両少尉の会話以外の部分の記述についても、同様に、それが両少尉の話をもとにしたものか、それとも、記者が記事に整合性をもたせるために創作したものか、その判別ができなくなってしまったのです。そのため、記者の”両少尉から聞いたままを記事にした”という言葉への反証が困難になりました。
先に紹介した裁判所の最終判断は、こうした議論の流れを受けたものと思われますが、では、原告側はなぜ、このような、それまでの研究成果を無視した「事実の摘示」を行ったのでしょうか。あるいは、記事中に両少尉の「自白」部分を認めることは、裁判では不利との判断があったのでしょうか。
また、こうした主張は、両少尉が南京裁判の過程でもしていましたから、その証言の信用性を維持しようとしたのかもしれません。といっても、両少尉の場合は、その主張の根幹が、新聞記事は記者が構想したものであり、従って、「ヤラセ」でしゃべらされた自分たちの会話も、記者の「創作」とする意識が働いたものと思われます。
そこで、次に、この新聞記事の内、どの部分が両少尉が「ヤラセ」でしゃべらされたものか、あるいは記者の創作によるものかを、それまでの鈴木明や山本七平が行った論証に見てみたいと思います。