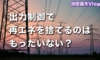仏週刊紙「シャルリー・エブド」本社テロ事件とドイツの反イスラム運動「西洋のイスラム教化に反対する愛国主義欧州人」(Patriotischen Europaer gegen die Islamisierung des Abendlandes、通称ぺギダ運動)をフォローしていると、自由に対する私たちの異なった対応が見えてくる。一つは「言論の自由」を含む人間の自由への飽くなき希求だ。もう一つは、自由の一部を国家に委ねることで幸せを求める国民の実態が浮かび上がってくる。以下、少し、説明したい。
人は自由を求める存在だ。取り巻く環境、社会が自由を制限するならば、その障害を突破して自由を獲得しようと腐心する。中世時代からカトリック教会の伝統や慣習に縛られていたフランス国民が起こした革命はその代表的な例だろう。
神の支配から脱して、人間本来の自由の謳歌を求めたルネッサンス運動は当時のフランスに影響を与えていた啓蒙思想と結びついて1789年、フランス革命を引き起こした。
その革命で獲得した成果の一つが「言論の自由」を含む「自由」だった。だから、イスラム過激派テロリストの風刺週刊紙本社襲撃事件直後、300万人以上のフランス国民が反テロ国民行進に参加したわけだ。行進に参加した国民は同週刊紙の愛読者だけではなかった。むしろ、言論の「自由」という革命の成果が攻撃されたことに対する憤りが強かったのではないか。
一方、隣国ドイツでは反イスラム教運動が全土に拡大してきた。それに対し、メルケル首相は機会がある度に警告を発し、「イスラム教はドイツの一部だ」と表明したヴォルフ前大統領の発言を繰り返している。
同首相には、仏テロ事件を受けてドイツ国内で反イスラム運動が勢いをつけ、混乱が生じるのではないか、といった懸念が強いはずだ。ひょっとしたら、それだけではないかもしれない。ユダヤ民族を大虐殺した負の歴史を抱えるドイツでは、特定の民族・宗派の国民を批判することに強い心理的ブレーキが働くからかもしれない。
フランスでは国民は「Je suis Charlie」(私はシャルリー)という抗議プラカードを掲げたが、ぺギダ運動に参加する市民は‘Wir sind das Volk’(われわれは国民だ)と叫びながら行進する。「われわれは国民だ」は政治の転換を求める明確なメッセージだ。換言すれば、イスラム系移住者の殺到を止め、“ドイツ国民ファースト”の政治を求めているのだ。それは同時に、「信教の自由」、「移民の自由」への制限を容認するという暗黙の了解も含まれているわけだ。
人は自由を求める存在だが、同時に、強い指導者のもとで自由の制限を喜んで甘受する。自主的に判断して選択しなければならない「自由」を恐れる人々がいる。ドイツの社会心理学者エーリッヒ・フロムはそれを「自由からの逃避」と名付けている。そして、その数は決して少数派ではないのだ。
ぺギダ運動がドレスデン市という旧東独都市から始まったのも偶然ではない。反イスラム運動に共鳴する市民は共産政権下で自身の自由が制限されることを体験してきた。東西ドイツ再統一後、自由を得たが、生活環境は改善されていないと感じる市民はイスラム系移住者をターゲットにしてデモ行進する。彼らはパリの市民のように無制限な自由を願っていない。
フランス国民は自由の制限に対して沈黙しない。その結果、仏人気作家ミシェル・ウエルベック(Michel Houellebecq)氏の最新小説『服従』のストーリーが現実味を帯びてくることになる。
小説の内容は、2022年の大統領選でイスラム系政党から出馬した大統領候補者が対立候補の極右政党「国民戦線」マリーヌ・ル・ペン氏を破って当選するというストーリーだ。フランス革命で出発し、政教分離を表明してきた同国で、将来、イスラム系政党出身の大統領が選出されるという話だ。
保守系政党が反イスラム教、外国人排斥を訴えるル・ペン党首と連携すればイスラム系大統領候補を破ることは可能だったが、強い指導力と自由の制限を良しとしない国民はそのチャンスを放棄した。著者は、カトリック国フランスで同国初のイスラム系大統領が選出されるという皮肉な結果をシニカルに描いている。
自由の問題はフランスやドイツだけではない。「自由」が全てを許すならば、私たちは「自由の乱用」という副産物に直面する。それだけではない。「私の自由」が「他の人の自由」と衝突することを回避できないから、紛争、対立が絶えない。一方、強い指導者のもと、安定した生活を求めるならば自由の制限を甘受せざるを得ない。「自由」への対応では、われわれはこのようにあまり魅力的ではない二者択一を迫られているわけだ
少々蛇足だが、フランスで反テロ運動が高まっていく中、国民の中には「私はシャルリー」ではなく、「私たちはシャルリー」と書いた紙を掲げる人々が出てきた。これは単数から複数への変化というより、「個人の自由」を追求してきた国民がその自由を守るために社会、国家の関与を求めだしてきた、と解釈できるかもしれない。
編集部より:このブログは「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2015年1月27日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。