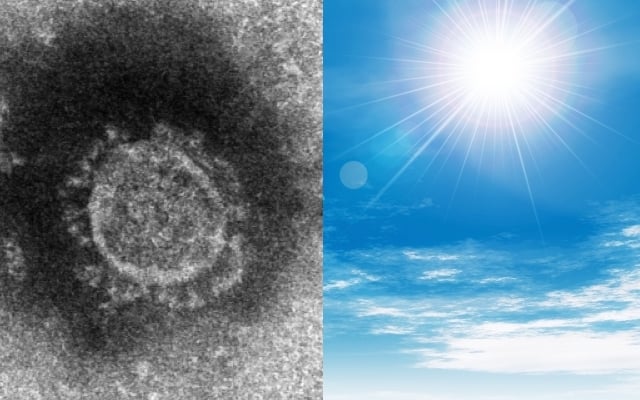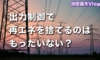独材がなく発表ものばかり
安倍首相、小池都知事らや厚労省が、「三密」を避けてくださいと、連呼しています。「密閉、密閉、密接」の三要素を禁止されて、深刻な影響を受けているのがメディア、それも新聞です。

記者会見も距離を開けて実施(官邸サイトより:編集部)
収入源を断たれた人の購読停止による部数減、広告主の出広削減、販売店の折り込みチラシの激減という三重苦で新聞経営は大ピンチです。さらに困るのは、記者取材の基本はニュース・ソースに対する密着なのに、それができなくなっていることです。「三密」禁止で取材源へ接近できず、官製記事ばかり紙面が覆われる。戦前、戦時以来です。
新聞を広げて見ましょう。4月24日の読売新聞朝刊を例にとってみます。1面トップは「感染者集団が全国で125か所/都道府県が公表した情報を集計」とあります。準トップは「軽症者はホテル療養/加藤厚労相が記者団に明らかにした」とあります。
3段の記事で「国内景気が急速に悪化/政府公表の月例経済報告」があります。1面記事4本が全て、「公表ないしインタビューもの」で埋められ、スクープはもちろん、これはという独材もありません。
2面を見ましょうか。「クラスター(集団感染)の恐れのある施設名を公表/政府が都道府県に指針を通知」、「船の科学館を中等症向け臨時施設に/政府と都」、「入社時期は弾力的に対応/経団連会長が記者団に語る」、「武漢研究所の立ち入り要求/米国務長官が会見」などなど。大小8本の記事の全てが「記者会見で」「記者会見で」です。記者はいらない。ロボットで処理できる情報ばかりです。
社会面も同じです。「人気女優の岡江久美子さん(63)がコロナウイルスによる肺炎で死去」は所属事務所の発表です。ほか著名な2人の死亡記事も遺族による公表です。「国内死者300人超」「クルーズ船の感染者48人に/長崎」など、合わせて7本の記事は記者不要のものばかりです。
国際報道面はどうでしょうか。ソウル、台北、ワシントン、ニューヨーク、ハノイ、ロンドン、北京、モスクワ発など9本の記事が載っています。全てに現地支局の記者名(昔は特派員と称した)が入っています。これも記者は要らない。現地の新聞、テレビ、通信社情報のリライトでしょう。
朝日新聞、日経新聞も同工異曲で、読売に限った現象ではありません。このような現象はコロナ騒動が始まった2,3月から始まり、この後、いつまで続くのか。記事はネット、テレビに先行された情報の二番煎じばかりで、定時の印刷と配達という時間差のハンディを負う新聞は圧倒的に不利です。

写真AC
メディア研究の方がどなたか、ニュース面における「発表、会見もの」の本数、比率を調査してみたら、様変わりになった新聞紙面の検証になります。新型コロナがもたらした異変です。
独自情報の基本は対面取材です。取材源に対する密接な人間関係の構築、密着したフォローアップが必要で、「三密」とは正反対の関係にあります。接近した立ち話で、そっと耳うちされることも許されません。テレワーク、自宅勤務、テレビ会議、電話取材では、重要な情報源に接近できません。
記者の取材をかわせて、ほっとしている政治家、官僚、経済人は多いことでしょう。その結果、秘匿されている情報の発掘もできず、戦前や戦時の「大本営発表」みたいになったら社会損失です。
テレビは、自宅から記者が映像を流したり、スタジオにアンカーが座って複数の専門家を画面に登場させたりすれば、最低限の仕事はできます。ネットはもっと簡単で、専門家、識者が自分の知見をアップするだけでいい。新聞はそうもいかず、官製記事が満載の紙面では、息の根が止まります。
では、どうしたらいいのか。日経(4/25)の2面に、ノーベル医学賞を受賞した仏学者の「中国の研究所によるコロナ人為説」の検証記事を載せていました。フェイク情報かなと疑っていましたら、論文が本当にサイトに掲載されているようです。記事の要点は「研究者の多くが否定」とのことです。
この種の検証は新聞が得意とするところです。日経はよく考えた記事を書きました。もう一つは「米財政赤字、戦時並みに」の記事扱いで、これは逆に不十分です。主要国が競うようにぶち上げている財政出動、超金融緩和の問題点を誰も指摘したがらないのはよくない。
1面に元財務長官のサマーズ氏のインタビュー記事が載りました。「現在の資本主義は、マネーが十分な投資機会を生み出すことができず、余剰マネーとなって市場に流れ込み、金融資産を押し上げる。この結果、富裕層に富が集中し、格差拡大が深刻になった」。重要な指摘です。
米国では、投入される資金は4兆、5兆㌦と膨らみ、日本でも100兆円を超す事業規模の経済対策が決まりました。倒産しかねない企業の資金繰りには役だっても、経済の長期的停滞を打開することは難しい。怒涛のようにつぎ込まれたマネーは結局、また株高、資産高の復活を演出する。
「アフター・コロナ」のバブルが生成され、それがまた、何かのきっかけで崩壊する。そこでまた巨大な規模の金融財政出動が要請される。そんなことがいつまでも続くはずはない。最後は、第二次世界大戦のように、無残にも敗北する国の惨状が再現され、積もり積もった国債も「ご破算に願いまして」となるのかもしれません。
表面的な動きばかりを追わず、もっと本質的な問題点を指摘することは新聞だからこそ、できると思うのです。コロナ対策を名乗れば「なんでもあり、なんでも通る」です。それにどう切り込むか、新聞の役割を再発見してほしい。
編集部より:このブログは「新聞記者OBが書くニュース物語 中村仁のブログ」2020年4月25日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、中村氏のブログをご覧ください。