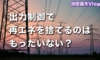官邸HP、Wikipedia
検察庁法改正の話題が非常に話題に上っており、検察官人事を内閣が掌握することは三権分立に反するという議論もなされているが、それはあまり正確とは言えない。
モンテスキューは、「三権分立」を主張して権力分立による自由主義を尊重したわけだが、実際に三権分立を厳格に実施しているのはアメリカのような大統領制の国であって、イギリス型の議院内閣制においては、「権力集中」モデルなのである。ましてや検察官がいくら準司法的な役割を担っているとはいえ、あくまで行政権の一部である以上、内閣が人事権を行使することに問題があるとはいえない。
むしろ、今回のケースは、明治以来から続く官と民の戦いの歴史上に位置づけられるものと言えるだろう。
戦後長らく続いた官僚支配からの脱却を目指して、橋本行革、小泉改革を経て、内閣府・内閣官房の権限は強化され続けきた。この省庁再編と小選挙区制という制度改革はある意味国統治構造を大きく変えるものであり、形式的に文言を変えてはいないものの、実質的な意味での憲法改正に等しいものと言えるだろう。
安倍一強を支えるメカニズム ーなぜ強い内閣は生まれたのかー(Yahooニュース個人拙稿)
戦後の政官財のトライアングルによる調整型談合政治は、バブル崩壊や冷戦終結という事態において機能不全となった。住専問題や薬害エイズ、ノーパンしゃぶしゃぶなどが問題となったのもこの頃である。
そうした状況に対応するための「政治主導」というものが求められ、民主的な手続によって選ばれた国会議員、内閣総理大臣とその閣僚が、霞ヶ関の官僚に対して支配を及ぼして行政権を行使するという、あるべき民主的統治構造を可能にするべく、平成以降の一連の制度改革がなされてきた。そして、新聞やテレビなどの主要メディアは、一貫してそれを要望し続けてきたはずだ。
今回、検察OBたちは口をそろえて改正法案に反対しているが、それもそのはず官僚の論理としては、素人の政治家に自分たちの人事に首を突っ込まれたくないのだから当たり前の話である。
問題は、自称リベラル派や主要メディアが、この対立構造において、自分たちの代表である民の側ではなく、官の側に立っていることだ。「素人の政治家による官僚への民主的統制は問題である」といったような、民主制への疑問を投げかけた上であれば理屈も通ろうが、そういった気配は見られない。自分たちが選んだ政治家よりも、官僚の方が信頼できるというのであれば、政治家は必要なくなる。
今回の改正法によって、検事総長、次長検事、検事長についての役職定年の延長(改正検察庁法22条2項、5項、6項)というのは、内閣の意向に沿った人物をその職に留めることができるという意味で蛇足の条文であるとは思うが、そもそもこれらの職については内閣が任免権を持っていることからすると、さほど大きな欠陥とも思えない。
戦後の制度改革は、一貫して内閣総理大臣、そしてそれを支える内閣官房に権限を集中させることにより、より機動的で統合的な国家戦略、政策立案を可能にするための改革がなされてきた。当然のことだが、完璧な制度というものはありえないので弊害もあるだろうが、これに対しては、最終的に主権者の意思を選挙で示すかたちでガバナンスを効かせていく以外にはないのである。

田上 嘉一 (たがみ・よしかず)弁護士/陸上自衛隊三等陸佐(予備自衛官)
早稲田大学法学部卒、ロンドン大学クィーン・メアリー校修士課程修了。防衛法学会、戦略法研究会所属。