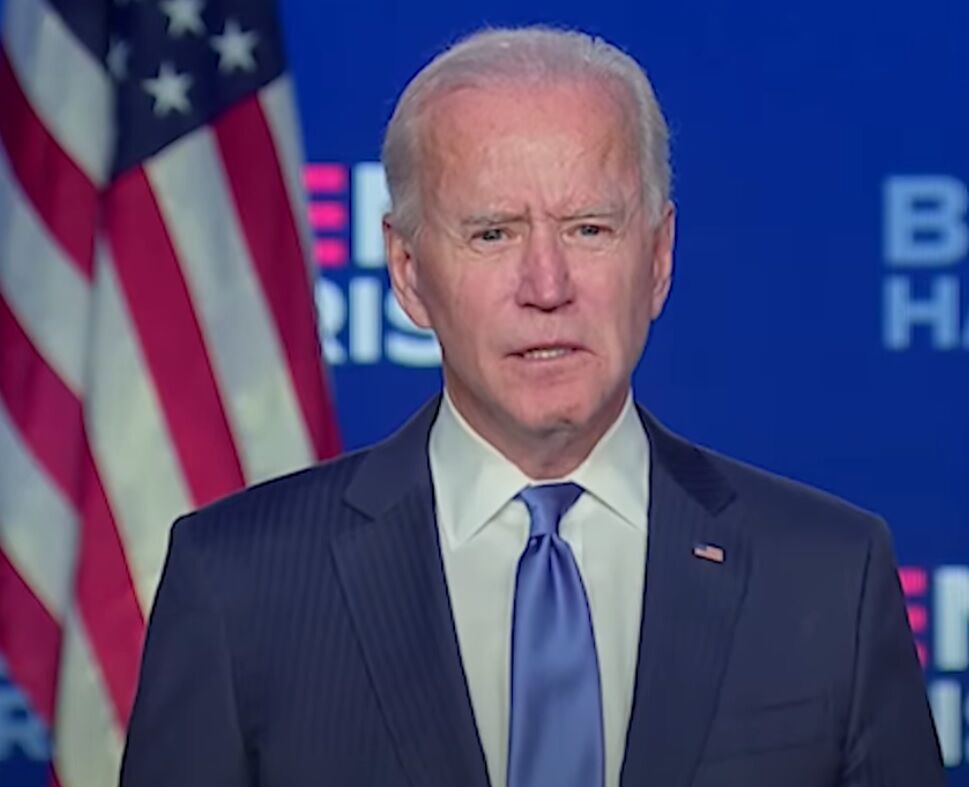キリスト教は世界に300以上のグループが存在し、各グループは独自の教えをもっている。伝統的キリスト教神学では、イエスは「神の子」であり、人類を救済するために地上に降臨し、人間の罪を背負って十字架上で亡くなったが、3日後、復活して福音を伝え始めた、といわれている。

▲「磔刑図」アンドレア。マンテーニャ画1459年(ウィキぺディアから)
それに対し、7世紀に登場したムハンマドが創設したイスラム教では、「神の子が死ぬはずがない」として、「十字架上で亡くなったのはイエスではなく、彼のドッペルゲンガーだった」と考えている。それにしても「神、ないしは神の子は死ぬはずがない」と考えるイスラム教はある意味で非常に論理的だ。神が死んだら、神を信じる唯一信教は成り立たなくなるからだ。神、ないしは「神の子」を殺しておきながら、「3日後に復活した」と主張するキリスト教神学とは異なっている。
新約聖書を見ると、イエスはゴルゴダの丘で十字架で亡くなる直前、「わが神,、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか」(「マタイによる福音書」第27章45から56節)と問いかけ、最後は「神のみ心のままに」と言って亡くなった。イスラム教では「その瞬間、神はイエスの体から抜け出た」と考え、死んだのはイエスの肢体だけだったと考えることで、「神の死」を免れる論理を展開させてきた。神の子、イエスが十字架で亡くなった後、3日後に復活したという伝統的な神学より説得力がある。「死んだ人間がどうして復活できるか」といったキリスト教神学者を悩ませてきたテーマに対峙せずに済んだわけだ
イスラム教徒の聖典コーランにはイエスも聖母マリアも登場する。イスラム教ではイエスは「キリスト」や「メシア」でもなく、あくまで「預言者の一人」だ。ただし、ムハンマドが誕生する前では最高の預言者として信望されてきた。
ここで注目したい点は、イスラム教ではイエスの十字架の死については信じていないとすれば、ゴルゴダの丘で何が起きたのだろうか。それを説明するシナリオとして、①死んだのはイエスではなく、彼のドッペルゲンガーだった、②集団的幻覚症状(Hallucination)が生じ、イエスは困惑する人々をおいてに十字架から逃げ去った、という2通りの説だ。
ドッペルゲンガー説をいうと、北朝鮮の金正恩新総書記を想起する読者もおられるだろう。今月14日の第8回党大会後の夜の軍事パレードで演壇に立つ金正恩氏の写真をみると、「彼は金正恩氏ではない」といった声がソーシャルメディアでは既に飛び出している。金正恩氏には身辺の安全のために数人のドッペルゲンガーがいるといわれてきた。
そのドッペルゲンガーがイエスの十字架の死でも大きな役割を果たしたという考えはユニークだが、全く新しいわけではない。「イエスは十字架上では亡くなっておらず、インドやアジア地域に逃避した」という話は口述で昔から伝わっている。イエスは日本まで来たという話さえある。イエスのドッペルゲンガー説を100%排斥することはできない。
それでは「イエスのドッペルゲンガーは誰だったか」、「誰がイエスに代わって死んだのか」だ。イスラム教義者は、①ゴルゴダの丘までイエスに代わって重い十字架を運んだシモン、②イエスを銀貨30シェケルで裏切った使徒イスカリオテ・ユダ、③イエスの13番目の弟子―の3つが考えられるという。ちなみに、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画「最後の晩餐」でも分かるように、イエスの弟子は12人と言われているが、イスラム教では13人にいた。その13番目の弟子がイエスの代わりに死んだというのだ。
イエスを殺したくないために、イスラム教義学者は必死にイエスの代わりに死んだ人間は誰だったかを考えてきたわけだ。それにしても、先述したように、「イエスは人類救済のために死んだ」、「死んだイエスは3日後に復活してその教えを広めていった」といった論理で満足しているキリスト教神学者の怠慢さとは対照的だ。どちらが正しいかという問題ではなく、イエスへの思い込みはイスラム教側のほうが強いのを感じるのだ。
以上は、独仏共同出資の放送局「アルテ」(ARTE)の「イスラム教のイエス像」というタイトルの番組から興味深い点を抜粋して紹介した。ドッペルゲンガー説や集団興奮状況説はイスラム教世界では高名な教義学者の意見であることを付け加えておく。
最後に、もう1点、報告する。聖母マリアがイエスを処女懐胎した点について、1人のイスラム教理学者は「この世界で男女間の性関係なく生まれた人間は2人しかいない。一人はイエスであり、もう一人はアダムだ。イエスは第2のアダムの立場だったから、聖書の書き手はイエスの誕生を説明するためにはどうしても聖母マリアの処女懐胎という書割が必要となった」と述べていた。非常に理路整然とした解釈だ。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2021年1月18日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。