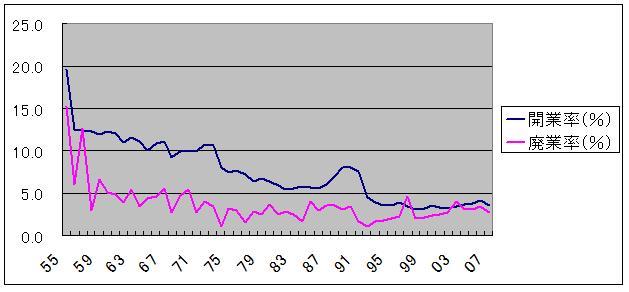足裏マッサージと同じで、結局人の為すことは洋の東西あまり変わらない...であろう、ということで、ご紹介します。
「Yes, Minster」と続編「Yes, Prime Minister」は1980年から1987年まで、イギリスのBBCで放送された、コメディー番組です。
メインの登場人物は3人。
一人目は政治家、下院議員のジム・ハッカー。番組のスタート時点で、ハッカーの所属する政党が総選挙に勝利し、彼は閣僚入りを果たします。
二人目は彼が担当することになった架空のMinistry of Administrative Affairs(総務省?)の事務次官(イギリスではPermanent Secretaryという)、サー・ハンフリー・アップルビー。ハッカー新大臣は、それなりの理想を抱き、マニフェストに準じた改革を推進すべくホワイト・ホール(イギリスの霞ヶ関)に乗り込んでくるのですが、現状維持を第一とする典型的官僚タイプであるサー・ハンフリーは、新任の大臣と表面上は友好関係を保ちつつも、水面下ではことあるごとに対立します。
この二人に挟まれて四苦八苦するのが三人目、ハッカーの筆頭秘書官(Principal Private Secretary)であるバーナード・ウリー。立場上、国家公務員であるバーナードは、ハッカーに同情しつつも、常に組織上の上司であるサー・ハンフリーに「政治家は、いつ選挙で消えていくか分からない...しかし官僚組織は永遠だ。」と脅されます。
シリーズ全編を通じて珠玉のユーモア・シーンが満載なのですが、例えば、ハッカー大臣が提唱した政策に関して、紳士クラブのラウンジでくつろぐサー・ハンフリーと、Cabinet Secretary(日本における官房副長官に相当する国内国家公務員組織のトップ )サー・アーノルド・ロビンソンのこの会話。なんだかどこかの国の補正予算の話みたいじゃないですか。
また、引退を決意したサー・アーノルドが、後継者指名の白羽の矢をちらつかせながら、サー・ハンフリーから引退後の天下り先の確保の約束を引き出すこのシーン。(4:42のマークからです。)
このシリーズは1979年にスタートする予定だったのが、79年が総選挙の年だったことに配慮し、1980年のスタートとなったのだとか。
ですからここに描かれている背景は70年代、つまり76年にIMFの救済を受けた英国のドンゾコの時代の政官界に取材したものです。「議会制民主主義の母」も英国病の病膏肓に入るころには、こんなテイタラクだったのです。
いわずもがなではありますが、この1979年の総選挙に勝利し、ダウニング・ストリート(首相官邸)とホワイト・ホールに乗り込んできたのが「鉄の女」マーガレット・サッチャー保守党政権。サッチャーさん自身、このシリーズの大ファンであったとか。
そして、皆様ご存知のごとく、サッチャー政権下で、イギリスの政官界も大改革時代にはいります。
「サッチャー革命」自体は色々研究されていますので、門外漢の私があえて付け加えることはあまりないのですが、政官界改革という切り口でみた場合、次の三つがサッチャー時代の大きな動きだったといえるのではないかと思います。
一つには従前の諮問会議の回答に答える形で1979年より始まったSelect Committeeの制度。国会において、各省庁に対応する委員会(Select Committee)が設置され、それぞれ担当省庁の活動を監視し、国会議員が必要に応じて担当公務員を喚問できる制度が、政官のパワーバランスに大きな影響を与えました。
二つにはポリティカル・アドバイザーの存在の重要性が増したこと。省庁内部から叩き上げられてきた純粋培養の官僚とは異なり、政権担当政党から各大臣とともに各省庁に送り込まれてきた「部外者」が政策発案とプレゼンテーション(いわゆる「スピン」というやつですな)に大きな発言力を持つことによって、官僚の地位が相対的に下がりました。
三つ目は、これは上記の二つに比べはっきりと目に見えていなかったことですが、 サッチャー政権の長期化により、かつては一枚岩とみえていた英国官僚組織にヒビがはいったことでしょう。とくにサッチャー首相の秘書官であった、外務省出身のチャールズ・パウエルさんなどは、それこそコメディー・シリーズのバーナード・ウリー秘書官が注意されたように、ポリティカル・マスターに近寄り過ぎ、彼を身内(と思っていた)の官僚たちから「裏切り者」呼ばわりされるまでサッチャー女史に仕えました。
ちなみにパウエルさんはサッチャーさん失脚後、後継者のメージャー首相に1年間仕えた後、ビジネス界に転身。ジャーディン・マセソン社、LVMHモエ・ヘネシー・ルイヴィトン社、マンダリン・オリエンタル・インターナショナル社などの取締役を兼任し、2000年よりは一代貴族として現在は貴族院議員となっています。
ようするに、天下りがどうこう、人材バンクがああでもないこうでもない...などと二代目/三代目政治家たちにいわれる以前に、できる人材は世間がほっとかないということです。日本の官僚諸士も組織力に頼るのではなく、自らの能力に大いに自信をもっていただきたい。
(ちなみついでに、チャールズさんの弟のジョナサン・パウエルはトニー・ブレアの首席補佐官でした。まさに80/90年代イギリス版華麗なる一族。)
結局TVコメディーのレベルまで落ちてしまった官僚システムに喝を入れたのは「鉄の女」のConviction Politics(信念の政治)だったわけです。疲弊したシステムを再生するには、プラグマティズムを標榜するコンセンサス政治家ではだめなのです。
もっとも、いまのところコメディー番組でジョークのネタになっているわけではなく、木村拓哉さんがドラマで政治家役をやっているようなのであれば、日本の政治家さんや役人さんたちもまだしばらくは安穏としていられるのかも知れませんね。
以下は「メイキング・オブ...」の映像。
また、サッチャー政権下における保守党陣笠議員の「革命後」のやりきれない議員人生に関しては、サッチャー内閣で雇用省や国防省の閣外相を勤めた故アラン・クラークの日記と、それをベースにしたドラマ・シリーズが秀逸です。
また私が留学中にその知己を得たフィリップ・オッペンハイム元議員の著作、「マギーからマルガリータへ」もなかなか笑わせてくれます。ケネス・クラーク蔵相の下で閣外相を勤めていたオッペンハイム議員は、1997年の総選挙に落選した後、キューバ料理のレストランを始めたという変わりダネ。
「歴史は繰り返さない。しかし韻を踏む。」とも言うようですから、約20年前の英国病の症状とその処方箋が、21世紀の日本病の治療のヒントになるかもしれません。
以下、タネ明かしのビデオ。