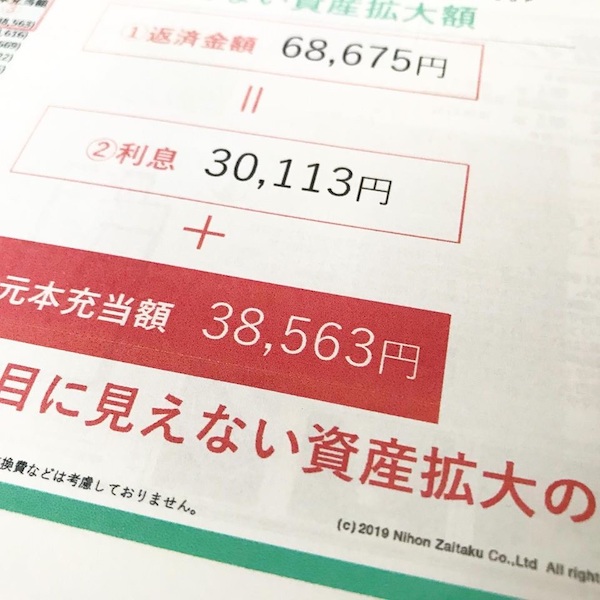廣瀬禎彦さんブログより:編集部
廣瀬禎彦さんが亡くなりました。享年76。
IBMの事業部長としてPCを作り、アスキーの専務としてゲームを作り、セガの副社長としてドリームキャストを作り、@NetHome(現J:COM)の社長としてネット事業を作り、コロムビアレコードの立て直しを進めた、とんでもない人でした。
1997年9月、政府・行革会議は郵政省を解体する中間報告を発表。郵政省の担当であるぼくは反抗する運動を展開し、12月、結果として総務省に滑り込むことで決着。結果オーライだがぼくは辞表を書かねばなぁ。ぼくは事務次官に上り詰めるつもりだったんだがなぁ。どう生きようかなぁ。
悶々としていたその頃、アスキー西和彦社長と廣瀬専務から会おうと連絡。ホテルオークラのロビーでした。初対面の廣瀬さんがいきなり「民間に出なさいよ。アスキーのゲーム部門の責任者やりなさいよ。」と言う。当時その部門はダビスタやらmoonやらツクールやら、数百億円の売上がある大ビジネスで、すぐにはピンと来なかったものの、民間に拾ってくれる人がいるのか、と実に安心しました。
ロビーの向こうにオノ・ヨーコさんがいて、おお、生で初めて見る、すると廣瀬さんが「オノ・ヨーコさんはぼくの家庭教師だったんだ」という。何か複雑なジョークだと思い、民間じゃこういうのも笑わないといけないのかと表情に困りました。後に聞いたところ、廣瀬さんが永田町小学校(!)に通っていたころ本当に英語を教えてもらっていたそうで。廣瀬さん、先生より先に逝ってはいけません。
98年に入り、ぼくが役所を出る決心をしたころ、西さん廣瀬さんは別のオファーを持ってきました。「セガ/CSKの大川功会長と話せ。」言われるがまま西麻布で大川さんとサシ飲み。(たぶん)めっちゃ高いワインをガブ飲みしました。
大川さん「私財35億円をMITに寄付してメディアと子どもの研究所を作るさかい、担当する客員教授にならへんか。」それはぼくの仕事です。リアリティあります。行きます。と答えました。「何やら大川さんに気に入られたみたいです」と廣瀬さんに報告すると、「大川さんの前でそんなにガブガブ飲むヤツはいないからだ。」大笑いされました。
民間に出ることになったぼくは、ビジネスのこと、アメリカのこと、さまざまなことを教わります。大学で学ばなかったぼくは役所ですさまじく勉強をさせられましたが、民間に出てアメリカに出て、改めてすさまじい勉強を強いられました。廣瀬さんが師匠でした。
ぼくの渡米と同時にセガの副社長に就いた廣瀬さんはドリームキャストに邁進します。セガの顧問にしてもらってそのチームにぼくも加わり、開発・販売の現場を見ました。そして廣瀬さんの差配に舌を巻きました。チップ、OS、通信(ドリキャスは世界初の通信機能付きゲーム機)、ゲームソフト、映像、音楽、デザイン、生産ライン、販路、その他全てに精通していないと統括できない。限られたスケジュールで仕上げるには、毎日瞬時に判断していかないといけない。くらいつくのがやっとでした。
でもいつも軽やかなんですよね。羽田の副社長室でダベっていたら、水口哲也さんが入ってきて、構想中のゲームを長身の身振り手振りでクネクネ説明する。「銃をこう打ったら星人がチューチューってこうなる。」廣瀬さんがキャラ設定だとか反応スピードだとか開発コストだとかニコニコと矢継ぎ早に聞く。水口さんがタタっと答える。素人のぼくは、へぇゲームってそんな感じでできるのかー、と聞き入っていました。名作、Space Channel 5がスタートする瞬間でした。
当時、セガアメリカはシリコンバレーの静かな湖畔にありました。廣瀬さんはアメリカのゲーム制作のリーダーたちに英語で罵声を浴びせていました。生産管理の観点から現場を締めていました。一方で、ドリキャス発売が見えてきて、ソフトに比重が移るのを見越して、会社の移転を画策しました。
クリエイターはシリコンバレーじゃダメだ。田舎じゃダメだ。メシとクラブがなきゃ。文化がなきゃ。都会じゃなきゃ。そう言って、セガアメリカをサンフランシスコの倉庫街に移しました。技術者は不満だったかもしれませんが、クリエイターは大喜び。
テクノロジーとコンテンツ、デジタルとアナログ、その双方をガッツリ押さえている、当時では稀有な存在でした。
MITの契約を終え、ぼくがスタンフォード日本センターの所長に就いたころ、廣瀬さんはセガを出て、@NetHomeというプロバイダーの社長をしていました。その仕事にぼくはほぼタッチしていないのですが、一つ大きな仕事をなさいました。ほしよりこさん著「きょうの猫村さん」です。
西麻布の怪しいマンションで音楽制作者連盟の飲み会を毎月開く、という最高の仕事を副業として請け負っていたぼくは、一緒に仕事をしていたほしさんを廣瀬さんに会わせたのです。絵が抜群で言葉も豊かなほしさん、マンガ描くといいのにねーという話になり、「@NetHomeで一日一コマ連載すれば?」と廣瀬さん。そこから、猫村さんが始まります。17年続いています。廣瀬さんの軽口と、それを実行するマネジメントがなければ、あの名作は生まれていませんし、大家ほしよりこもデビューしていません。
子どもとメディアの研究所を作っていたMITから戻り、日本で子どもの創造力・表現力のNPO CANVASを立ち上げる際には、記念すべき第一回ワークショップを岡山市で廣瀬さんが開いてくれました。葉っぱやテープなど好きな素材を使って自分だけの写真を撮ろう、というもの。ご自身がファシリテーターを務めました。その後CANVASは成長し、世界最大級の子ども創作イベント「ワークショップコレクション」を開催し、プログラミング教育の必修化にも大きく貢献しています。廣瀬さんにはずっと理事を務めていただきました。
スタンフォードの契約も切れる。2006年。どうしようかなぁ。どうしたらいいですかね廣瀬さん?「メディアに出て、来る仕事を全部引き受けろ。仕事があふれてから考えろ。」六本木の飲み屋でスパッと言われました。
ぼくはホリプロと文化人タレント契約を結び、クイズ番組やら奥様番組やらに出つつ、慶應大学にも拾ってもらい、片っ端から引き受けて、あなた何者?と聞かれるほど訳のわからないヤツになりました。つけていた格好が崩れたと言いますか、被っていたメッキが剥がれたと言いますか、まぁ素になったんだと思います。要するに廣瀬さんは、「カッコつけてんじゃねーよ、動け。」とおっしゃっていたわけです。
それがあって、今日に至る。
役所勤め。MIT・スタンフォード・慶應。そしてまもなくiUというベンチャー大学を開学し、ぼくは人生 三毛作めにさしかかります。今度はスタートアップだけに、じっくりとご指南をいただきたい。iU構想の最初から廣瀬さんには客員教授をお願いしていました。じっくり伺う暇もなく、旅立たれてしまいました。76歳。若すぎる。残念です。
今のぼくの歳のころ廣瀬さんは、東京で中古のポルシェに乗り、ニューヨークのクラブで朝まで踊り、サンフランシスコの朝にエッグベネディクトを食べていました。その姿を思い出しつつ、次の仕事に向かいます。
合掌。
編集部より:このブログは「中村伊知哉氏のブログ」2020年3月19日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はIchiya Nakamuraをご覧ください。