大阪は橋下知事の「大阪都構想」もあり、また名古屋は「減税」が争点となっているために、他の地域と比較すれば地域主権化への関心がまだ高いほうだと思います。橋下知事と平松市長のバトルが面白いだけかもしれませんが。しかし、地域主権化は、きっと日本の産業構造を変え、また日本経済復活を促すエンジンとなってくるのではないでしょうか。
地域主権化には、橋下知事の強調されるところですが、住民サービスの問題と経済活性化の問題のふたつの側面があると思っています。
これまでの議論を聞いていると、どうも地域主権化の問題を住民サービスの問題としてだけに焦点を当てて議論する人が多いのが気になるところです。
柔軟な住民サービスの問題は新党日本の田中康夫さんが長野県知事時代に主張されてきたことに通じる問題でしょう。国と地方とで行政の重なりがあること、また国の一律な基準による地方支配が、地方の特性や現実とあっておらず、高コストになっていることです。高コストだけでなく、しかも住民のニーズにあっていない、だから小泉元総理もおっしゃっていたように、「地方でできることは地方に任せる」ほうがいいという議論です。
しかし、もうひとつの側面としての経済の活性化を考えると、日本は産業転換をいかにはかるのかが今後の最大の課題であり、それを促進するのも地方主権化ではないかと思っています。
Chikirinさんが、野口悠紀雄教授の「経済危機のルーツ」を紹介し、時代の変遷のなかで、いかに日本が脱工業化に失敗し、乗り遅れてしまったかの状況をうまく図で整理してくださっています。Chikirinさんはほんとうに分かりやすくすることがお上手です。
戦後の世界経済が俯瞰できる本 – Chikirinの日記 – BLOGOS(ブロゴス) – livedoor ニュース :
日本は経済にカンフル剤を打てば打つほど、産業構造の根本的な転換に遅れてきたというのが結果を見ればあきらかです。いまだに日本の競争力は「モノづくり」だということ議論があることにはいつも驚かされます。モノづくりでは敗北してきたし、ますます競争力を失っていきます。たとえば日本が強い工作機械は、すでにたんなる製造業かというと違います。高度に情報を集積した産業だから強いのです。
遅れてしまった産業構造を塗り替えるためには相当思い切った政策転換が必要になってきます。それは、かなり大胆な社会実験となってくることは避けられません。なぜ実験かというと、経済は生き物で、かならずしも絶対に保証された結果というのはないことと、経済が国際化してきたなかでは、ライバルは国外にもいくらでもいるので、ほんとうに有効かどうかはやってみなければわからないことがどうしても多くなってきます。
大きな変革は既得権益を持った人たちとの軋轢も生じてきます。それによる社会的な影響も大きくなってきます。おそらく日本全体で規制緩和しようものなら、コンセンサスを取ることも、調整も難しくなり、またリスクも極めて大きくなるので実行が難しくなります。
小さな問題に過ぎないと思えるカジノ特区構想ですら、議論ばかりで遅々として進みません。消費税問題も、日本全体で一律に考えるから政権が揺らぐほどの問題になってしまいます。貿易自由化の問題も、全国で考えると農業問題と正面きってやらなければならなくなります。
国政レベルで考えると、テーマが重くなりすぎ、どうしても中庸な政策になってしまいます。地方主権化は、政策断行のリスクも軽減され、自由度も高まります。
もうひとつの問題ですが、工業化社会は効率性が重要でした。東京に経済の中心機能を一極集中させたほうが効率的でした。それはまさに、現在中国が進めてきていることです。
しかし、堺屋太一さんの「知価革命」に限らず、もう長年にわたって知識、感性、知恵が競争力の中心になってくる時代だと言われてきました。それが経済の現実となってきました。
そんな時代に重要になってきているのが、「多様な個性」が生まれる社会づくり、産業づくりだと思います。それを生み出すためには、社会基盤そのものの個性化と多様化が欠かせません。日本も多極的な経済のハブをもたないと、そんな時代の要請に応えることは困難だと思います。
たとえば、創造的な人材、高度な技術を生み出す人材を集積する都市がますます重要になってきます。それは日本からだけではなく、広く世界からも求めるべきで、シリコンバレーの技術者の6割が外国人であるように、経済力、あるいは社会の成熟度からいえば、アジアのブレーンが集積する都市が日本のなかにあっても自然です。
現実は、日本は海外から日本に来る留学生も頭打ちとなり、また海外から来る労働者も、これまでは伸びてきたのが、製造業の不振で2008年には、こちらも頭打ちになりました。しかも本当に日本にとって必要な労働力が工場労働者ではないはずです。
統計局ホームページ/外国人留学生数 :
国籍(出身地)別外国人登録者数の推移(PDF)
この点も、地域主権が進めば、国全体で外国人労働者の基準を定める必要がなくなり、自由に法律をつくり、来て欲しい人材にインセンティブをつくることもできます。
おそらく観光立国というテーマで、今以上に、地方の持つ自然や文化資産、地域価値がクローズアップされてくると思いますが、経済も地域価値をつくる大きな要因です。それも地域が自ら考え、リスクを負って、実行してこそ地域価値になってきます。リスクを負っていない官僚の日の丸プロジェクトがことごとく失敗するのもリスクを取らないからでしょう。
地域主権化は、地域のみならず、日本全体の戦略自由度を高める鍵となってくると思います。行政サービスから考えることも重要でしょうが、経済が衰退していくとそれすら危うくなってきます。
ぜひ地方主権化は、日本の成長戦略だという視点もあわせた議論を期待したいところです。
地方主権化こそ、全国一律で考えるのではなく、まずは大阪あたりで壮大な社会実験をやってみてはどうでしょう。







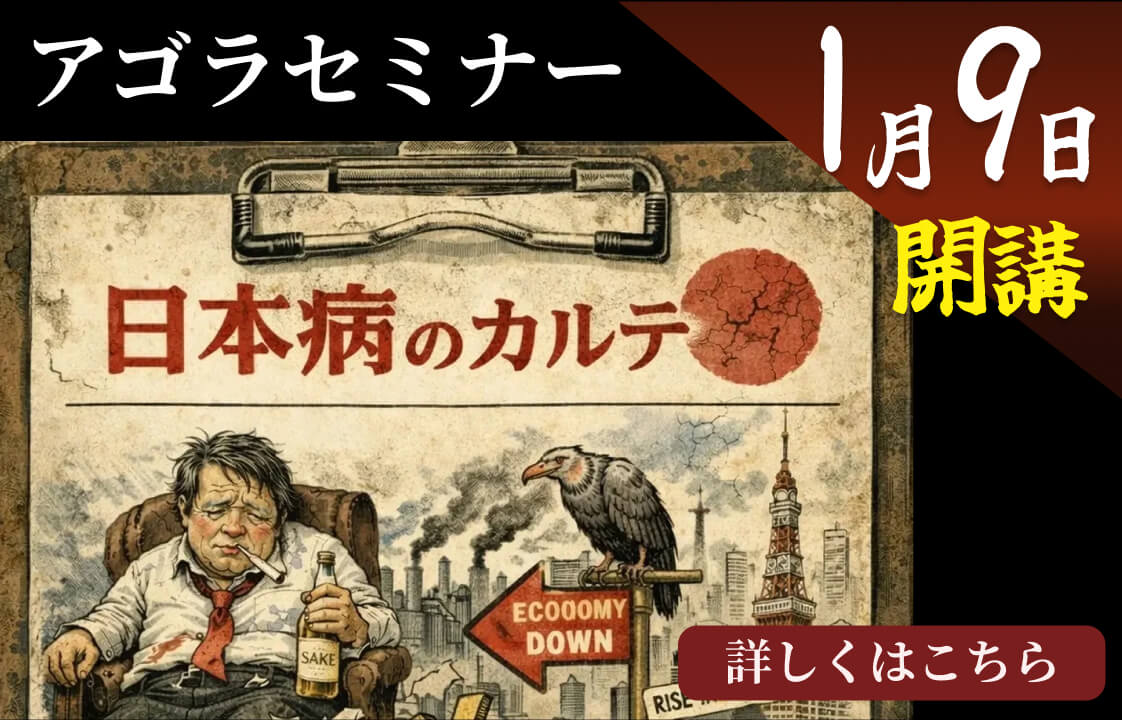







コメント
地域主権、地方分権、どこまでの主権とするかいろいろ定義があって、いつもすっきりしない感じがします。
勝手な意見で、日本を二つにしてみれば考えやすくないか?と思います。国防は二つにはできませんし、国債の返却方法は検討しなければいけませんが、これ以外は司法、行政、立法も含め全く別々に決めてもいいでしょう。
「そうしたら~に問題が生じる。」という点があれば、(例えば通貨、皇室)それがそのまま地方分権の際でも問題になると思うのです。
どこで分けるか、ですが、交流の周波数(50/60Hz)でわけてるのが以外とバランス取れてたりしてません?本当に勝手ですが、あくまでシミュレーションです。
たいへん奇抜ですが、意外とベストかも・・・私たちは、中央集権的に日本再生を25年間目指してきましたが、それが民主政権という「奇形児」を生み出しました。一握りの「霞ヶ関」に財布を預けたら、彼らは破産も何も考えない「完全無欠の禁治産者」のごとく振る舞い、稼ぎの二倍にせまる借金を作り出しました。
ホント許せないのは、現状が焼け野原でも、明日のデザインが描けるのならまだいい、自分の子供に朝の直前だから今一番暗いのだって説明できるなら、まだ私たちも救われますが、ほとんどの国民は、明日はもっと悪くなるだろう・・と閉塞感しかもてないことです。完全に二つに分けて、競争原理を働かせるという選択肢があってもいいかも。政府の押し付けでなく同じ国民どうしで、よい社会を築くのを競い合うのです。日本は島国で競争というのが今一度、身近に感じなかったのが、あまり緊迫感のない社会を作り出してしまったと思う。二分でうまくいったら、もう少し合理的な道州制を目指す選択肢も、その先にあるかも。少なくとも自治や社会を自ら作るという自覚を多くの人がもてる。民族として競争はしながらも、お互いエールを送るスポーツ精神のようなものになると思います。
霞ヶ関は罰符として、かつての国鉄清算事業団のように、借金と一歩社会に出たらなんの生産性もない人々の再訓練の場程度でいいと思う。