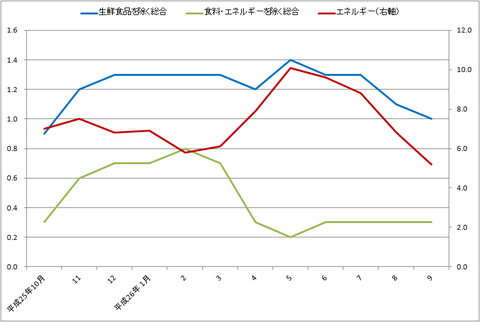※(その3)より続く。
16、17世紀の長い過酷な宗教戦争の経験から、ヨーロッパは政教分離を大原則とし、特にフランスは宗教の影響力を注意深く抑制しようとする。しかし信仰の自由を中心視するアメリカでは、信仰は政治、社会に大きな影響力を持つ。紙幣、貨幣には“In God We Trust”と刻印されているし、「教会に毎週行く人」という言葉は「信用のおける人」という意味で使われる。これは信じること自体を重んじる傾向ともなり、ダーウィンの進化論や地球温暖化を否定する人々がアメリカで横行する原因ともなっている。信仰は事実による保証を必要としないばかりでなく、科学や理性による反証を受け付けない。そのような態度をとる自由も保証されているのだ。共和党には思想的純粋性(ideological purity)などと唱え、教条主義が美徳だとしている人も少なくない。
自由市場主義者は、スティーヴ・ジョッブスやビル・ゲイツは政府の助け無しにビジネスを育て、多くの仕事を生み出したと主張する。これは政府機関は彼らのお得意様の筆頭である上、連邦政府は彼らの特許を国の内外において保証していることを無視している。政府のお世話に何か何もなっていないと称するアメリカ人は数多いが、僻地で自給自足生活をしているのでなければ、上下水道から道路や学校まで、政府無しでは存在しないものに頼って生きている。そんなことは都合よく無視して、個人の自由を標榜するのである。
この政府筋のコントロールからの自由のシンボルがカウボーイである。無法状態に近かった19世紀のアメリカ西部にあっては、馬と銃による自営団が連邦政府から独立してコミュニティーを営んでいた。しかし、カウボーイは「白人を西部に広げようという神の意志(Manifest Destiny)」を標榜し、アメリカン・インディアンやメキシコ人から土地や財産を奪って当然としていた時代の産物である。それが理想では、強者は社会に及ぼす影響や法規制などは顧みずに自己利益の追求に奔走することが正当だと考え、弱者は自らも強者になれるものと夢見て、不公平な扱いに甘んずるという構造の社会ができてしまう。フランスやドイツがグーグルやアマゾンを規制しようとするのは、こういうカウボーイ資本主義の弱肉強食性を非倫理的だとするからである。
先日、マイクロソフトのCEOサティア・ナデラは、賃金格差を解消するために女性は積極的に昇給を求めるべきかという質問を受けた。彼は、「「昇給を求めるかどうかの問題ではなく、システムがいつも自分のしているのに見合った昇給をしてくれると知り、信じることの問題だ。それがよいカルマだ。誰かがこれは信頼できる人間だと思ってくれるという見返りがある」と答えて、猛反発を買った。これはたまたまコンピューター業界で活躍する女性を主題とするシンポジウムにおいてだったので、そんな見返りなんてないことをよく知っている働く女性からの反撃を受けた。しかしナデラは例外ではない。CEO達ばかりでなく、自由市場資本主義経済学者達も、このシステムは私の才能を適切に認めてくれているのだから、これがあなたの才能も適切に評価しているのだと信じなさい、と皆に言ってきたのである。(『21世紀の資本論』第8章参照)
アメリカ人はジョッブスのような人達を偶像化し、彼らの言うようにすれば自分達も成功できると信じ、経済的成功者の意見を有難く拝聴してきた。世俗主義のフランスから来たピケティは、そんな偶像に騙されるな、「神の見えざる手」に導かれた市場は常に正しいなどという自由市場主義経済学を疑え、と言う。ピケティ論争は経済学論争であるばかりでなく、宗教文化論争でもある。「思想的純粋性」派は自らの信仰に反するピケティやクラークの論は頭から否定してすませる。しかし理性を重んずるならば、経済学者は経済学を改めて検証し、信仰と科学を分別せねばなるまい。
宮本 陽子
歴史研究者(無所属)
オーストリア・ウィーン大学歴史学博士(D.Phil.)
シカゴ在住
ホームページ:Demystifying Confucianism