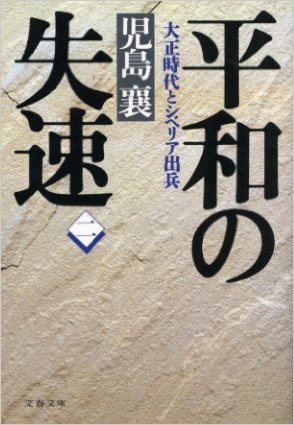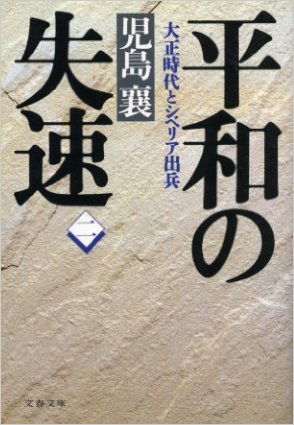
児島襄「平和の失速第三巻」から(但し画像は第二巻)
第一次大戦中対ドイツ参戦を決めるに当り元老(山縣、大山、松方、井上)の意見を聞くことになり首相官邸で先ず外相加藤高明が参戦方針を説明した。ここで加藤は日本が参戦する目的を三つあげる。日英同盟上の義務、三国干渉への復讐、中国における利権の拡大である。以下P42から
山縣は不快感をかきたてられた。戦争は国家の危難を排除するためにのみ認められるはずであるのに加藤外相によれば主として(中国における)経済的利益を追求するために戦争しようとする印象を受ける。それは邪道ではないのか。中略
次いで山縣は次の三つの配慮の必要性を指摘した。
ドイツへの配慮
仮に今時大戦でドイツが敗北したとしても、ドイツ国とドイツ人が地上から消滅するわけではない。日本が参戦すればドイツ人から永久の恨みを買うことにならないか。
ロシアへの配慮
三国協商陣営(英国、フランス、ロシア)が勝った場合ロシアは背後のドイツの脅威から解放されるのでその後東洋に向かって発展をめざすことなり、日本の脅威となりはしないか。
人種戦争への配慮
欧州大戦の根底には人種間の争いがある(アーリア人とスラブ民族)。この戦争が終われば米国の排日機運が示すように必ずや白人対黄色人種の新たな人種間戦争が生まれるに違いない。日本は同じ黄色人種としてこれまでの(侵略的)対支那政策をあらため、日中友好を進めて味方を増やさなければならない。
火事場泥棒式に中国に進出しようとする加藤外交への批判である。以上引用
山縣はこの立場から、その後の対支二十一箇条の要求を厳しく批判する。
山縣と言えば陸軍の法皇と呼ばれ軍国主義の権化と思っている人が多いが、実は日清戦争、日露戦争、そしてここに見られるように第一次世界大戦いずれにも極めて慎重であった。日清戦争は外相陸奥宗光、参謀次長川上操六、駐清国公使小村寿太郎、日露戦争は外相小村寿太郎、参謀次長児玉源太郎、第一次世界大戦は外相加藤高明が開戦論をリードした。彼らはいずれも維新の第二世代(加藤は第三世代というべきかもしれない)であって第一世代である山縣や伊藤博文は常に開戦には消極的であった(第一次大戦当時伊藤は既にいない)ことは記憶する必要がある。
ここにおける山縣の見通しは必ずしも当たらなかったが伊藤にしろ山縣にしろ明治国家を作ったものとしての責任感の強さ、視野の広さはその後の世代とは明らかに懸絶している。
「人間一度は清水の舞台から飛び降りる覚悟が必要だ」と して日米開戦を決めた軽躁な東條英機の無責任ぶりと 好対照をなしている。
山縣が対独参戦は邪道だと批判したように、国外でも日本の参戦は評判が悪かった。以下はその時のアメリカの新聞論調 P86
ニューヨークトリビューン紙
ドイツは膠州湾に孤立しその艦隊は小勢力にとどまり青島基地の存在は欧州大戦には関係がない。日本は日英同盟の友誼に基づき参戦するというがその必要はあるのか。
フィラデルフィアレコード紙
日本の参戦はドイツが欧州で手一杯であるのにつけこんだものである。日本は膠州湾の次には(ドイツの委任統治領である)南洋のカロリン、マーシャル諸島の奪取を図るであろう。
注:日本はパリ講和会議の結果これらの島嶼を獲得する。
ニューヨークアメリカン紙
米国はいつか日本がフィリピンに手をのばすのを阻止するために大西洋、太平洋の平和を確保するための大海軍をもたなければならない。
政友会総裁原敬も対独参戦を懸念し山縣の私邸を訪ね以下の意見を述べるP63
たんに「漁夫の利」或いは火事場泥棒式に同盟関係を理由として開戦が認められそれが先例になれば道義の否認にほかならず政治道徳と国民道徳の荒廃は必至となる。誠に憂慮に耐えない。
山縣も完全に同意見であった。
後年山縣が原敬を首相に推す心境になったのはこの時の会談の印象があったためかもしれない。
青木亮
英語中国語翻訳者