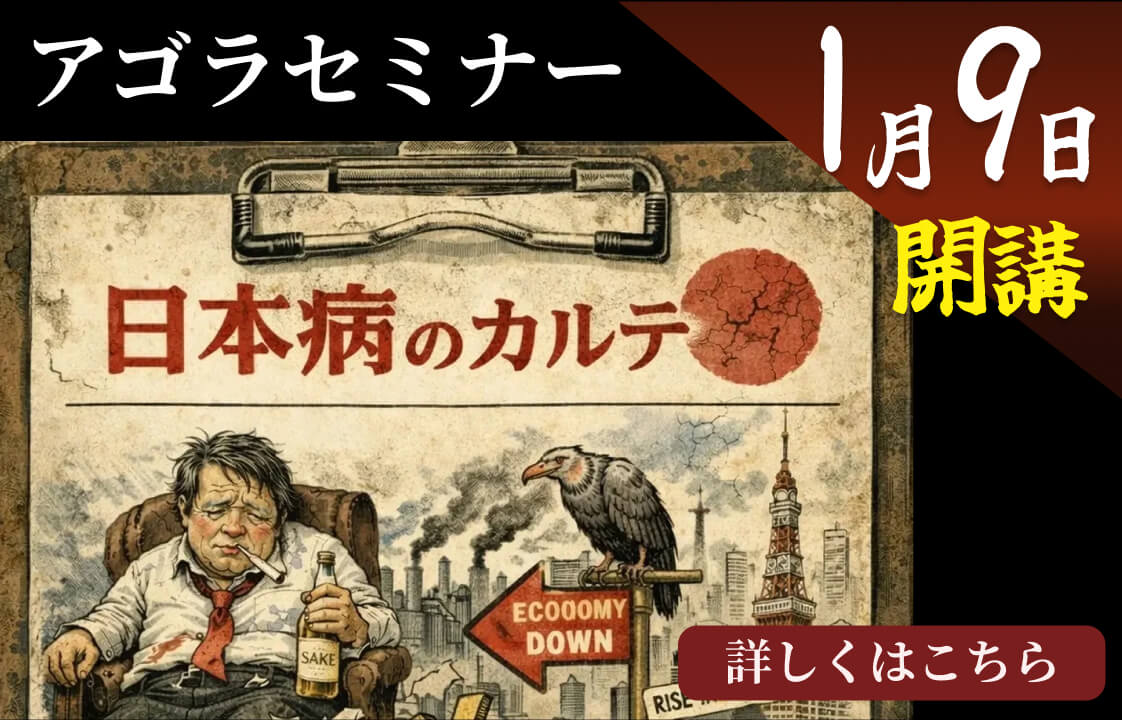このごろ日本でMMT(現代貨幣理論)という理論が流行しています。これは50年ぐらい前からある話で、現代的でも貨幣理論でもないのですが、経済運営が手詰まりになった日本で今ごろ話題になっています(2020年1月15日の記事に加筆)。

Q1. MMTって何ですか?
MMTは新しい理論ではありません。不完全雇用のときは財政支出で総需要を増やすべきだというのは、1930年代のケインズの理論と同じです。国債は将来世代の負担にならないというのは、1950年代のラーナーの理論です。これを1990年代にレイなどが主張しましたが、アメリカでは相手にされなかった。
Q2. では何が注目されてるんですか?
日本で注目されているのは、安倍政権の内閣官房参与だった藤井聡さんがMMTを宣伝し、政調会長の高市早苗さんが支持したり、MMT派の西田昌司さんが自民党の財政政策検討本部長になったりして、政権への影響が強まっているからです。でもこういう人は経済学を知らない素人で、MMTを支持するプロの経済学者はいません。
Q3. 「自国通貨を発行できる政府は財政破たんしない」というのは本当ですか?
嘘です。財政破たんが「国債が返済できない」という意味だとすれば、自国通貨を発行できるロシアもメキシコもアルゼンチンも、国債を返済できなくなりました。
他方で自国通貨を発行できないドイツもフランスも、財政は破たんしません。日本政府の借金が増えても破たんしないのは、国民が政府は借金を返すと信頼しているからなのです。
Q4. 「国債を日銀が買えば国の借金はチャラになる」というのは本当ですか?
これも嘘です。日銀が銀行などから国債を買ったとき、銀行はその代金を日銀当座預金として預けているのです。これは日銀の民間に対する借金ですから、政府全体でみると、長期の借金(国債)を超短期の借金(日銀当座預金)に置き換えただけで、政府と日銀を合計した借金は同じです。
Q5. 「国債は国民の資産だから負担にならない」というのは本当ですか?
これも嘘です。借金はいつも貸し手の資産ですが、国債の返し方は民間とはちがいます。いま国債を買う人は自分の意思で買いますが、将来それを税で返すときは強制的に増税されます。国債は現在世代の資産ですが、将来世代の税負担になるのです。
Q6. では永遠に国債を返さなければいいんですね?
国債の償還を永遠に先送りするネズミ講ができれば、国債は負担になりませんが、そんなことはできません。ネズミ講を続けるうちに金利が上がると、雪ダルマ式に借金が増えて、返せなくなります。
その国債を日銀が買い取って金利上昇を防ぐと、インフレになります。インフレになったからといって国債の発行をやめると、政府の支出がまかなえなくなります。
Q7. インフレになったら増税すればいいんじゃありませんか?
増税は法案をつくって国会が同意しないといけません。1997年に消費税を5%に上げてから2019年に10%に上げるまでに22年もかかった日本で、そんな簡単に増税はできません。
Q8. なぜそんな古い理論が、いま流行してるんでしょうか?
MMTはアメリカで生まれた理論ですが、アメリカでは誰も知りません。日本で受けるのは、それが国債と通貨を同じと考えて金利を無視する理論なので、ゼロ金利の日本では問題を単純化できるからです。ここでは金利リスクはないので、国債はいくら発行してもいいわけです。バラマキをやりたい政治家のみなさんには、ありがたい理論ですね。
Q9. MMTにはまったく意味がないんでしょうか?
そうでもありません。MMTのもう一つの特徴は「信用創造は預金の制約を受けない」という内生的貨幣供給説です。たとえばA銀行がB社に1億円貸すとき、1億円の札束を持って行くわけではありません。A銀行にあるB社の預金通帳に万年筆で「1億円」と書いたら終わりです。
これを万年筆マネーといいます。現代では「キーボードマネー」といったほうがいいと思いますが、これによると貸し出しは資金需要で決まるので、日銀がいくらお金を発行しても、資金需要がないと貸し出しは増えません。国債を発行するときも、それを銀行が買ったとき貸し出しが発生するので、税収の裏づけは必要ありません。
Q10. では政府はいくら借金してもいいんですか?
そうではありません。国の借金という意味では国債もお金も同じなので、日銀がいくらゼロ金利の国債を買ってお金を増やしても何も起こりませんが、これからインフレになって金利が上がったら国債の価格が暴落します。
このときどうなるかについて、MMTは何も教えてくれません。それは金利はつねにゼロと想定しているからです。銀行の保有する国債が値下がりすると、預金の取り付けが起こって銀行がつぶれ、金融危機で経済が崩壊するでしょう。財政が破たんしなくても、みなさんの生活が破たんするのです。