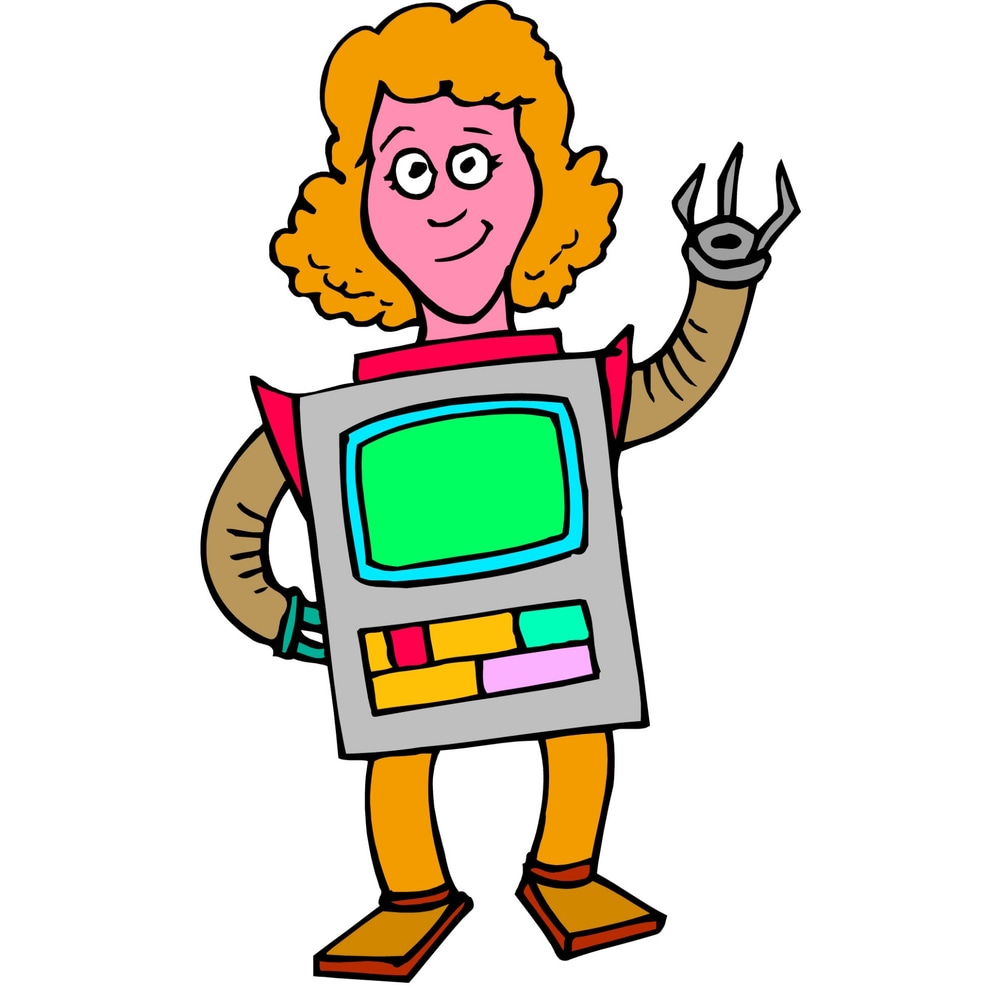いわゆるリーマン・ショックとギリシャ・ショックと呼ばれた百年に一度のショックが続けておきたことによる世界的な金融経済危機は後退した。リーマン・ショックとはあくまでリーマンの破綻によるショックが大きかったことで象徴的なものとなっているが、米国のサブプライム問題と複雑化した金融商品が原因となっていた。住宅バブルや金余りによる金融資産バブルが崩壊し、欧米の金融機関を直撃したことによる金融不安である。
ギリシャ・ショックもギリシャの財政に対する懸念が発端ながら、財政に不安を抱えた国をユーロ圏に止められるのかといった問題から、欧州の信用不安が強まり、ギリシャやポルトガル、イタリアなどの国債が急落し、これによって金融経済リスクを強めた。
これらの金融経済危機に対する財政面からの救済措置には限界もあった。金融危機は金融市場を通じて顕在化していたこともあり、市場参加者の不安を除去する必要もあった。そこで動いたのが中央銀行となる。政策金利の低下余地は限られたことで、日米欧の中央銀行が採用したのが、非伝統的な金融政策となった。その手段として取られたのがマイナス金利政策や、以前に日銀が世界の中央銀行で初めて実施した量的緩和政策であった。
米国のFRBやイングランド銀行はこの量的緩和を主眼に置いた。ECBは市場の正常化という目的のもとに国債の買入を行った。日銀も国債の買入を増額させていったが、このリスクに対しては長期国債の買入などには手をつけなかった。それでも長期金利は低位で推移していた。
日米欧の非伝統的な金融緩和策、特にECBの政策が功を奏して、市場はリスク回避の動きを後退させつつあったのが、日本でアベノミクスと呼ばれたものが登場したタイミングとなった。特段、世界的なリスクが強まっていたわけでなく、むしろリスクが後退していたところに、日銀が異次元の金融緩和を行ったことになる。アベノミクスの登場で円安株高が進んだが、あくまでそんなタイミングだからこその動きであり、巻き戻しの動きが一巡すれば落ち着いてしまうことも当然といえる。
大きなリスクが後退したことで、今度は非常時の金融緩和から正常に戻る動きは当然といえる。英国のEU離脱や新興国の経済への不安等もあり、さらに正常化はつまり金融引き締めにも映ることで市場への影響も警戒され、なかなか踏み出せなかった。日銀はなぜか一層の金融緩和をせざるを得ない状況に追い込まれていった。
しかし、中央銀行が大量に国債を買い続けるにも限界があり、いつまでも緊急時の対応を続けるわけにもいかない。いち早くそこから脱してきたのは雇用がしっかりしていた米国である。それでもテーパリングとその後の利上げはかなり慎重に行った。ここにきてやっと資産の縮小に手を付けることが予想される。
ECBも10月にも資産買入の縮小を検討するとみられる。イングランド銀行は新たな国債買入は行っておらず、まずは利上げを視野に入れている。日銀は物価目標を達成するとしてしまったため、出口政策は取れないながらも、政策目標を量から金利に置き換えた上で、国債の買入額を縮小しつつある。
中央銀行による国債大量買いの時代は終焉しつつある。これは物価が上がってきているからではなく、あくまで大きな危機が去ったからであることを認識する必要があろう。
編集部より:この記事は、久保田博幸氏のブログ「牛さん熊さんブログ」2017年9月15日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方はこちらをご覧ください。