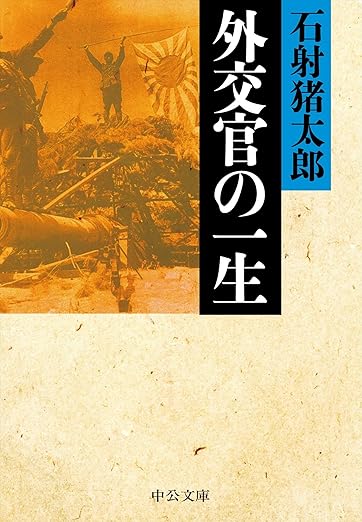
1920年代の国際協調時代から軍国主義時代、やがて太平洋戦争における敗戦という激動の20年間にわたり外交官として活躍した人物による回顧録。
石射は、今風に言えばチャイナスクールの外交官として、広東や天津、吉林そして上海で在外公館勤務を、本省においては中国外交を統括する東亜局局長としての経験を重ねた。彼は、満州事変を境に、政府の日中事変の不拡大方針が、陸海軍や関東軍の独行により有名無実化し、外交が軍部に壟断されていく様を第一人者として目撃しつつ、霞ヶ関正統外交の継承者の一人として、中国を舞台に日本の対華善隣外交を与えられた職責で実践し、日本の国際信用の失墜を食い止めるべく奔走していく。
『外交官の一生』は、時代に抗った外交官の物語として、外交機関が有すべき「勇気」の重要性を示唆している。
1. 霞ヶ関正統外交とは
そもそも、石射が近代日本外交の至高と表した幣原外交の特徴とは何か。石射は在米日本大使館勤務時に当時の幣原大使と机を並べた経験を持つが、彼によれば、幣原外交は次のように表現される。
「幣原さんは外相在任中宣明した外交政策において、日本は偏狭な利己的見地に執着せず、列強との共存共栄の主義を堅持すべきであることを強調し、また外交政策の継続性を維持することによって、国家の対外威信の保たれるゆえんを説いた。また一国が力を恃んで、列強間に専横を極める時は、遂には無残な失敗を免れないとして、国際間の調和が永遠の利益を確保する者である事を明らかにした。特に動乱常なき隣邦中国の事態に、深く同情すると同時に、その国民的要望を尊重すべきであるとの建前の下に、徹底的不干渉主義を固執した。隣邦に対する幣原さんの深い同情は、心ある者の胸を打った。」
(140‐141頁)
また、石射によると、幣原外交は幣原外相の専売特許ではなく、綿々と受け継がれてきた霞ヶ関正統外交の延長であり、そのスタイルを内外の圧力に屈せず貫徹した勇気に、幣原外交の傑出した価値を見出している
「しかしこうした政策は、幣原さんの発明でなく、平和主義といい国際協調といい、対華不干渉といい、従来歴代外務大臣の掲げた政策の基調をなしたもので、いわば霞ヶ関の正統外交政策なのであった。ただそれが周囲の圧力に歪曲されて、いつも口頭禅に終わっていたのを、幣原さんが飽く迄守り通したところ幣原外交の特性があった。荒ぶる外部の論難攻撃に動じなかった信念の強さが、幣原外交の生命なのだ。」
(同上)
石射の上のような幣原外交への自負は、同人が若き書記官として幣原駐米大使の下で霞ヶ関正統外交の一翼を実践してきた経験からも求められるかもしれない。しかし、その後石射が中国における総領事や局長ポストを務める時代になると、霞ヶ関正統外交は軍部と右翼、それから世論による非難も重なって次第に社会的な正当性を失っていく。
満州事変以降、軍部が華北分離工作や自治政権の確立、満州国の独立、そして上海や南京における日本政府(外務省)の意思決定を介在しない形での軍部独断の局所的な軍事衝突と、時代はまさに外交が軍部に壟断される時代に突入していた。
もっとも、外務省にそれを許さないとする意思や勇気、知恵の発揮が欠けていたとの視点も重要であり、外部圧力を跳ねのけ列強間協調を基調とする外交を継続する信念と勇気——幣原外交——を失ったことの外務省の責任も問われるべきだ。
石射の述懐は、軍部責任論に流れる傾向があり、他律的であるところに留意が必要と感じる。外務省が外交一元化を損失していくプロセスについて、幣原外交を近代日本外交の至高とするのであれば、その喪失の過程と外務省の責任について綴るのもプロフェッショナリズムの一つの仕事ではないかと読後に感じる。
石射は、中国大陸における日本陸海軍による独断専行の派兵や武力行使を、なかんずく政治家(近衛首相や広田外相)の責任不履行論に帰している印象がある。もっとも、真珠湾攻撃以降、対英米にも戦線が開かれ、帝国日本としての戦争の大義を国際に理解せしめんために作成された大東亜共栄会議やその宣言の欺瞞性は石射も外交当局の一員として見抜いていたが、同人が、ソ連であれ何であれ、具体的に終戦工作のために骨を折ったとの事績は本書からは確認されない。
ただ、当時の時代人でもなく、置かれる立場も大きく異なる小生をして石射に職業人としての怠慢があったと責めることは心苦しい。
石射は、与えられた職責で日中事変の早期終結、そうでなくとも事態の「止血」に意を注ごうとした意識は確認できる。軍部と右翼が外交を壟断する時代に逆行し、霞ヶ関正統外交と対中善隣主義を回復しようとした勇気こそが、石射の外交官の価値であるとも評価できよう。
「私は、中、日のみならず、諸外国の神経が錯綜するこの国際都市を、断じて再び戦火の巷とすべきでない。平和はまず上海からと思い定め、着いて間もなく新聞記者会談で、上海だけは如何なる場合にも無風状態に置くのが、私の抱負だと語った。そしてその抱負に忠実ならん事にこれ務めたのが、私の上海在勤の全意義であった。」
(上海総領事時代/207頁)
「私は一総領事の身分として世界平和のために貢献するなどという、ヴィジョンの広い理想の持ち合わせはなく、ただ、霞ヶ関外交の伝統たる国際協調政策の一使途たるに過ぎなかったが、中日関係についてはユートピア的の理想を温存していた。・・・理想への境地の道は遠しといえども、到達不可能ではない。これに向かってちょっとでも一尺でも荊棘(けいきょく)を開く、その努力は中国側にもこれを期待せねばならないが、まず徳を建て範を示すべきは、強者日本であらねばならない。それは一総領事の力をもって拓き得る境地ではないが、少なくとも自己の職域だけには、この理想を推し進めよう。こうした考えから、私の着任第一声『上海を無風状態に』が生まれたのであった。」
(210頁)
2. 霞ヶ関正統外交の今日的示唆
石射が惜敗の情をもって懐古した霞ヶ関正統外交-国際協調主義と平和主義、対華善隣主義政策-は現代日本外交にいかなる示唆を与えるだろうか。
第一に、批判を恐れずに言えば、日中の強弱関係は先の日中事変時とは様変わりしている。世界第二位の経済大国であるに加え、伸張する海軍力や核・ミサイル能力、サイバーをも駆使した総合的な国防能力を有する軍事大国であり、西欧がそのルール・規範形成を主動した国際法体系及び自由主義的国際秩序を換骨奪胎せんとする外交的意思を有する「国際大国としての中国」に、今日の日本は対峙している。シンプルに言えば、先の時代に比べ、日中の攻勢は逆転している。
今日の日本外交の最重要課題は、「広い意味での中国の力による現状変更」——領域拡張から地域・国際秩序の変容ないし相対化の試み——に対して、日本が同盟国・同志国と以下に有機的に連携し、総合的な均衡状態を日中間に現出・維持することにあると小生は考えている。
具体的には、日米同盟、つまり在日米軍やインド太平洋軍との連携をつうじて、抑止力と対処力を中心に大勢の均衡を維持すること、次に、G7や豪州やインドといった同志国との連携を外交・軍事・経済・情報面で補強すること、さらに、東南アジア諸国の経済成長と社会的安定を手助けすることでその戦略的自律性を促進させることが戦略的な外交政策の体幹を成す。戦略的な見地で、複合的に外交政策を組み立て実施することによって対中関係の総合的な均衡を維持することが、日本外交の当座の主要命題と考えている。
むしろ霞ヶ関正統外交の意義は、習近平時代になり強国思想にひた走る中国自身が学ぶべきではないかという皮肉な感情に誘われるが、そのような日中攻勢が逆転した様の時代においても石射の述懐が今日の日本外交に与える示唆はある。それは、外交の継続性を担保するプロフェッショナルの「勇気」の問題である。
時代は変われど、外交機関は、その時その時の内外の圧力を受けるものである。80年前、それは軍部と右翼が主張した大陸権益の拡張主義であった。今日の外交政策に対する内外の挑戦を洞察し、然るべく応答できるロジック、言葉そして勇気をもつことが外交機関の究極的な仕事であることを石射の回顧は示唆しているのではないか。
国際協調主義の意味合いも、幣原時代と今日とでは大きく異なるが、国際主要国と足並みをそろえ、国際的な紛争ないし第3国・地域の経済・社会の不安定化を防ぐために、適切な外交政策を実施・継続することに躊躇しないという点に共通項が見出せる。
今日の東アジアとインド太平洋の最大のリスクは、中国を筆頭に、安全保障上の均衡の崩壊による軍事衝突にある。その均衡を、外交・軍事・経済・情報という安全保障政策を構成するすべての側面を動員して維持・強化するのが当面の日本外交の最も重要な仕事である。
その意味での国際協調主義が令和の日本には求められていることを認識したうえで、外交政策を実施・継続するロジックと勇気を外交機関が有することが、『外交官の一生』に対するひとつの実践的読書ではないかと感じている。
今一度、石射の幣原外交評を噛みしめることをもって本稿を閉じたい。
「幣原外交の真価は、自ら搔き立てた霞ヶ関正統外交の法灯を、飽くまで守り通した信念にあった。信念に徹するがゆえに、外に対しては条理をかざして、自主的に力強く動いた。内は幣原外交を歪曲せしめんとする、諸勢力の圧迫に屈しない。国内の囂々(ごうごう)たる非難攻撃に堪え、身近に迫る危険を恐れなかった。信念の外交であり、また勇気の外交であった。日本の国際信用は、これがために躍進し、外務省正統外交の黄金期を現出した。しかししれは長続きしなかった。幣原氏退陣後の外務省には、その残した正統外交政策はなお基調として存したが、信念と勇気亡きところ外務省の正統外交は一路衰微へと転落した。」
(450頁)
編集部より:この記事はYukiguni氏のブログ「On Statecraft」2025年11月2日のエントリーより転載させていただきました。














