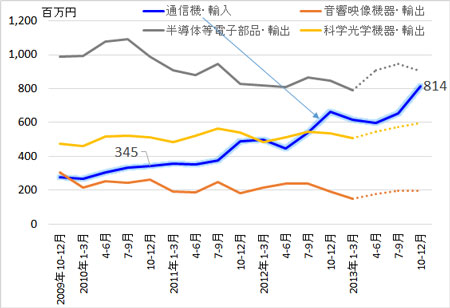内閣法制局の憲法解釈をめぐり安倍首相が「憲法解釈の最高責任者は私だ」と答弁した事に、与野党から批判が出たそうだが、首相の答弁が「憲法解釈の(行政府に於ける)最高責任者は私だ」と言う意味であれば、安倍首相が正しい。
なぜかと言えば、「内閣法制局設置法」の第七条で「内閣法制局に係る事項については、内閣法 にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする」と内閣法制局の最高責任者は内閣総理大臣であると定められているからである。
それにも拘らす、この当たり前の答弁が問題になる背景には、「立憲民主制」である筈の日本を、事実上「立憲権威制」に堕落させた象徴的存在である内閣法制局の「権威主義」がある。
法制局のうぬぼれと厚顔振りを物語る実例として、退官後に最高裁判所判事に天下り(天上がり?)した故高辻正己元法制局長官が現役時代に新聞インタビューで内閣法制局の存在意義について述べたコメントを紹介したい。
「何のために法制局があるかと言えば、政府の施策が法の支配、法の定めるところに従って実施されることを担保するためですよ。……内閣は行政各部を指揮監督できるんですが、内閣が法制局を指揮監督するというのは考えられない。法の支配を考えると、法律判断というのを内閣がやっていたらきりがない。だがら、法制局が重視されざるをえない」
この「内閣が法制局を指揮監督するというのは考えられない」と言う、何とも非論理的で傲慢な発言には怒りを覚えるが、これに反論もしないマスコミや識者の権威への屈服振りも見事なものである。
政治的システムとしての権威主義の特徴は:
①政治的権力は被統治者に対して何ら憲法上の責務を負わない。②単一の指導者または少数エリートに集中される反民主性。
③指針となるイデオロギーの欠如。
③社会的機構に幾らかの複数性を許容する。
④他人の意思や意見への関心が欠ける。
等があげられるが、内閣法制局はこの全てが当てはまる。
故高辻元長官の意味する処は「政権交代があったとしても、一義的に導き出される憲法解釈の変更を認めない」と言うに等しい。
この事は「一度示した憲法解釈、法律解釈は誰が首相でも、政権交代があっても従来の見解は頑として変更しない」と選挙で示された国民の意志を含む全てからの「超然性」を求める暴論で、これを崩すには首相が法制局内の順送り人事を無視して自分の信頼できる人物を持って来る他に方法がない。
安倍首相が、新長官に小松氏を連れて来たのもこれが理由であろう。又、設置法に定められた法制局の担当職務が内閣の相談係である以上、首相が自分の信頼する人物を長官に任命するのは当然である。
英米法の泰斗で少数意見の多いことで知られた故伊藤正巳元最高裁判事(東大名誉教授)が退官される際に「先輩には、補足意見は無駄な独り言だと言われもした」と嘆いた通り、法制局や最高裁に限らず、日本の司法幹部には長いプロセスに於ける少数意見から学ぶ利点も知らない時代に遅れた余りに不適格な人物が多すぎるのも問題である。
支配の形式である前にその中身が正義・公正の原則に合うものでなければならないとする「法の支配」と異なり、法律の文言や形式に重きを置く「法治主義」は、法律によれば解釈次第で何でも出来ると言う「法律万能主義」に陥り易い欠点がある。
国家の近代化で一歩先行していた英国に追いつこうとした独仏などの大陸欧州諸国は、分散的な封建主義から中央集権的近代国家に移行しようとして、中身・内容は二の次にして体裁を整える事を優先してローマ法を発展させた法制度(大陸法系の法治主義)を導入した。
その結果、法文解釈の「硬直化」や「権威化」が広がり、(1) ジャコバン党の恐怖政治(フランス)(2) ナチスの席巻(ドイツ)(3) ソ連の全体主義支配(欧州全体)。と三回に亘る制度危機に直面し、その度にコモンローの英米両国に救われて来た。
この傾向は第二次大戦後も変らず、頻繁に憲法や統治形態の変更を迫られ、1945 年の第二次世界大戦終結から2010 年に至るまでに、成文憲法の無い英国は別として、アメリカが6 回のみであったのに対し、フランスは27 回(1958 年の新憲法制定を含む)ドイツは57 回も憲法を改正して制度の陳腐化を防いで来た。
大陸法的な憲法運用をする日本が戦後一度も憲法を改正していない事実からも、法制局による「恣意的解釈」で誤魔化して来たことは火を見るより明らかである。
近代国家で唯一成分憲法を持たない英国が「憲法の祖国」と言われる理由は、国民の権利・自由を保障しそれを守る為に民主主義的な政治制度を定めた1215年のマグナ・カルタに遡る気の遠くなる様な昔から、中身・内容を重視する「法の支配思想」を守って来たからである。
又、独立した精神と自由への愛着の強い裁判官が「法の支配」を実現する上で最も大きな役割を果たすと信ずるコモンロー国家では、裁判官の独立性を保障する為に日本の様に昇進、昇給,更には任地についてまで最高裁事務局や上司を気にして行動しなければならない官僚制度の適用を意識的に排除している。これは、裁判官の好みや恣意的判断を防ぐ重要な智恵でもあり、アメリカややカナダでも踏襲している。
法律を学んだ事のない私には、ケルゼン純粋法学も修正自然法論も理解の外だが、ここに挙げた例でも判る通り「法の支配」を採用するコモンローの国と大陸法系の「法治主義」を採用する諸国の統治制度や憲法の永続性や安定度を比較すると、「法治主義」国家の劣勢は明らかである。
1889年当時から既に時代遅れだと言われていたプロイセン憲法を真似て、大日本帝国憲法を制定して「法治国」入りした日本は、内容も理解もせずに殆ど直訳して沢山の法律用語を整える事で形式的な近代化を果たした。
この慣習は現在でも継承され、アメリカの強い影響を受けて制定された日本国憲法でありながら、英米とは全く異なる戦前からの日本の伝統に沿った権威主義と仲間意識を中心とした運用と解釈が横行し、永らく行政訴訟は門前払い、憲法判断は回避する時代が続いた。
そのため、憲法第八十一条 で「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定しているにも拘らず、政治とのかかわりを嫌い違憲判断を避けたい最高裁の意向を知る内閣法制局は、何の法的根拠もなしに「法制局、法の番人論」と言う流言飛語を流し、憲法上の責務を負わずに実態的な単一憲法解釈権を手に入れた。
その背後には、最高裁と司法行政当局との互助会的な談合もあると思われるが、この点は改めて触れる事にしたい。
法治主義のもう一つの欠点は、いくら細かく規定したとしても解釈の余地が全く無い法律と言うものはあり得ない事で、例えば、「白馬」の売買を禁止する法律を制定しても、法解釈の責任者がその馬の背中に数本の黒毛を発見して「この馬は白馬ではない」と解釈できる「恣意的な判断」が容易な点である。
しかも、内閣法制局は相対立する法解釈に弁論の機会を与えすに「白馬でないと言う結論が論理的な帰結である」と問答無用の宣言をしても誰も抵抗出来ない組織に変えてしまった。
米国の大統領制の三権分立統治とは異なり、英国や日本の議院内閣制に於いては必然的に行政が強くなる宿命にあり、今回の「内閣法制局」問題を契機に、我が国も明治以来継承して来た大陸法的な「法治主義」の弊害をきちんと認識した上で、英米流の「法の支配」原理を日本の法体系に融合する時期である。
以上の事からも憲法改正は喫緊の課題であるが、次回は米国司法省法律顧問局(OLC)と日本の法制局の機能を比較しながら、現憲法下でも現実の政治課題を迅速に処理出来る具体策を論じたい。
2014年2月27日
北村隆司