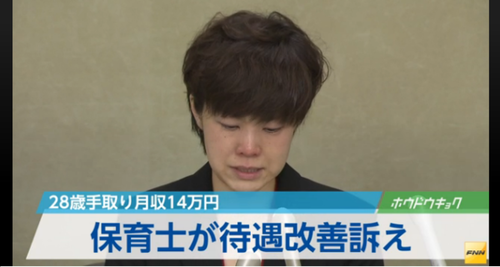職人話を耳にするのが好きである。本人たちは右から左に、普段の通りに話しているつもりかもしれないが、その道に疎いわたしにしてみれば、あとあと役に立つ金言があったりして聞き逃せない。

かなりむかしのことだが、年配のコックやベテランのウエイターの雑談にまぎれこんだことがある。話がふと、
「やっぱりサラダやろな」
「そやそや」
という展開になった。ご存知の方もあると思うが、きちんとしたレストラン、味のたしかなレストランかどうかは、サラダの扱いを見ればだいたい見当がつくというのである。
その場にいた経験豊富な人たちの言うことに、その時はいまひとつ理解が及ばなかったのだが、印象に残ったのでずっと忘れないでいた。日替りの安いランチなんかを食べるときに、小さい皿(厨房では「ぺティ皿」などと和製仏語? を使ったりする)で出てくるサラダを注意して見るようになったものである。
しばらくすると、これがかなり確度の高い言葉だったことが理解されてきた。そこで関係者に、すこしずつ、遠回しにたずねてみて、根拠を探ってみることにした。あんまり直接に質問すると、テレがあるのか教えてもらえなかったりするからだ。そんな意見を寄せ集めると、だいたいこんなことになる。
「一番の下っ端にさせる仕事がきちんとできているかどうか。丁寧であるよりも手早く盛らないとサマにならないので、その店の能率もわかる。肝腎なのは、手を抜きやすいところで手を抜いていないこと」
もちろん異論も多いだろうし、これがいつでもどこでも正しいとも思わないが、素人目に見て手を抜いてもわからないところでも手を抜かないというのは、きっと職人仕事の真髄なのだろう。しかしファーストフードのチェーン店だって、(利用者から見て)これは無関係な話ではないと思う。
これと似た話に「索引を使ってみたらわかる」がある。これはじつは、古書の値踏みの秘訣である。
古書には相場というものがある。現在では、もうそんなものは崩壊してしまったが、かつては相場というものがあったのである。
「○○年発行の漱石全集箱付月報付全巻揃美本」でならいくら、といった類ものである。古書の世界で生きてゆくのには、これを知らなければならなかったわけだ。
しかし古書店の主にしても、得意と不得意はある。不得意の分野の本の値付けをしなくてはならない、そんな時、たとえば索引をチェックする。著者も編集者も書店もしっかり力を入れた本は、(もし索引があれば)きちんとした索引になっているはずだ。
最悪なのは、巻末にページが余ったので(最近の製本事情では、ほとんどこういうことは起こらないが)、そのページの分だけ索引にしました、という本。こういう場合は、必要な項目が確実に欠落している。安心して引けない索引は、見栄えのためだけのもので、罪悪ですらある。ない方がはるかにマシ。
翻訳書の場合、原書にはあった索引が省略されていることがじつに多い。しかし丁寧に索引を作成している翻訳書もなくはない。稀には、原書よりも精確な索引を作る例すらある。こういう場合、翻訳者(たいてい大学の先生)は、その本が長く使われるはずだし、そうあるべきだ、と判断したとみてよいのである。索引まで手を抜いていない本は立派である、ということ。
索引がなければ目次の出来を確かめること。またノンブル(ページ番号のこと)の見やすさなどもチェック項目に入れてよいだろう。
さて今回もまたまた現実離れした話題になったが、世の中偽装や手抜きが横行していて、それも大規模であったり組織的であったりで、鬱々としてしまうことが多い。そこで毒消しになるような記憶をたどってみたのが上記。
しかし厨房ばなしはともかく、古書のはなしは、すでに歴史的になってしまっていて、京都でも、新刊書店も古書店も、一軒、また一軒と閉店が続いている。
2015/11/05
若井 朝彦(書籍編集)