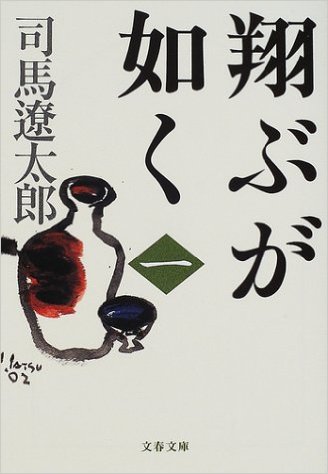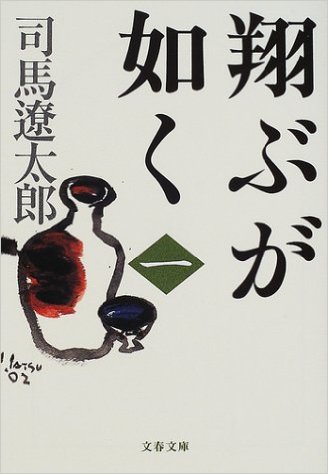
この本は大長編である上にドラマチックな小説ではないので、読みやすくはない。恐らく全編読み通した人は多くないのではないか。ただ史論或いは歴史随想風であるために情報量が豊富であり読み方によっては小説より楽しめる。司馬が西南戦争関係者の遺族から得た独自の資料も豊富に載っているので歴史学者も一読する価値がある。
いわゆる「征韓論」のこと
西郷が「征韓論」に固執したのは実は清朝の軍機大臣左宗棠(さそうとう)と連絡がありロシア南下の脅威に備えて満洲防衛のための共同行動を韓国に提案するためであった。そうであれば西郷が私学校党を組織し軍事訓練に励んだことと辻褄が合う。ただ日本が実際にロシアの脅威を痛感し戦端を開いたのはそれ(明治六年)から30年後の明治37年だ。当時にあっては西郷構想は空想的過ぎる。それより日本には優先すべき課題が山ほどあったはずだ。廃藩置県の仕上げ、税制整備、徴兵制、義務教育の普及、鉄道の敷設等。従って対ロシア日清韓提携論によっても西郷の「征韓論」が合理化されるわけではない。
尚仮に「征韓論」としたが厳密には「西郷遣韓大使論」と言うべきかもしれない。韓国と開戦すべきかどうかが閣議の議題になったわけではない。
台湾出兵
翌明治7年の大久保利通と西郷従道による台湾遠征は、「征韓論」の圧伏による鹿児島士族の不満をなだめるためであった。木戸孝允が「内治優先を理由に征韓論を退けながら台湾出兵を行うのは道理に合わない」として政府を辞めたのは無理からぬところだ。
台湾出兵問題を解決するために大久保自身が北京に乗り込み交渉に当たる。日本の主張は以下の通り。「沖縄の漂流民が台湾原住民に虐殺された。清国が台湾の領有権を主張するのであればこの事件に責任を負わなければならない」。この日本側主張に対し清国の対応は沖縄漁民が日本人であることつまり沖縄が日本領であることを前提としたものであった。これが明治12年日本政府による琉球処分つまり沖縄の正式領有につながる。これは清国外交の失態であり日本外交の成功であった。
西南戦争
西郷が下野した後の側近の中心は桐野利秋、篠原国幹等。西南戦争勃発直前西郷従道が兄隆盛を評して「兄が幕末あれだけの仕事ができたのは側に私や大山巌がいたからです。今兄の周りには碌なものがいません。だから大したことはできないでしょう」と。村田新八や永山弥一郎は西郷周辺では稀な人材であったが彼らの発言権は皆無であった。
西南戦争勃発時に西郷が陸軍大将の軍服を着たことの滑稽さ
確かに西郷は近衛都督と参議は辞任したがなぜか陸軍大将は辞めていない。陸軍大将の俸給も引き続き支払われている。西郷と完全に絶縁することをおそれた東京政府の配慮だ。だがこれは形式に過ぎず実質陸軍大将の仕事はせず毎日鹿児島で猟をして過ごした。それが突如陸軍大将を名乗り、熊本鎮台に対し「陸軍大将たる自分の指揮下に入れ」とはムシが良すぎる。
西南戦争に関する私の予てからの疑問はなぜあれほど薩摩軍鎮圧が長引いたかであったが、(反乱勃発から西郷の死まで7ヶ月以上かかっている)この本で疑問が解けた。陸軍トップの山県有朋は慎重な性格であった上に山城屋和助事件で窮地を救ってくれた西郷に深く恩義を感じていたので積極的な攻撃を手控えた。
一方八代方面から上陸し挟撃体制を整えた黒田清隆は西郷軍と内通してわざと脱出の時間を与えた。確かな資料はないが情況からそうとしか考えられない。西郷を思慕していた黒田は自分が西郷を捕える先に自刃してほしいと願っていたことだろう。
西南戦争は、熊本城攻防戦とその近郊の戦いで薩摩軍が敗れた時実質終わっている。
「雨は降る降る陣馬は濡れる、越すに越されぬ田原坂」の歌は薩摩軍側の立場から見た場景であると思い込んでいたが実はこれは政府軍側から見た場景とわかった。
田原坂はもっと福岡県境に近い位置にあると思い込んでいたが、地図で確認したところ熊本城からさほど遠くない位置関係にあるとわかった。 薩摩軍は東京まで行くつもりだったが熊本城のちょっと先までしか行けなかったことになる。
西南戦争に登場する軍人は、何せ国軍ができたばかりであり中将の山県有朋、大山巌を除き当時の階級は必ずしも高くなかったが、その後日清日露戦争で中心的役割を果たす軍人を網羅している。
青木亮
英語中国語翻訳者