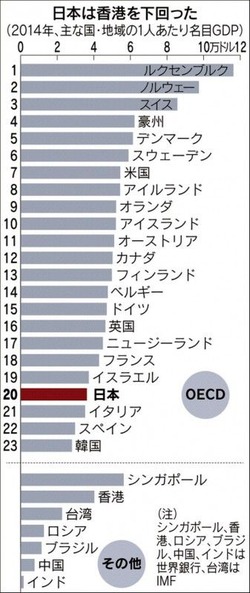英国のエリザベス女王が25日、恒例のクリスマス・スピーチの中で、「世界は今年、暗闇に直面せざるを得なかった」と語ったという。女王は、1月と11月、フランスで生じたテロ事件を想起しながら、「暗闇」と表現されたのかもしれない。イスラム教過激派テロ組織の蛮行の犠牲者にとっては限りなく悲しみであったことは確かだが、それが即、「暗闇」に該当するかは分からない。
明らかな点は女王が、「光は暗闇の中に輝いている。そして、暗闇は勝たなかった」(「ヨハネによる福音書」第1章)という新約聖書の聖句を引用されていることから、女王が指摘された「暗闇」はテロ事件に限定された現象を意味するのではなく、もっと広義的な社会現象が含まれていたと受け取るべきだろう。
聖書学的な終末論をここで振り回すつもりはないが、21世紀を生きているわたしたちが一種の行き詰まりに直面していることは確かだろう。今年は宇宙物理学の驚くべきニュースに多く接する度、地球に生きている私たち自身の成長が余りにも遅々たるものであるといった実感から逃れられない。宇宙の神秘が次第に私たちに披露され出しているのに、私たちは、自分の中で、家族の間で、そして社会、国家の間で、平和な時よりもいがみ合い、紛争、戦いを多く目撃している。そのコントラスにやり切れない思いが湧いてくる。
私たちは何か忘れてきたのかもしれない。科学技術の急速な発展の一方、人権と自由は次第に拡大し、多くの人はそれらを享受し、謳歌できる時代圏に入っていることは間違いない。それらの発展で私たちが幸せを感じ、互いに尊敬を払う社会となったのならばいいが、現実は「貧富の格差」は広がる一方、物質消費社会が席巻する中で心は砂漠のように飢え乾いた現代人が少なくない。諦観と失望が広がり、希望と喜びは遠ざかっていったような気持ちがする。科学の目覚ましい発展に眼を眩まされて何かを見逃してきたのかもしれない。
ひょっとしたら、エリザベス女王の「暗闇」はキリスト教社会の欧州に当てはまるが、アジア、南米、アフリカなど地球の他の地域には当てはまらないかもしれない。明確な点は、欧州社会は確かに暗闇に直面していることだ。
近代史を引っ張ってきた欧州社会が今、そのキリスト教価値観、世界観と共に落日を迎えている。欧州社会は息切れしてきているのだ。クリスマスは到来し、プレゼント交換が終わると過ぎ去っていく。「なぜイエスは十字架で亡くならざるを得なかったか」と真剣に問いかける人は誰もいない。
例えば、ドイツでは教会葬式を願う国民が急減してきたという。死んだ後、復活するという教会の教義をもはや信じられなくなったから、教会で埋葬される意味を感じなくなった結果だ。
冷戦時代、共産主義政権が崩壊すれば、世界は良くなるだろうと漠然と信じてきた。希望もあった。しかし、共産政権が崩壊し、本来ならば勝利の盃をかわすべき資本主義社会で貧富の格差は拡大し、社会システムは、少子化、年金体制の崩壊、健康問題など大きな時限爆弾を抱え、限界にきているのだ。
ここまで書いていくと、エリザベス女王のスピーチの「暗闇」という表現が本当に正しい選択だといわざるを得ない。しかし、その「暗闇」は過去形ではなく、現在進行形だというべきだろう。
オスカー・ワイルドは、「楽天主義は不安の裏返しだ」と述べている。不安だから、楽観的に生きざるを得ないという「必要は発明の母」的な生き方だ。現実の多くの楽観主義者はそうかもしれない。
エリザベス女王は、「光は暗闇の中に輝いている」という聖句を引用し、希望と歓喜の世界への信頼を失っていない。「不安」からではなく、「希望」と「歓喜」に支えられた楽観主義者を目撃したならば、その人からその秘密を学びたいものだ。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2015年12月28日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。