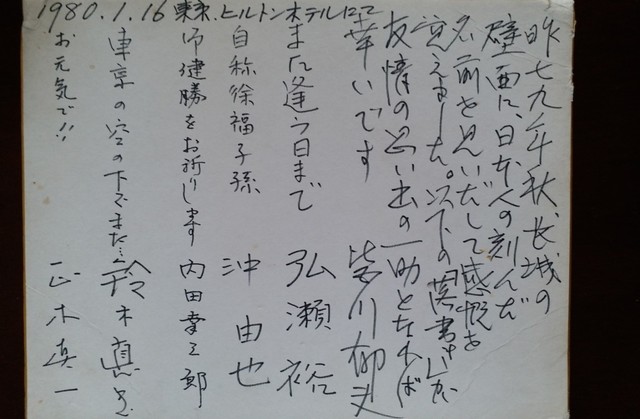民法では、夫が亡くなった場合その妻は遺産の2分の1を相続し、残りの2分の1は子どもが相続することになる。分かりやすく数字で示すと、遺産のうち預貯金が2000万円で自宅の土地建物の評価が3000万円であるとした場合、それぞれが相続する額は妻が2500万円、子どもが2500万円となる。このような場合、様々な理由から子どもが遺産を現金で求めることもあり、その現金を捻出するために自宅の売却を余儀なくされるケースもある。
また、預貯金額が3000万円で自宅土地建物の評価が2000万円である様な場合では、妻が自宅に住み続ける為その土地建物を単独で相続すると、遺産として受け取れる現金は500万円となりその後の生活が苦しくなるということも起こりうる。(※上記の例は遺産分割について遺言がなく配偶者と子どもで分ける場合。ただし要旨を明確にするためここでは基礎控除等や評価減の特例等は考慮しない)
厚労省が行った調査によると2016年の日本人の平均寿命は男性80.98歳、女性87.14歳であり、ここから見ても妻よりも夫が先に亡くなる場合が多いことが窺える。
政府は、残された配偶者が他の相続人の遺産取り分を捻出する為に住居を失ったり、相続後の生活が困窮したりすることを解消するための仕組み作りを始めた。
法務省によると、法制審議会(民法部会)は、1月16日開催の第26回会議において「民法(相続関係)等の改正に関する要項案」をまとめ、政府は今年の国会に改正法案を提出する。※詳細は法務省HP参照
この要綱案のいくつかの新制度のうち注目すべきは「配偶者居住権」の新設である。この居住権は相続人である配偶者が、遺産分割が終わるまでこれまでの住居に無償で住める「短期居住権」と、住居の所有権を他の相続人など配偶者以外が持っても、配偶者が終身又は期間を定めて居住できる「長期居住権」の2種類になるのだが、いずれも配偶者が相続によって「住居」を失わないようにするためのものである。
しかし、こういった施策に取り組む一方で、社会全体が「相続と相続税」の本質を考えることも重要である。国税庁が所管する税務大学校が作成している「税大講本」によると、そもそも相続税とは、所得税の補完機能(被相続人が生前において受けた社会及び経済上の要請に基づく税制上の特典、その他による負担の軽減などにより蓄積した財産を相続開始の時点で清算する機能)と、富の集中抑制機能(相続により相続人等が得た偶然の富の増加に対し、その一部を税として徴収することで、相続した者としなかった者との間の財産保有状況の均衡を図り、併せて富の過度の集中を抑制する)という機能を持つとされている。※詳細は国税庁HP参照
実は現行税法においても相続税には自宅の土地について「評価の特例」が設けられている。これは被相続人と同居していた配偶者や子どもがその土地を相続した場合、土地の330㎡までは、課税の対象とする土地の評価額を8割減にする(※建物については固定資産税評価額と同じ)というものだ。そして、配偶者が土地を相続する場合はこの特例は無条件で認められているのである。当然この特例の意図も先述の配偶者居住権新設の趣旨と同様、「配偶者が相続によって住居を失わないようにするため」のものだ。
また、相続税には基礎控除があり、その額は「3,000万円+法定相続人1名に対して600万円」である。例えば、配偶者と子ども2人の場合は、3,000万円+1,800万円(600万円×法定相続人3名)となり、基礎控除額は4,800万円となる。これらを踏まえて、本稿冒頭の「現行の民法では…」の段を見直してほしい。ここで示した例においても現行制度では「相続税が課税されない」場合もあるのである。
さらに「そもそも」本稿冒頭で述べた民法で定めた法定相続分、いわゆる遺産の分け方については、遺言が存在しない場合、相続人全員が遺産分割協議に参加しその全員が合意すれば、遺産の分け方は法定相続分の割合に縛られなくとも良い(民法907条1項)のである。つまり相続人である配偶者が住居を失ったり相続後の生活に困窮を回避できる最初の機会は、相続人全員の遺産分割協議にあるといってもいい。
このように相続や相続税が持つ社会的意義を考えた場合、現行の民法でも相続人全員の合意があればその相続分を自由に決めることができ、税法でも一定の相続税の負担軽減を規定しているにもかかわらず、政府が相続部門の民法改正に踏み込むのは、これまでも遺産分割協議がうまくいかないケースが多く、高齢者の住居喪失や生活困窮が今後さらに拡大していくことを想定してのことだろう。しかし、所有権を制限するともいえる居住権を新設すること、そしてその居住権によってもたらされる居住財産の課税評価額減に関しては、その必要性と公平性を含め今後も国会等でさらに議論を深めていくべきではないだろうか。
ひとつだけ間違いないのは、この相続新制度にかかわらず、「高齢化社会」とは民法のあり方をも変えてしまう、いや、変えなければ対応できない程の過酷な社会なのだということだろう。