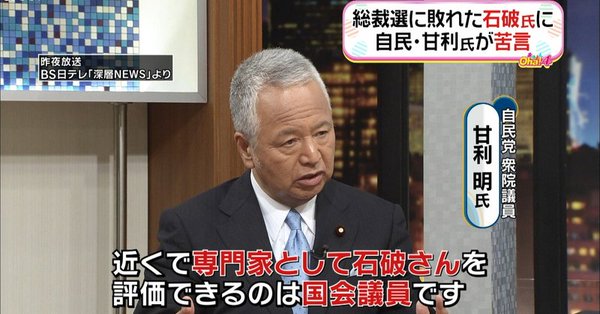ナショナリズム台頭の根は深い
トランプ大統領は、「なぜ米国民の税金で日本を含めた他国の防衛や世界の秩序の維持をしなければいけないのか」と、いわゆるモンロー主義、パックスアメリカーナの放棄を主張している。欧州に目を転じると、英国はEUからの離脱を決め、ドイツですら移民排斥派が興隆している。
こうした欧米で巻き起こるナショナリズムの動きは、ある意味で正論であるし、短期的には国益に資するであろう。しかし、長期的には彼らの首を絞めかねない自殺行為になるリスクを孕んでいると彼らは自覚しているのだろうか。

Gage Skidmore/flickr:編集部
資本主義と立憲民主主義の本質
そのリスクとはこういうことだ。1640年の英国清教徒革命に始まり、フランス革命、アメリカ独立革命、(あるいは明治維新もそこに含まれるかもしれない)などの一連の「市民革命」と、1760年に始まった「産業革命」によって欧米文明が創作した大きな物語である、「自由・博愛・平等」のキリスト教の根底原理の上にある「資本主義」と「立憲民主主義」の崩壊の引き金を引きかねないということだ。
Wikipediaの市民革命の定義を抜粋・引用する。
「市民革命(資本主義革命、民主主義革命)とは、封建的・絶対主義的国家体制を解体して、近代的市民社会をめざす革命を指す歴史用語である。一般的に、啓蒙思想に基づく、人権、政治参加権あるいは経済的自由権を主張した「市民(ブルジョワ)」が主体となって推し進めた革命と定義される。
この「市民」には、封建・絶対主義から解放され、自立した個人という意味および商人・資本家という意味を持っているため、市民革命の定義も二義性を持つ。一方で、この二義性は表裏一体をなす。すなわち、革命をなすための市民社会の形成には資本主義の発達が不可欠であり、私的所有の絶対を原則とする資本主義社会の成立が必要だったのである。
この、キリスト教的価値観の上に載った「立憲民主主義」と「資本主義」という2つの「壮大な物語」(あるいは「決め事、あるいはゲームのルール」)は過去300年に亘って世界の経済発展の大変大きく貢献した。蒸気機関の発明、電気の発明は生産性を飛躍的に向上させ、ブルジョアから中流社会の出現、所得の向上は有効需要を創出して、世界は大いに物を作り、消費し、それが利潤を産み、また作る、そのようにして好循環が発生した。
パックスブリタニカ・パックスアメリカーナの成功を見て、キリスト教を原理としない国々もこの物語を無謬的に受け入れていった。それは第一次世界大戦、第二次世界大戦、そして戦後の国連とブレトンウッズ体制で強固なものになる。イスラム諸国では「利子」という概念は禁止されていたが、利子なしに資本主義は廻らないので色々妥協をして資本主義経済に取り込まれていった。江戸時代まで鎖国を貫いた日本は、明治維新でその仕組みを器用に内部化し、現在の繁栄に至る。
この壮大な物語は、ベルリンの壁が崩壊する1990年までの約300年間は頗る順調に機能した。それは、経済が概ね各国の中で閉じていたからだ。もちろん、自由貿易はあり富める国とそうでない国の差は明確にあった。(日本は非キリスト教国でこの物語の恩恵を最も受けた。)
それに、国の中で貧富の差はあったから、「投票権は一人一票」という「資本主義」と「民主主義」が喧嘩をすることもあったがなんとか折り合いをつけていた。国家が転覆するまでの一大事には至ったのはソ連・東欧・中国・北朝鮮などで、こうした革命を成就してしまった国に比べて、明らかに西側の旗色が良かった。西側諸国も、なんだかんだ言って、完全なる競争主義政策を取らず、国の中で所得の再分配機能がそれなりに機能していたので、貧しい人々も「自分のもらいは少ないが、貧困国にいるよりはマシだ」と納得していた。
グローバリズムの影響
ところがこの20年間でグローバリズムの台頭という化け物が大暴れし始めた。それは、IT革命と金融の自由化、そして中国鄧小平の政策変換によって巻き起された。一言で言えば、「ヒト・モノ・カネ」が国境を越えて世界を自由に飛び回る世界だ。
その結果、米国の「ラストベルト」に象徴されるように先進国の中流が没落し、中国や東南アジアなどの新興国に億万長者が数億人も誕生した。貧しき国から先進国に移民・難民が流入し、「先住民」の職を奪った。グローバリズムの経済的本質は、「西側諸国」に押し留められた生産・消費市場の、中国など「東側諸国」への拡大であり、安い人件費のフロンティアを求めるグローバル企業が牽引したバングラデシュなど「南北問題で固定化され続けた南側諸国」への拡大である。
ここにきて、欧米において「資本主義」と「民主主義」が喧嘩を始める。没落民がマジョリティを占め、所得の再分配が機能不全を起こす。民主主義は国民国家ネーションという「ルール」と国の中で閉じていて「富める者でも貧しき者でも法の下では平等に一人一票の投票権」いうルールは変わらないから、国政選挙で「民主主義が資本主義を否定する」という合法的クーデターが起きる。私のいうクーデターとは、「世界の富の拡大という全体最適」に対する「国民の「エゴ」による部分最適」の反乱であり、それは結果として、その国民を苦しめるという経済学用語でいう「囚人のジレンマ」である。
「アメリカアズファースト」を掲げるトランプは現代版のジャンヌダルクだ。名もなき無数のラストベルトで現状に不安を持つ多くの「市民」の代弁者だ。粗野で下品な振る舞いをする「大統領の品格」にかけるトランプはなかなか特異なキャラクターであるが、彼が大統領になったのは決して偶然ではなく歴史の必然だ。これから、ますます「資本主義」と「民主主義」の仲違いは深刻化し、その壮大な物語の崩壊の可能性すらある。
非西洋的価値観興隆の予兆
さて、その物語の崩壊への影響は欧米と日本も含めた欧米以外の国々で全く異なる。これが僕の言いたいことだ。
こういう言い方は失礼かもしれないが、欧米はまだいい。資本主義と民主主義という二階部分が仮に壊れても、基礎をなすキリスト教的思想は厳然と残るだろうからだ。だから、新しい物語を再構築するにしても比較的マイナーなアップデートですむはずだ。しかし、非キリスト教国では異なるだろう。イスラム教国やヒンズー教が主流のインド、そして宗教を持たない中国では、この物語崩壊からの再構築は抜本的なものになるだろう。
それは、日本においても同じだ。西洋思想と東洋思想の「文明の衝突」の予感がする。
吉田拓郎とビートルズ
僕が生まれたのは、1963年で、ゲバ棒を持って暴れまくった全共闘世代より10年くらい下になる。幼稚園や小学校低学年時代にで起きていたベトナム戦争はほとんど記憶にない。当時はノンポリの「シラケ世代」と呼ばれた。実際僕は白けていた。
小学校5年で泉谷しげるの春夏秋冬という厭世的な曲を聴いていた。相当ませた、あるいはシニカルな子供だった。僕には2歳上の兄がいて、彼は吉田拓郎の大ファンであり、おかげで連日居間にあった新品のシャープのステレオで吉田拓郎の歌を繰り返し聞かされることになった。結果、吉田拓郎の歌はほとんど諳んじて歌えるようになった。
最近になって、ある興味深いことに気づいた。吉田拓郎作詞作曲で「イメージの詩」という歌がある。一方で、兄はビートルズ・ポールマッカートニー作詞作曲の「Let it Be」という歌もよく聴いていた。先ほど調べてわかったのだけれど、どちらも1970年つまり僕が7歳の時にリリースされている。「Let it Be」は3月に発表され、「イメージの詩」は6月に発表されている。吉田拓郎は「Let it Be」を知らずに「イメージの詩」を作ったのかもしれないし、あるいは知っていて作ったのかもしれない。まあそんなことはどうでもいい。

僕が言いたいのはこういうことだ。両方とも名曲で僕の心を打つのだけれど、発しているメッセージが(あくまでも僕の主観的解釈だが)真逆であり、それこそが西洋思想と東洋思想の「違い」を表している。
「Let it Be」を直訳すれば「それは、それのままにしておけ」ということだ。この歌をベトナム戦争や高度資本主義経済、あるいは反戦闘争に対するアンチテーゼだと僕は解釈する。「何かの固定観念(例えば戦争を生み出してしまう高度資本主義経済の是非を巡る激論)を捨てて、ありのままに生きていこう。」さらに言えば、「自然に帰ろう」。こういったメッセージに感応して米国西海岸で、アンチ東海岸の文化や社会風俗が成熟していったことは間違いないだろう。
一方「イメージの詩」で吉田拓郎はこういう趣旨のことを歌っている。「誰かが、「僕は人間として自然に生きている」といっていたが、自然に生きているということを自覚できるなんてとても不自然だと僕は思う」。僕は、こう解釈する。「人間はそもそも主体ではなく、自然という主体の一部の客体であって、自覚的に自然に生きるという考え方は矛盾している。」
これは僕の偏見かもしれないが、「Let it Be」は命令形であるから、その主語は「自分」という「主体」あるいは「キリスト教という絶対神の下で生誕した主体としての僕」なのではないだろうか。つまり、ポールマッカートニーは、資本主義は否定しても基礎部分のキリスト教「すなわち神(あるいは神の子である僕)が自然を支配する」という原理は否定してないのではないだろうか。そうでないとアナーキズムになってしまう。
立憲民主主義のもろさ
トランプがアジアから手を引いて安全保障は勝手にアジアでやってくれというのはある意味で筋が通った主張だ。そして、そうであるならば、アジア(日本・東洋)はもはや、キリスト教的価値観の上に載った「立憲民主主義」と「資本主義」に拘泥される筋合いはないという主張はあながち真っ当でないとも言い切れないのではないだろうか?
日本には、「和をもって尊しとなす」という聖徳太子以来の統治秩序がある。勘違いしないで欲しいのだが、僕はいわゆる右翼でも左翼でもない。政治的イデオロギーは持たない。だから「民主主義を否定しよう」とか「ナショナリズムを高揚させよう」という気持ちはさらさらない。むしろ、この秩序が崩壊しかかっていくことで、厄介なことになったなと思っている。できれば現状維持がいい。外交でも政治でも経済でも文化でも。
それでも、僕は一人の人間として、昔からキリスト教的価値観における「市民」や「人権」、あるいは「憲法」というものに対してなにがしかの違和感を子供の頃からもっていたことを白状する。小学生の時に社会科で教わった「基本的人権」だが、「でもなんで犬には犬権がなくて人だけ特別な存在で人権が認められないのだろう?」「虫は殺してもいいのになんで人は殺していけないのだろう」と当時思っていた。近年「世界の終わり」という若者たちも同様の趣旨の歌を歌って人気を博してる。
憲法改正論議の虚しさ
高校の倫理で教師からいわゆる社会契約論というものを教わったが、大きな違和感を覚えた。なんとなく、誰か他の人間の靴をはかされたような違和感だ。契約というのは、相手があって初めて成り立つ。でも、その相手が自分とは違う前提条件を持っていたらそもそも契約などは成り立たないだろうと考えていた。だから、日本国憲法というものにも違和感を覚えた。それは、お仕着せの憲法制定の経緯とか、9条是非論とかそういうことではなくて、「だってそれって決めの問題であって、自分ないし多くの人たちが「やめた」といえば無効になる「契約」に普通の法律と「特別の違い」を見出すのはなかなか厳しいからだ。でも大学受験のために、「自我」は捨てて社会契約論に従って今まであまり深く考えずに生きてきた。
だから、今の日本国憲法改正の議論からは比較的距離を置いて、生暖かく観察している。もちろん自衛隊について思うとことはあるが、それをいうとイデオロギーの罠に入り込むので、あえてここで私見は述べない。
でも、今振り返って思うと、そういう「市民」や「西洋的秩序」というのは基本的に性悪説あるいはディストラストに立っているからこそ必要なものだと思う。人の「エゴ」や国家の「エゴ」は時として他人や他国を無情にも苦しめる。だから、それを回避するために「ネガティヴリスト」を設けて「あれはやってはいけない。これを誰かにやられない権利がある」というルールでお互いを牽制しあうわけだ。
ところが「東洋的秩序」あるいは「日本的秩序」は、「情けは人のためならず」「お互い様」「近江商人の三方よし」というあうんの呼吸、性善説あるいはトラストに立っているのではないだろうか。その根底原理は、「人間は主体ではなく自然という大いなるものの客体である」ということだ。
そう暗くない日本の未来
長くなったので今日はこのくらいで筆を止めるが、日本や世界は今、新しい社会・経済秩序の再構築を求められている。そしてそれは決して悪い話ばかりではなく、少子高齢化・人口減少社会とAIやIoT化の中で、シェアリングエコノミーという貨幣経済やディストラストを超克した仕組みが少なくとも良い意味でのガラパゴス日本で実現できるのではないかというのが僕の予感だ。うまくするとそれを世界に向けて発信できるかもしれない。だから、僕は昨年株式会社電力シェアリングというベンチャーを立ち上げブロックチェーンを活用したスマートコントラクトにより、「助け合い社会」モデルの実現を進めている。
その過程で3ヶ月前に秋葉原のオフィスでお目にかかった、研究者・メディアアーティストの落合陽一さんの最新刊『デジタルネイチャー 生態系を為す汎神化された計算機による侘と寂』。を昨日から読み始めたが、おそらく僕と比較的類似した考えなのではないかと思うので楽しみにしている。