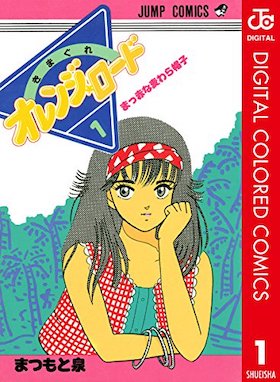秘書としてフルタイムのアルバイトを長年続けていた方の賞与支給を争った最高裁で支給の要なしと判決、また東京メトロの売店の契約社員で10年働いた方の退職金支給も要なしと判断されました。

(写真AC:編集部)
悩ましいところだと思います。
これが10-20年前ならあまり悩まなかったかもしれません。しかし、今の働き方改革と雇用形態の多様化を考えると一義的ではないような気もします。
この裁判の話題を聞いたときはごく一般的にアルバイト、非正規社員と正社員の業務内容に対する差という観点から賞与、退職金支給は難しいだろうと考えておりました。特に正社員は転勤や部署替えを厭わず、それが頻繁にある中で会社との忠義関係にある「メンバーシップ型採用」である点が大きいわけです。
私がゼネコンに入社した時、ある誓約書を書かされました。「海外勤務を厭わず」であります。これは入社した全員が署名させられました。そんな昔話ながら当時やや無理強い感があるなと思ったのは入社に至る面接で「海外勤務はどうですか?」と聞かれ「はい」と答えざるを得ない状況、つまり不平等な立場に置かれ言わされ感が強かったからです。内定が出るときにはそれが前提になっているとは知らされていないわけです。4月に入社してからしょっぱなに「これに署名を」というのは今の契約社会では受け入れられません。当然、内定の条件書にそれを謳うべきでした。
メンバーシップ制度の雇用関係はそんな無理強いをする会社へのコミットメントであるため、アルバイトさんと賃金的差額があるのはやむを得なかったのです。今でも覚えているのですが、2000年頃、親会社の経営が悪く賞与も減る一方で労働時間が異様に増えたことがあります。通常業務の上に銀行向けの資料作成と質疑応答であります。残業時間で換算すれば月150-200時間ぐらいは普通にあったと思います。そんな頃、皆で冗談交じりで話したのが「俺たちの労働時間当たりの給与は時給千数百円ぐらいかね?これじゃアルバイトと変わらないな」であります。
もう一つ、日本独特の賞与の発想について最高裁では触れていないと思いますが、ここにもからくりがあると思います。そもそも日本の給与制度は年間を12カ月で割るのではなく、14カ月で割る仕組みでした。賞与という発想ができたのは日本に盆暮のつけ届けという入用の時期があるため、夏と冬に給与と同額程度を支給できるように年収を14で割って計算し始めたのがオリジナルです。
つまり、賞与がいかにも正社員の既得権のように言われていますが、実はそうではありませんでした。ただ、この半世紀以上は実質的には経営側が業績見合いで増減させたり、個人査定を反映させたりしています。よって賞与という発想そのものが変質化していることは否めません。それなのに最も保守的であるべき住宅ローンで賞与月に増額返済などという仕組みだけは残っているのはやや時代錯誤感が無きにしも非ずであります。
ここまで書くと経営側の言い分に味方しているように思われるでしょう。そうではなく、私は働き方が変わってきた中で今回の問題は賞与と退職金そのもののあり方が問われているのだろうと思います。つまり、正社員であってもそれを無くし、代わりに月々の給与を増やす方が優れているのではないかと思うのです。メンバーシップ制度を継続するなら従業員にストックオプションをつける方がましであります。
海外では日本型の賞与も退職金もありません。クリスマスの時に一人1万-数万円程度を配るところもありますが、これはあくまでも一種の「餅代」であります。賞与はジョブ型契約において年間目標値を設定し、そこに達成したらいくらのボーナスがもらえるという方式です。私の会社でも10数年前から導入しており、一年に一度その配分があります。
賞与とは読んで字のごとし「功に対して褒美を与える」わけですが、「功」を測定する手段を持たない場合、会社全体の業績に依存するしかありません。秘書にしろ駅の売店の売り子さんにしろその功を決める約束事が事前になければ支払いようがないわけです。それはメンバーシップ型の一般正社員でも同じでそれゆえに株式でも分け与えるしかないというのが私の考えなのです。
同一労働同一賃金という発想は結構なのですが、これは経営的には成長のきっかけがつかめなくなる恐れがあります。どうやったら同一の枠組みから外れるか、その仕組みを雇用者側が提供しない限り延々と同じレベルの仕事しかしないというジレンマに陥るとみており、雇用側がどうインセンティブを出すか知恵の出しどころだと考えております。
私は賞与、退職金を含めた報酬、更には通勤費などの各種手当や賃金体系など雇用形態の多様化と共に抜本的見直しが必要になってきているのではないかと考えております。
では今日はこのぐらいで。
編集部より:この記事は岡本裕明氏のブログ「外から見る日本、見られる日本人」2020年10月14日の記事より転載させていただきました。