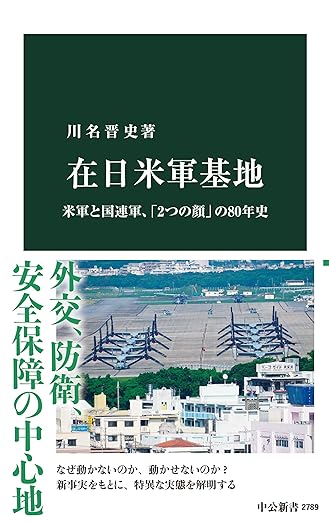sunrising4725/iStock
先日、『在日米軍基地 米軍と国連軍、「2つの顔」の80年史』(中公新書)と題した新刊が発売された。月刊「正論」の書評連載欄で取り上げようとも考えたが、すでに4月号(3月発売号)分まで入稿していることもあり(コルビー著『拒否戦略』日本経済新聞出版)、この場を借りて紹介させていただきたい。
表紙カバーに巻かれた帯ネームはこう謳う。
世界で最も多くの米軍基地を抱え、米兵が駐留する日本。米軍のみならず、終戦後一貫して友軍の「国連軍」も駐留する。なぜ、いつから基地大国になったのか。米軍の裏の顔である国連軍とは。本書は新発見の史料をふまえ、占領期から朝鮮戦争、安保改定、沖縄返還、冷戦終結、現代の普天間移設問題まで、基地と日米関係の軌跡を追う。「日本は基地を提供し、米国は防衛する」という通説を覆し、特異な実態を解明。戦後史を描き直す。
本書の中心的な命題は「はじめに」書かれている。冒頭こう書き出す。
日本にいる米軍は二つの顔をもっている。「表」の顔である在日米軍としての米軍と、「裏」の顔である国連軍としての米軍である。前者はよく知られているが、後者についてはほとんど知られていない。どちらも見た目には違いはないが、中身は大きく異なっている。日本にいる米軍は必要に応じて、この二つの顔を使い分けることができる。
失礼ながら大半の読者も、「裏」の顔はご存知あるまい。本書は続けてこう指摘する。
国連軍としての米軍には、たんなる在日米軍にはない様々な特権がある。最大の特権は、米軍以外の国連軍、すなわち友軍に在日米軍基地を「又貸し」できることである。その際、日本側の同意を得る必要はない。又貸しされる基地は、在日米軍基地であると同時に、国連軍後方基地とよばれる。現在、それは日本に7ヵ所ある。本土に4ヵ所(横田、座間、横須賀、佐世保)、沖縄に3ヵ所(嘉手納、普天間、ホワイトビーチ)である。2023年現在、日本にある後方司令部(横田)には豪軍出身の司令官ほか3名が常駐し、豪州、英国、カナダ、フランス、イタリア、トルコ、ニュージランド、フィリピン、タイの9カ国の連絡将校が在京各国大使館に勤務しているとされる。
国連の旗を掲げる限り、米軍を含めた国連軍は基地での行動について事実上、日本の同意を得る必要はない。(中略)それは米国にとって事実上、彼らが戦後一貫して求めてきた基地の「自由使用」であり、日米安保条約が掲げる事前協議制の抜け穴だからである。米国は国連軍をその「隠れ蓑(cloak)」とみなしている。
ここでは、上記の中に「普天間」がある点にも注目したい。
本書第6章「普天間と辺野古――二つの仮説」は、「普天間の返還・移転に関しては、日米の二国間協議だけでなく、国連軍の他の参加国との協議も必要だ」、「しかし、普天間移設の問題を論じる際に、メディア等でこの点が議論されることはない」と指摘した上で、かつて「鳩山政権下で生じた普天間移設、とりわけ国外移設政策が頓挫した原因は、根本的には普天間が国連軍基地の地位にあることにある」と総括している。
公正を期すため書けば、異論を覚えた箇所もある。本書は、「台湾海峡で紛争が生じた場合に、米軍が戦闘作戦行動をとろうとし、事前協議において日本側がそれを拒否するという事態」を「現実的ではない」とし、「日本がこの場合の事前協議において同意しないという事態は想定しにくい」と切り捨てているが、それでは重要な論点が雲散霧消してしまう。
なお、この論点については拙著最新刊『台湾有事の衝撃 そのとき日本の「戦後」が終わる』(秀和システム)で、一章を割いて詳論したので、拙著に委ねる。いずれにせよ、在日米軍基地が持つ「裏」の顔に光を当てた本書の価値は、いささかも揺るがない。
最後に、本書終章「二つの顔」を借りよう。
それでもまだ米軍については国民やメディアの側に一定のリテラシーがあるからよいようなものだが、国連軍についてはそれすらない。監視の目は届いていない。そもそも、日本は個別の参加国に対して撤退交渉を行う立場にすらない。彼らの駐留は国連安保理決議に基づくものだからだ。これは日本の国家主権に干渉しうる重大な問題をはらんでいる。
著者は川名晋史教授(東京工業大学リベラルアーツ研究教育院)。聞けば、小泉悠准教授(東京大学)とかつて国立国会図書館職員として、ともに働いた同僚らしい。ご両人とも、ますますの活躍が期待される。
基地問題に関する立場を問わず、本書を強く推す。
■