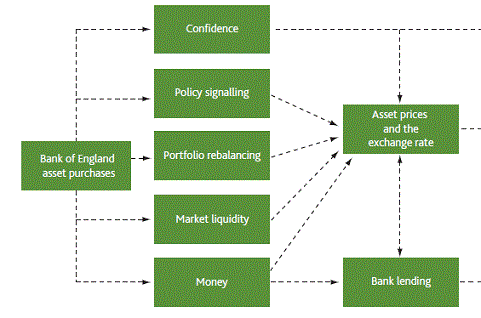前の記事では、日米の非伝統的金融政策について述べたが、黒田新体制の下で日本銀行が新たに行おうとしている金融緩和は、むしろ英国で実施されているものと類似性が高いものになるのではないかと思われる。そこで、英国の経験についても少し整理しておきたい。英国の中央銀行であるイングランド銀行は、前回述べた米国連邦準備とは異なって、その政策を自ら「量的緩和(Quantitative Easing)」と呼んでいる。
リーマンショック以後、英国でも金融緩和が進められてきたが、2009年3月に、政策金利を0.5%まで低下させたところで、実務上はこれ以上政策金利を下げることはできないとして、同時に「量的緩和のための資産買い取りプログラム(Quantitative Easing Asset Purchase Programme)」を開始することが決定された。その内容は、2009年の3月から11月の間に総額2000億ポンドの資産(対象となる資産はもっぱら英国国債)を購入するというものであった。
それにしても、0.5%というと、日本の感覚からするとまだ金利を低下させる余地があるように思われるが、シティの市場機能を維持するためには、それ以上の引き下げは好ましくないという判断になったものとみられる。その後、買い入れ額は順次増加されられていき、現在は3750億ポンドにまで拡大している。
当初は、この資産買い入れによって、ベースマネーを経済に注入すれば、マネーストックが増大し、名目需要の拡大がもたらされると説明されていたが、残念ながら、そうした事態は起こらなかった。すなわち、ベースマネーは増加しても、英国のマネーストックは伸び悩んだままである。それどころか、直近の広義貨幣量(M4)の伸び率はマイナスが続いている(小口の預金や現金は伸びているが、法人預金が急激に減少しているため)。
要するに、実質的なゼロ金利制約下では、機械的な貨幣乗数メカニズムは作用しない。それゆえ、最近では量的緩和の効果に関するイングランド銀行の説明は、やや変更されており、もっぱら資産価格と為替レートへの影響、および期待へのより広い効果を通じて、効果をもつとされている。決定的な伝播経路があるわけではないが、様々な経路を通じて効くはずだという話である。そのために、伝播経路の説明は、以下の図のようにかなり複雑である。
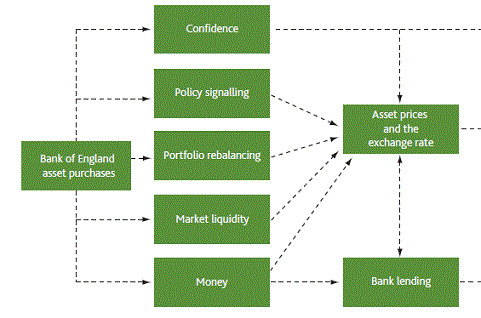
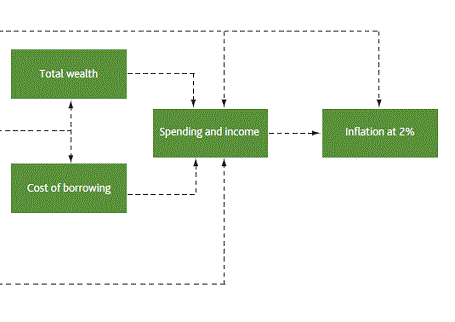
イングランド銀行は「効果の定量的な大きさには無視できない不確実性(considerable uncertainty about the magnitudes)があるものの、量的緩和には経済的に意味のある効果はあった(QE asset purchases have had economically significant effects)」という見解であるけれども、それでは実績はどうだろうか。
インフレ率は、この数年間、目標である2%を上回った状態が継続している(11年頃の4%超えには、付加価値税の引き上げの影響が含まれている)。英国は、明示的にインフレーション・ターゲットを導入している国であるけれども、インフレ目標の設定だけはインフレ率高進の決定的な歯止めにはならないという実例になっている。
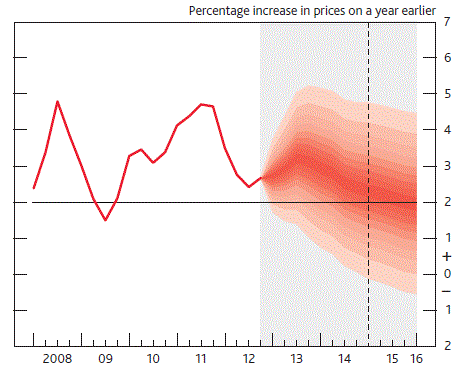
なぜ、実際のインフレ率がインフレ目標を上回っているのに金融引き締めを行わないのかというと、話は簡単で、景気が悪いからである。足下では、英国の実質経済成長率は、ゼロあるいは若干のマイナスといった事態になっている。すなわち、英国はスタグフレーション(不況とインフレの共存)に近い状態になっているといえる。インフレも、貨幣数量説的なメカニズムが働いた結果というよりも、コスト・プッシュによる面が大きいとみられる。
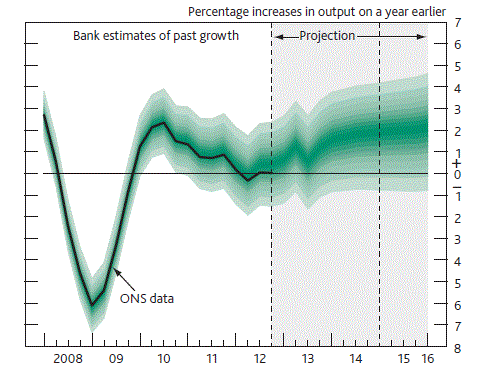
上の2つの図は、イングランド銀行の最新の「インフレーション・レポート」からとった。予想の部分は、扇状図(fan chart)といって確率分布を示すかたちになっている。色の濃い(薄い)ところほど、起こる確率が大きい(小さい)ということである。
--
池尾 和人@kazikeo