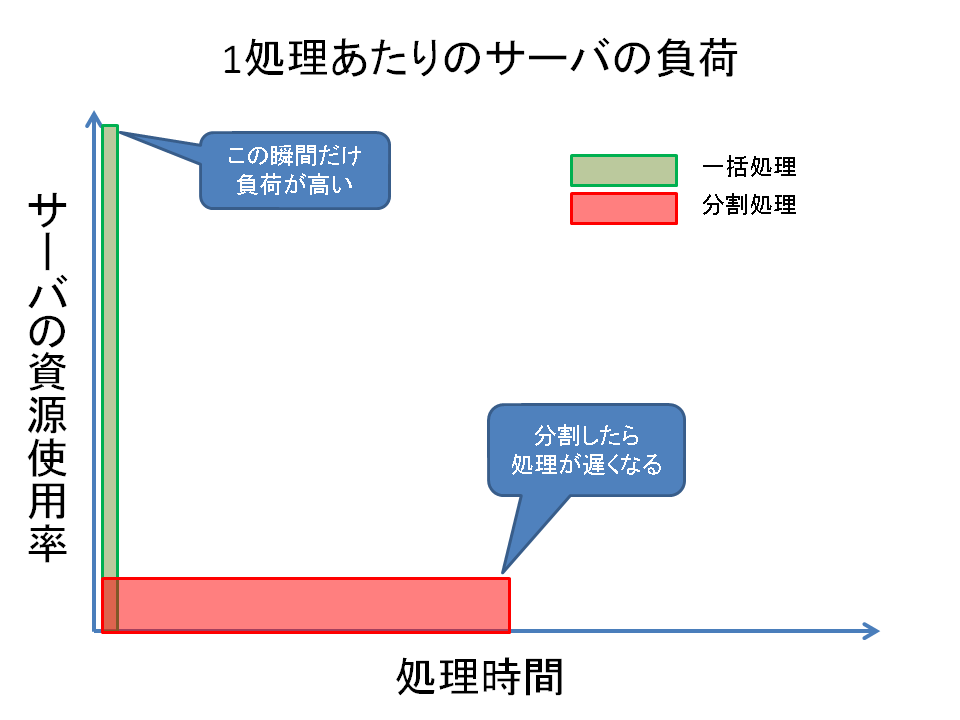動き出しました。
自民党情報化教育促進議連は6月、「教育のICT化に関する決議」5項目を採択しました。
- 一人一台タブレットPC等の導入の促進:低価格化・標準化の推進
- ICT活用による21世紀型教育の推進:100程度の拠点地域を指定
- 教師のICT活用指導力の向上:教師サポートと民間人材の活用
- デジタル教科書・教材の充実・普及:多様な情報端末での利用のための標準化
- 情報モラル教育の充実
どれも非常に大事な事項です。古屋圭司会長、遠藤利明会長代理、山際大志郎事務局長。ぼくが「学」の立場からアドバイザーとなって、策定に協力しました。議連の会議には文科省・総務省の代表も列席していました。
これを受け、デジタル教科書・教材協議会(DiTT)も、政府の情報化推進計画の前倒し、推進地域の全国整備、スーパーデジタル教員の支援、デジタル教育システムの標準化、教育情報化予算の拡充などを内容とする提言をとりまとめ、政府・与党に申し入れました。
政官と産業界とが連携し、「学」が仲を取り持つという構図です。
しかし、その橋渡し役として、ぼくが正面テーブルに座っているのは、いかにも居心地が悪い。というより、不自然なことです。客観的にみて違和感があります。この分野を代表する学界の大御所や専門家は他にもたくさんおられるからです。ぼくは1995年のジュニアサミットに参画してから20年近く、この問題に携わっていますが、教育学や工学の専門家ではありません。
ではなぜぼくが座っているのか。
それは、本来そこに座るべき方々に断られたからです。
DiTTが設立されたのは3年前のこと。MITで$100PCを提唱して以来10年、日本の動きの遅さに業を煮やしたぼくら有志は、そのタイミングがラストチャンスと考え、「一人一台の情報端末とデジタル教科書」の運動を起こすべく声を上げました。
でも、その分野の権威ある先生方や学者のかたがたから参加を断られたのです。全員ではありません。当初から手を組んで進めている研究者のかたはおられます。でも少数。当初たいていは距離を取られました。推進するには問題が多い、教育現場や関係者の反発を招く、といったことを懸念されたからだろうと推測します。
ムリもありません、3年前は「一人一台」というのは乱暴な要求でしたから。
でも、動かなければいけないギリギリのタイミング。仕方がない、叩かれようと殺されようとかまわん、やるしかない、という有志で立ち上げることを決意しました。驚いたのはそれからのこと。東京大学の前総長である小宮山宏先生に相談したところ、私がやると即断していただきました。DiTTの会長に就いていただきました。
その後、京都大学の長尾真前学長、慶應義塾大学の安西祐一郎前塾長も、DiTTに協力していただきました。3学長ともにエンジニアの王道を歩まれ、この分野には深い知見と問題意識をお持ちです。ですが、教育情報化を専門に研究してきたコミュニティとは所属が若干異なります。でも、3学長というボスキャラが立ち上がってくれたおかげで、ぼくらの運動は動きだしたのです。
案の定、ずいぶん叩かれ、議論し、批判され、調整しました。そして3年たって、気がつけばこの運動は政府与党も多くの自治体も「推進」という立場が明確となり、政権に返り咲いた自民党の提言とりまとめの席に、本来の専門家の学者ではなく、DiTT事務局長のぼくが呼ばれたという経緯です。
ぼくは日本のITは大学がネックだと自己批判してきました。MITやスタンフォード大学にいたころ目の当たりにした、学が産官を含むコミュニティのプラットフォームとして機能して新しいプロジェクト、サービス、商品、価値を生み出す構図。日本の学が生んだものは乏しい。その構図が教育情報化にも現れています。何とかしなければいけない。
しかし、この分野については、もう学は必要ありません。もちろん、研究は必要です。情報化の効果検証や優れた教育法の探求、機材や教材の標準化など課題は多い。しかし、こと「運動」としては、学界が旗を振る段階は過ぎ、学校現場と自治体が自らの問題として動く時期が来ました。
本件は動くべきプレーヤーが動き、あるべき状況に近づいたということで、特段の問題もなく、次は現場主導の新しいステージとなる。まぁそれでいいってことでしょう。でも、3年前に、立ち上がる暴れん坊の部隊が存在せず、3学長がリスクを取って参加してくれなかったら、今こういう状況になっていたかどうか。
他にも、リスクを恐れてプレーヤーが動き出さずに停滞しているジャンルはいくつもあるでしょう。ITに限らず。そこで学が役立つことはないでしょうか。点検してみていただきたい。
編集部より:このブログは「中村伊知哉氏のブログ」2013年8月15日の記事を転載させていただきました。
オリジナル原稿を読みたい方はIchiya Nakamuraをご覧ください。