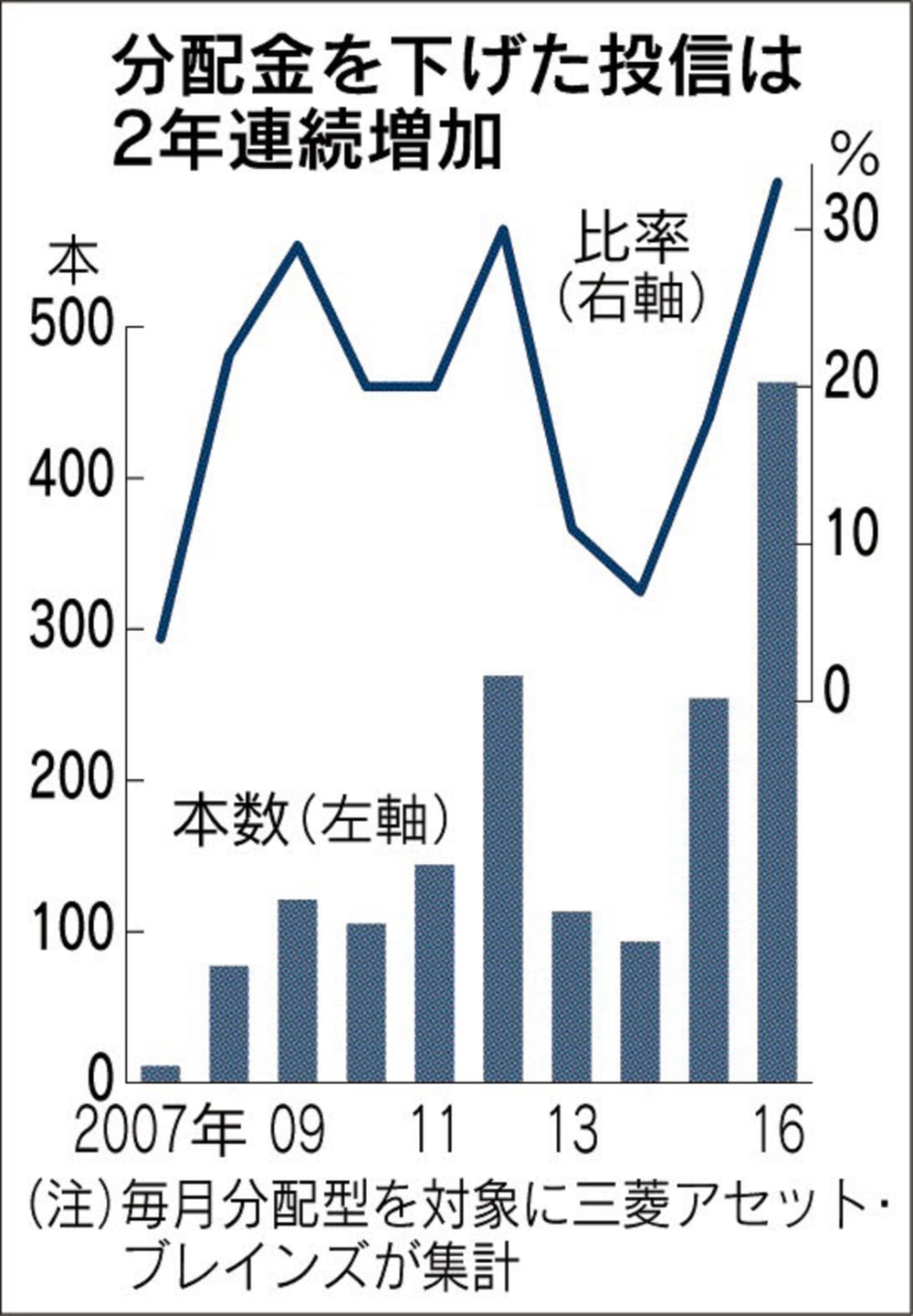インターネット空間の主導権争いをめぐる議論が盛んだ。国家主権、安全保障といった国家レベルの問題から、言論封殺、民主化、コミュニケーションといった個人の表現にかかわる問題、さらには様々な情報イノベーション、娯楽の多様化、eコマースにいたるビジネス分野にいたるまで、切り口は多種多様だ。
メディア論からみれば、新聞やテレビといった大資本による巨大なシステムを背景とした主流メディアから、万人が参画できる簡便なソーシャル・メディアへの転換がある。固定されていた情報の送り手、受け手の関係が解体され、相互乗り入れが常態化する。無力だった個人が大きな発信力を得ると同時に、受け手も自分が求める多種多様な情報を選択する自由を享受できる。情報市場の障壁を取り除く全面開放と言ってよい。
「沈黙の螺旋」と呼ばれる理論がある。社会に一定の大勢意見が生まれると、異なる少数意見はその空気に押され、意見を公表する気持ちをそがれる。こうして人々は沈黙する。沈黙は大勢意見への受動的な合意とみなされ、マイノリティはなだれのようにマジョリティに呑み込まれていく。マジョリティは螺旋状に増殖し、結果的に実際以上の多数派世論が形成される。思考が麻痺し、理性が感性に屈するのである。
ネット空間は情報市場の開放によって、さまざまな意見を表明する場となり、「沈黙の螺旋」理論はもはや適用不能のようにみえる。だが逆に、取るに足らないニュースやデマが、あたかもイナゴの大群に出会ったかのようにたちまち転載され、膨大なアクセス数をヒットする現象が起きる。個人が仮想のサイバー空間に飲み込まれ、正常な思考、理性が奪われているのだ。沈黙の螺旋というよりは、浅薄な言語の過剰が生む「喧噪のなだれ」と評するのがふさわしい。この場合、沈黙と饒舌と現象は正反対のようにみえるが、思考が停止する点においては同じことだ。
毛沢東への激烈な批判で公職と教授職を追われた山東建築大学芸術学院副院長の鄧相超氏(61)は、「自らの求めによって」引き際を決めた。だがそれが本人の真意だとはだれも思っていない。見えない力によってそう追い込まれたのである。見えない力とは、権力者によるあくどい手段だけではない。抗議デモの背景にある、得体のしれない物言わぬ群衆も含まれている。思考を停止し、物見遊山に集まっている人々である。
魯迅はそれを「看客(カンク―)」と呼んだ。1926年、22歳にして軍閥政府の弾圧に倒れた女子学生、劉和珍に贈った一文『劉和珍君を記念する』にこう書いている。
「私は衰亡する民族の、黙して語らない理由を悟った。沈黙よ、沈黙よ!沈黙の中で爆発するのではなく、沈黙の中において滅亡するのだ」
権勢や世論を恐れ、黙して語らない奴隷根性への痛烈な警句である。声を発しなければ民族は滅亡する。真の愛国、憂国の激情が吐いた言葉だ。遠い昔、よその土地で起きた事柄で済まされるのだろうか。ネット社会が生んだグローバル化に意味があるとすれば、苦境にある人々への共感、共鳴を、時空を超えて広く呼び起こすこと以外にない。この共通認識を土台としないネット空間の主導権争いは、しょせん形を変えた権力と利益の奪い合いでしかない。
「わたしたちはいついかなる場合にも思考をやめることができない」。ヘーゲルが『歴史哲学講義』でこう言い残している。眠っているように見えても死んでいるのではない。止まっているように見えても休んでいるに過ぎない。思考を続けなければならない。「沈黙の螺旋」「喧噪のなだれ」の中で、尊い思考から生まれてくるかけがえのない言葉の重みを取り返さなければならない。
編集部より:この記事は、汕頭大学新聞学院教授・加藤隆則氏(元読売新聞中国総局長)のブログ「独立記者の挑戦 中国でメディアを語る」2017年1月11日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は、加藤氏のブログをご覧ください。