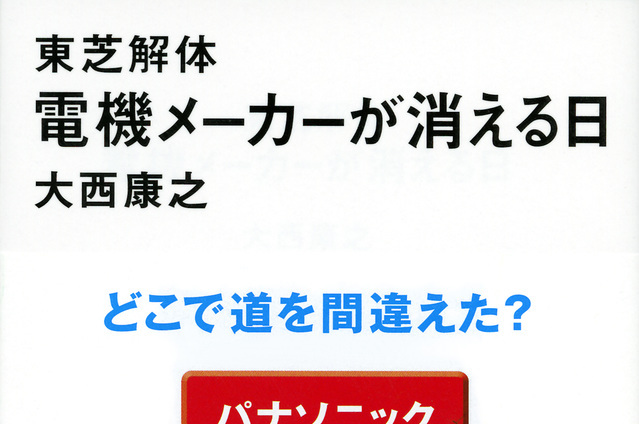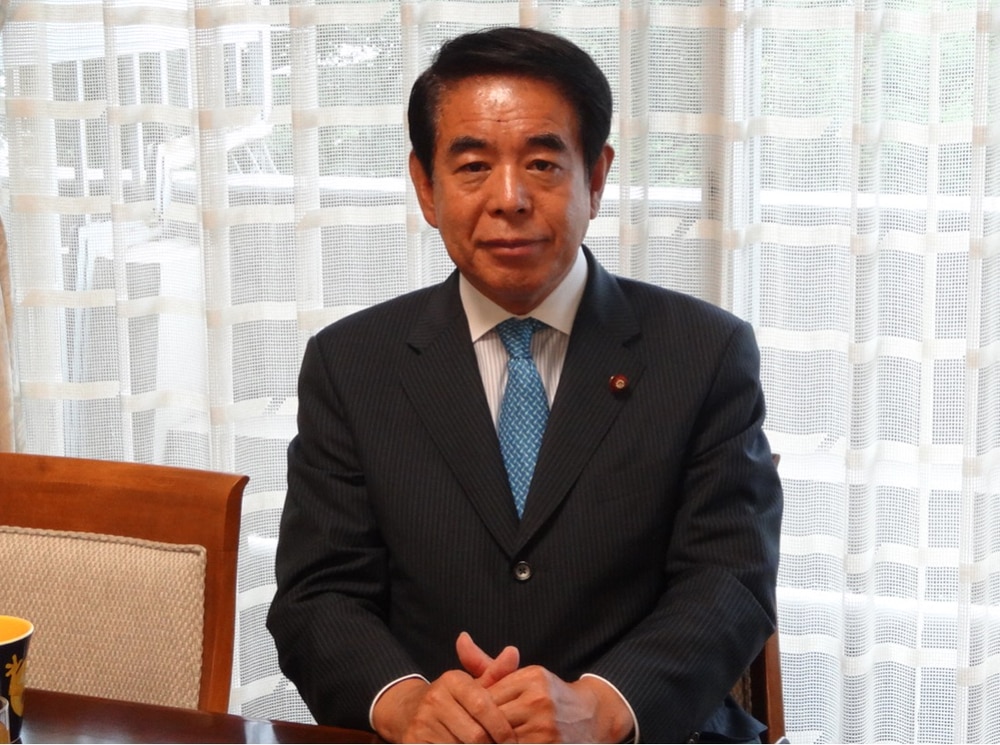ややタイトルがミスリーディングだが、ちゃんと“勝ち組”企業の三菱電機の事例も取り上げてある。電機各社の浮沈は経済誌などではしばしば取り上げられるネタではあるが、こうして各社ごとにコンパクトにまとめられているのは本書だけだろう。あとがきにもある通り「総合電機版の失敗の本質」と言っていい内容だ。
日本の総合電機には、コンシューマー向け家電に軸足を置く独立系にくわえ、NTTをボスとした通信インフラを担当する電電ファミリー、東電など電力会社をボスとする電力ファミリーの3タイプに分類できる。ソニーやパナソニック、シャープは独立系で、NECや富士通は電電ファミリー、東芝と日立は電力ファミリーに軸足を置きつつ電電も兼ねるという図式だ。
電電ファミリーと電力ファミリーは、90年代までは政府にとって重要な景気調整ツールの一つだった。消費を刺激したいと思えば春闘で賃上げをさせて、その原資は電気代や電話代を引き上げて設備投資という名の栄養補給をしてやればいいからだ。電話料金なんて米国の10倍ともいわれるほど高額化したものの、それで電機産業全体を経済のけん引役に育てたわけだから、日本が「成功した社会主義国」と呼ばれたのも当然だろう。
ただし、このアングルはファミリー内の各電機に深刻な内向き体質を残した。
「新規事業で失敗しても本業にいつでも帰れる」
『偏執狂だけが生き残る』(インテル元CEO)ような国際競争の世界で、こういうスタンスでは生き残ることは難しい。ファミリー各社は半導体やテレビ、液晶といった後発事業で次第に劣勢に追い込まれ、本業の稼ぎでなんとか屋台骨を支える状態になっていった。
だが、本業とていつまでも安泰というわけではなかった。KDDIやソフトバンクとの競争がし烈化する中でNTTは設備投資を激減させ、事故により原発ビジネスは事業そのものが成り立たない事態となった。ITバブル崩壊後、NTTの下請けという祖業に回帰していたNECは15年で時価総額を1/5に減少させ、原発事業の世界展開に社運をかけていた東芝は解体不可避な状況に陥った。
富士通、日立も次の収益の柱が見えないまま足踏み状態。ファミリー系以外の独立系でも、経営判断を誤ったシャープは鴻海傘下となり、パナソニックもまだまだ次の一手が見えない状態。明るい話題が聞こえてくるのは、PS4をプラットフォームとするリカーリングビジネスに光が見えてきたソニーと、総合電機から機械メーカーに生まれ変わった三菱電機の2社くらいだ。
さて、ここからは筆者の雑感。
著者は電機各社の衰退の理由について、ファミリー系電機については国策に甘やかされた点、その他の電機については経営がリスクを取らず、変革のスピードが遅い点を挙げている。米WHという大型買収の後に事故に見舞われた東芝は運が悪かったにしても、確かに筆者も電機産業の衰退には、柔軟に変化を受け入れることのできない体質があるように思う。逆に言えば、だからこそファミリーなるものにしがみついてきたのだろう。
それは、2015年に行われたNECの社長交代の発表会見が象徴しているように思う。
それは奇妙な記者会見であり、東京・三田のNEC本社に集まった多くの記者が首を傾げた。新野に社長の座を譲り、自らは代表権のある会長に就任する遠藤信博が笑顔でこう語ったからだ。
「企業で最も大事なことは継続性。自身が作った基盤を引き継いでくれる人に適切なタイミングで渡すことを、トップ自ら示したかった」隣の新野はニコニコ頷いて聞いている。「こんな体たらくを継続しちゃダメだろう」
それが記者たちの偽らざる感想だった。質疑応答で記者に「6年間を自己採点すると何点ぐらいですか」と問われた遠藤はためらう様子もなく「60点ですかね」と答えた。NECの株式を長期保有していた株主は、怒り心頭に発したはずだ。遠藤が社長を務めた6年間、NECの企業価値はひたすら落ち続けてきたのだから。
トップがニコニコしながら継続性こそ大事だと言い、社員もそれに黙々と従い、そういうトップに対して株主のガバナンスがきかない現状をぜんぶ変えない限り、なかなかIBMやフィリップスのような大胆な身を切る改革は出来ないのではいか。
編集部より:この記事は城繁幸氏のブログ「Joe’s Labo」2017年6月19日の記事より転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はJoe’s Laboをご覧ください。