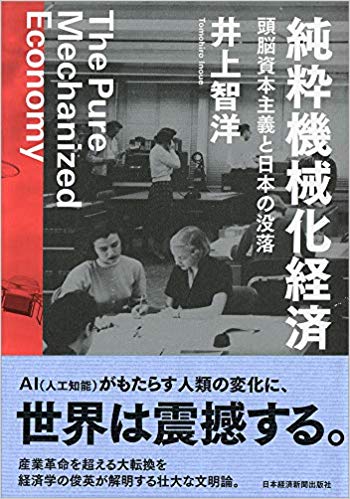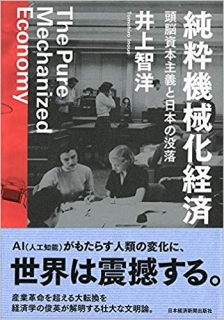 井上智洋さん著「純粋機械化経済」を読みました。
井上智洋さん著「純粋機械化経済」を読みました。
488ページ、スゴい本です。
技術、哲学、経済、国家、文明の切り口でAIの意味を縦横に描きます。
AIは天啓か脅威か。
無論、両面ある。
その登場と普及をどの程度のインパクトとみるか。
ぼくは人類史を前後期に分ける大分岐とみる。
産業革命にとどまらぬ文明の転換とみる。
「超ヒマ社会をつくる」には荒っぽくそう感想を書いた。
井上さんの本はそれを冷静、精密、広範、重厚に解きます。
日本の科学技術力に危機感を抱き、AIの技術水準が国家の命運を分けるとします。
同意します。もちろんAIの限界は認識した上でのことですが、画像認識、IoT、自動運転、信用評価システムなど、急速に広がる利用の破壊力を共有しておきたい。
覇権を握るのはどの国か。
16世紀までの中国、欧州、米国、そして中国へと移るヘゲモニー史を踏まえ、労働者の頭数から頭脳資本主義へ転換する中で日本が衰退する可能性を訴えます。
日本が後進国に転落するだろう、と。
そこには無作為ニッポンへの怒りさえ感じます。
AIはユートピアかディストピアか。
これを巡り、ヒトラー、ユンガー、マリネッティ、福田和也、ウィーナー、マルクス、エンゲルス、ガンディーらが引用されて論じられます。
この軽快なフィールディングによる広い守備範囲が筆者の真骨頂。
さらにネットやAIを巡る哲学論として、ハイデッガー、ジャック・アタリ、ドゥルーズ、ガタリ、フーコー、ライプニッツ、ソシュール、チューリング、ハラリ、ドレイファス、フロイト、カールワイツ、ルソー、ニーチェ、チョムスキー、デカルトが登場します。
ドキドキします。
話は経済学に移ります。
AIは仕事を奪うか。
産業革命の機械化、情報革命のIT化による失業と労働移動を踏まえつつ、AIによる雇用減も雇用増もあるとします。
ただ、ハイテク失業者はローテク分野に流れ低賃金化し、超実力主義の二極化を迎えると論じます。
汎用AIは2030年ごろ登場し2045年ごろ普及するとの展望。
ぼくの超ヒマ本も同様の想定を置き、仕事の減少を能天気なポジティブで書きましたが、本書はそれをより重い実態として捉えます。
ケインジアンvs新古典派、ポストケインジアンvsニューケインジアンの論争も照らしながら。
そして文明論。
ダイアモンド「銃・病原菌・鉄」やハラリ「サピエンス全史」を引いて、狩猟から農耕への移行は人類が「土地」に支配され、害悪をもたらした説に立ちます。
人口増で生存水準が上がらない「マルサスの罠」も紹介しつつ。
産業革命により、インプットが「土地+労働」から「機械+労働」に変化して、生活水準が向上、マルサスの罠を脱却した。
中国、中東、地中海、近代ヨーロッパの経済と技術開発の歴史を追って、現代に至る世界の情勢を整理します。
そして本書の本論、AIによる変化。
農耕革命、産業革命に次ぐ大分岐が起きるとします。
ドイツ型第4次産業革命より、日本型Society5.0に近い見解です。
インプットは労働が不要な「機械」のみとなる「純粋機械化経済」という本書の題名が登場します。
注目すべきは政策論。
爆発的な供給増に需要が追いつかないデフレ圧力を前提とし、財政政策より金融政策が効果的とした上で、「ヘリコプターマネー」を提案します。
併せて、大規模な再分配政策としてのベーシックインカム。
大胆な提言。でもこのくらい根本的な政策構築が求められるとぼくも考えます。
唐突に1968年革命が登場。
ゴダール「中国女」、「俺たちに明日はない」、ソンミ虐殺、キング牧師暗殺。
ヒッピーイズムからアナーキズムに話が及びます。
ネグリ・ハートのマルチチュード(民衆)vs帝国。
さらにはシカゴ学派ミルトン・フリードマンの自由主義も。
計画経済と対比されて論じられます。
アナーキズムもソ連型社会主義も批判する一方、グーグルが貨幣を発行する日を展望しつつ、再分配と金融政策は国家しか責任を持てないとします。
現時点では穏当な帰結ですが、筆者がスキゾに疾走するにつれ、この考えが変化していくかどうか、関心があります。
本書は、68年革命は「脱労働社会を到来させるAIとBI(ベーシックインカム)による革命のリハーサルだ。」で終わります。
レベルは全然違うけれど、超ヒマ社会をつくりたいぼくの趣旨と方向は同じ。
フルコースを味わって満足しました。
ぼくの本はiUに入る高校生向けに書いたけど、同ジャンルの大学生には本書を薦めます。
AIの大分岐には、専門の掘り下げとともに、技術、哲学、経済、歴史、文明といった横断的な教養というか、それらを拒絶しない好奇心が決め手。
それを教えてくれる好著です。
編集部より:このブログは「中村伊知哉氏のブログ」2019年12月2日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はIchiya Nakamuraをご覧ください。