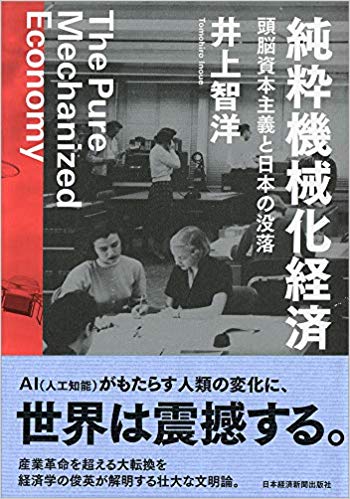日経に「節税封じ あの手この手 ソフトバンクGのM&Aなど いたちごっこの恐れ」とあります。

(写真AC:編集部)
ソフトバンクが使った節税手法に対して税務当局がお怒りになっているのでしょう。非常に複雑ですが日経の説明は以下の通りです。
「SBG(ソフトバンクグループ)はリミテッド株(アームHDの重要子会社)の4分の3をアームHDから配当の形で吸い上げた。SBGは、価値が大幅に下がったアームHD株の大部分を傘下のソフトバンク・ビジョン・ファンドなどに売って帳簿上の赤字を発生させた。この赤字と他の部門の黒字を相殺することで、1兆円を超す連結純利益をあげたSBGの法人税負担はゼロになった。」
一言でいうとある事業について帳簿上の赤字を意図的に生み出し、その損失をもって儲かっていたほかの事業の利益を相殺することであります。帳簿の赤字は痛くも痒くもないのです。今は合法ですが、税務当局はそれを今後許さない方針です。
私が以前勤めていたゼネコンでも節税については異様に執着していました。当時のオーナーが旧大蔵省出身ということもあり、詳しかったこともあります。私がまだ26~27歳の頃、次々と押し寄せる不動産開発案件等で将来にわたる節税方策をパズルのように組まされたことは鮮明な記憶として残っています。
その後、バンクーバーに赴任した後、カナダの関連会社も節税目的で複雑怪奇な子会社、関連会社の資金の流れの中で儲かってもいない事業の儲けた後の節税対策に躍起になっている本社に違和感を感じないわけにはいきませんでした。結局、その節税はどうなったかといえば私が買収後にその効果が絶大となり、見事に税金を払わずに済んだというオチがあります。
不動産事業者には国内外を問わず、強力な節税ができるごく当たり前の方法があります。それは減価償却による損失で経常利益を相殺するという手段です。開発事業は特に初めの5年ぐらいは非常に大きな減価償却が発生します。(各国の償却のルール次第です。)単体の開発事業ならほぼ5年近くは赤字、でもキャッシュフローは真っ黒という状態になります。よってだいたい5~10年に一度、大きな開発事業をやっていくことで節税ができるようになっています。これは不動産開発業者では当たり前でだからこそ、「やったらやめられない不動産事業」ということになるのです。
連結納税ができないカナダでは赤字会社の売買もよく使う手段です。私もその研究をしたことがあります。儲かっていない会社を赤字1ドルあたりいくらといった考え方で買収するのです。当時、こんなことも商売になるのか、と驚いたものです。
さて、冒頭の日経の記事はソフトバンクなど企業の節税に限らず、富裕層の節税にもより血眼になっているようです。「富裕層が使う海外不動産投資を通じた節税策も封じる。海外投資で生じた赤字を国内の所得に合算して所得税の負担を減らせないようにする」とあります。これを一種の連結納税だと考えれば日本国内の事業と海外事業の連結をさせないということです。
これを突き詰めていくと日本もそのうち連結納税に対して厳しい施策が出る可能性があります。ちなみに連結納税とはグループ会社間の損益を全部足していくら納税するという発想です。A社が1億円の黒字、子会社のB社が1億円の赤字なら連結してゼロになるということです。カナダはそれを昔から禁じていますが、当初はやりすぎだろう、と思っていたのですが、今はなぜ、日本で取り入れないのだろう、と思っています。
国家の歳入に於いて個人所得税と消費税が伸びている一方で法人税が今一つで三本柱の一角として「威厳を保っていない」と私は思っています。企業財務担当者からはおしかりを受けるかも知れませんが、税務当局が連結納税をやめれば法人税収は今の2倍になってもおかしくないと考えています。
実は連結納税をやめることで企業の活性化も進むのです。赤字の子会社、関連会社を持つ意味がなくなり、企業のリストラが進むからです。税務当局は海外の富裕層に関しては国会議員の抵抗がなく、やりたいようにその締め付けを行っていますが、国内についてとるべき努力をしていないと考えています。ある意味、とてもずるいのです。政治家に抑えられ、正義としての税収が上がらないのはおかしいでしょう。
ならば税務当局も日銀と同様、独立性を与え、国会議員の口出しができないようにしたらどうでしょうか?仮に連結納税制度を止めれば、国家歳入は大きく変わり、プライマリーバランスは達成できる可能性は高まると思います。私から見れば普段の税務当局の対策は小手先、だからこそ、日経に「あの手、この手」「いたちごっこ」と揶揄されるのでしょう。消費税は当面10%で打ち止めでしょうから税務当局の次の一手に注目したいと思います。
では今日はこのぐらいで。
編集部より:この記事は岡本裕明氏のブログ「外から見る日本、見られる日本人」2019年12月2日の記事より転載させていただきました。