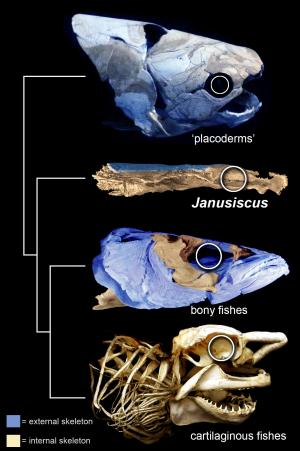久しぶりに先月、病院に入院(眼科病棟)した。入院生活は決して楽しいものではないが、取り立てて大変ということはない。簡単に言えば、忍耐の日々だ。限られた空間で行動も束縛される一方、病の進展が気になるから、心は穏やかではない。
さて当方は夕食が午後5時前後と極端に早いことが困った。夕食後の夜の時間が長すぎる。16年前の入院生活(泌尿器科病棟)は少々長かったが、その食事メニューは今回より豊かだった記憶がある。朝食7時、昼食12時、夕食が5時前後だ。昼食が1日のメインだ。今回の入院生活の昼食メニューを紹介すると、ウイーナーシュニッツエルとジャガイモ、それにプリン。別の日はフィアカー・グラーシュにスープ、それに1本バナナがついていた。昼食はまあまあだが、朝と夕はセメル2個にバターとジャムだけだ。前の入院では、朝食にヨーグルトがついていたが、今回ヨーグルトの姿を見なかったところをみると、病院側も節約路線を強いられているようだ。
部屋は16年前と同様、4人部屋だった。当時の病棟ではがん患者が多かったので、回復の見通しのない患者と快方に向かっている患者では明暗がはっきりしていた。今回は眼科病棟だったので、がん患者のような深刻な雰囲気はなかったが、網膜剥離で失明する恐れもあることから、患者の心理は複雑だ。がん病棟と眼科病棟の両方を体験した当方にとってはがんも大変だが、目がやられると全てのオリエンテーションがなくなるから、これまた大変だ。普段の生活に支障が出てくる。
当方ががん病棟にいたとき、ベットから離れたくないので看護人に「食事をベットまで持ってきてほしい」と頼んでみたが、「ベットから立ち上がって自分の足で食事を運びなさい」と厳しく注意されたことを覚えている。手術直後の患者をできる限り、動かすことで早く床離れさせるためだ。一方、眼科病棟では看護人が食事を必ず運んでくれる。体力があっても目が不自由だからだ。当方の場合、手術で右目にガスを注入していた。だから、視界が見えない。肝心の左目も視界が良くないので、歩行もままならない状況だった。
入院生活で忘れることができない思い出は、16年前の手術後のこと。集中治療室に運ばれたが前日から何も食べていなかったので、根が食いしん坊の当方は夜中、空腹に悩まされた。すると、担当看護婦が「特別よ」といって一口サンドイッチを運んでくれたのだ。思いがけない差し入れの美味しかったこと、その看護婦が天使のように見えたものだ。
病気になると、患者は「ダンケ、ダンケシェーン」(ありがとう)という機会が増える。医者や看護婦に助けてもらう度に「ダンケ」が出る。患者は彼らの助けなくしては生きていけないから頼ることしかできない。病気になって初めて他人の親切が身に染みて有難く感じられる。病気は人を謙虚にするものだ。それが病を体験することの効用かもしれない。
編集部より:このブログは「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2014年8月17日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。