
先日、編集者さんとの打ちあわせで言われたのだが、ぼくは業界でも「筆が速い人」の方に入るらしい。本人の自画像とはだいぶ違うが、でも想定外の事件の翌朝に記事を出したりはするから、たぶんそうなんだと思う。
ちなみに別の編集者さんからは、「なかなか落ちない人」として有名ですと聞いたこともある。新刊の執筆を簡単にOKしない人、の意味で、逆に言うと他の著者はそんなに気軽に引き受けまくってるのかと驚いたが、 “筆が速いのに” 受けてくれない、という含みだったかもしれない。
そんな次第で、実は〆切ものは “余裕をもってあらかじめ” 書かないと、落ち着かない性格だ。なのでよく、後で「しまった!」と叫ぶことが多い。もうちょい書くのを待てば、この本も記事で採り上げられたのに、的な。

前回ご紹介した『Wedge』の連載では、戦後80年目の収穫となる歴史書を3つ挙げたけど、まさに「しまった!」が執筆後にやってきた。刊行のたびに献本してくださる(これまでの拙書評を末尾に)、前田啓介さんの新刊が10月に出たのだ。
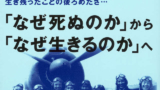
詳しい人には自明だけど、戦争を経験してれば全員が「戦中派」になるわけじゃない。学徒出陣や特攻隊志願など、”青春をまるごと戦争に捧げた” 世代を指す用語で、定義は人により幅がある。
本書では「1917~27年生」が戦中派で、核をなすのが「1920~23年生」だ(53・63頁)。ぼくは別の切り口で、”知識人” としての活躍が遅い山本七平(21年)・司馬遼太郎(23年)・網野善彦(28年)を、「遅れてきた戦中派」と呼んだことがある。
前田氏の本書が圧巻なのは、有名・無名の戦中派世代の手記を用いつつ、戦時下だけでなくその “前と後” まで、彼らの人生に則して描いたことだ。戦後も80年目といえど、これは類書がないと思う。
「あの戦争」を語るとき、ぼくらの視点は “戦争そのもの” に行きがちだ。だから「戦後80年」と言われても、いまに繋がる後遺症を捉える戦後史の方は、大切なのにそこまで読まれない――と、つい愚痴っぽくなるけど、それはどうでもいい。

著者の肉親も含め、無数の人が登場する『戦中派』だが、軸になる親友コンビが2組ある。片方は、『戦艦大和ノ最期』の吉田満(1923年)と、彼の青春を伝える日記を残した志垣民郎(22年)。
マジメ一徹なエリート学生で、特に志垣は敗戦後に言動を翻した教授たちを許せず、匿名で暴露本まで書いた(276頁)。この人は内閣の機密費を使い、言論人を政権寄りに懐柔する仕事をしたことで有名だが、それも屈折ゆえかもしれない。
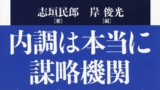
もうひと組は、作家の安岡章太郎(20年)と古山高麗雄(同)。こちらはグレちゃったタイプで、どんどん軍国主義一色に染まる世相になじめず、入営までは飲みィのヤリィの、ひたすらふまじめに暮らしてすごした。
が、軽薄だったわけじゃない。体制になびかないだけで、むしろガチで気合の入った抵抗だった。
古山は、第三高等学校の口頭試験でも「八紘一宇」について「それと侵略主義とはどこが違うかね」と試験官に尋ねられ、「八紘一宇と言っても、結局は侵略主義です」と答えるというやり取りをしている……。
国のやり方に反発していたのは古山だけではないが、それを面接会場という閉じた空間であっても、当時の正解ではないことを言うのは勇気(蛮勇と言うべきか)が必要だっただろう。
(中 略)
そういう若者を全否定しない風潮も学問の世界にはまだあった。だからこそ古山がそう答え、試験官が「うむ」とうなずき、問いを終えた時、「通った」と思ったのだろう〔1940年入学〕。
112-3頁(強調と改行を付与)
ここまで180度反対の2組が、どちらも敗戦後、なぜ自分は助かり他の者が死んだのか、”偶然” 以外に根拠なく生き残るのは不誠実では、との問いに憑かれる。この対照が、圧倒的な世代のトラウマの過酷さを、読者に伝える。
より強烈なことに、さらに別の対比も重なる。
一般に戦中派を代表する作家は三島由紀夫(25年)だが、よく知られるとおり、徴兵検査に不合格で兵士の体験がない。ので、”拡大自殺” のための決起をバーチャルな代償行動と見なす視点は、本書に限らずいっぱいある。

が、ここで古山高麗雄の三島観を突きつけられると、思わず「うっ」と呻いてしまう。三島がコスプレする “純情な軍国青年” を冷ややかに眺めつつ、しかし自ら戦場をリアルに体験した古山は、事件をこんな風に見ていた。
そんな古山が「今度の三島由紀夫さんの自殺については、まったく感動がない」のだと、あえて書く。三島とは知らない間柄ではなく、熱海のホテルのプールで一緒に泳いだり、食事をしたりした知人であった。だから感情は動いたが、衝撃はなかった。
(中 略)
生死を決めるものが運であることを〔戦場での体験から〕知る古山は、だからといって、それですべてを納得させようとしたわけではない。どれほどその死に高尚な思想があったとしても、それは関係ない。死のうと思って死んだ人よりも、生きたいと思いながら死んだ人の方が哀しい。
383-4頁
悔しいので、著者が用いてない資料を引いておこう。古山が「プレオー8の夜明け」で受賞した芥川賞の選考は1970年の7月18日で、委員の一人が三島由紀夫。つまり、あと4か月で自殺する彼の、最後の選評にはこうある。

「プレオー8の夜明け」は、体験曲折の上に、悲喜哀歓と幸不幸に翻弄された極致に、デンとあぐらをかいた、晴朗そのもののノンシャラント〔無頓着〕な作品で、苦味のある洗煉は疑いようがない。
しかしこうまで見事に腰の坐ったノンシャランスは危険である。今度はこれに対して、どんな野暮な批評も可能になるからである。あらゆる人の口をつぐませることはできないというのが文学のおそろしさで、そのことに九十九パーセント成功しているこの作品といえども、一パーセントの瑕瑾は免れなかった。
『芥川賞全集8』文藝春秋、536頁
自分は(内心バカにしていた)戦争の現場で悟った。ぜんぶ運だ。無価値だ。——といった古山の諦観に対して、「野暮な批評」かもしれないが、俺はもうすぐ軍国調で死んでみせる、99:1でもかまわない、と書いたのだろう。たとえコスプレでも、すごい気迫である。
そんなガチさなしで生きられる時代のほうが、もちろんいいに決まってるのだが、慣れすぎると今度はノンシャランスの方が堕落する。つまり、どーせ無意味ならニセモノでいーじゃん? な人が現われて、文学もガクモンも食い潰してゆく。

そんな時代にこそ、「本物」が必要だ。
歴史とは、この社会にも “かつては” 本物がいたのだと、確認しあうプラットフォームのようなものだ。その純正品、ホンモノの利用ガイドとして最良の手引きである本書が、ぜひ多くの読者を得ることを望みたい。

参考記事:


(ヘッダーはAmazonでの広告。左の軍装が古山高麗雄、右写真の中央に吉田満・右隣に志垣民郎)
編集部より:この記事は與那覇潤氏のnote 2025年11月25日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は與那覇潤氏のnoteをご覧ください。














