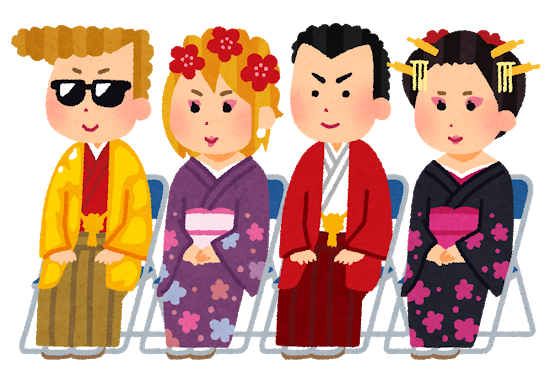本書が出て2ヶ月になるが、60万部を超えるベストセラーになり、アゴラでもいまだに賛否両論を呼んでいる。私は内容には興味がなかったが、帯の「私たちは何者なのか」という文句に引かれて読んでみた。個人や国家のアイデンティティの核にあるのは、自分が何者かという物語である。韓国はいまだに「日帝36年」の物語を国定教科書で教えているが、日本人はどんな物語をもっているか興味があったからだ。

百田氏ブログ、Amazonより:編集部
多くの人が指摘するように、本書は歴史書としてはかなりお粗末である。事実誤認が多く、他人の本の孫引きが目立つ。これは著者がアマチュアなのだから、ある程度はしょうがない。それより彼は作家としてはプロなのだから、歴史小説としておもしろいかどうかが問題だ。司馬遼太郎の小説が事実に反していると批判する人はいないだろう。
だが結論からいうと、おもしろくなかった。小説としては無味乾燥で、オリジナリティがない。約500ページのうち幕末以降に270ページを費やしている本書の力点は明らかに近代史にあり、そのねらいは「自虐史観」を否定しようという「新しい歴史教科書をつくる会」の教科書と同じだが、その劣化版である。
「大東亜戦争」についての記述もそれほど極端なものではないが、逆にいうと目新しい話はない。林房雄の『大東亜戦争肯定論』ぐらいスケールの大きな物語を展開すればおもしろかったが、そういう独自の歴史観があるわけでもない。本書の特徴は「南京大虐殺」はなかったという話ぐらいだが、これは定義の問題にすぎない。
全体としては日本を「美しい国」として賞賛する安倍政権の歴史観だが、戦後だけは妙にネガティブな物語になっている。特に戦後の政治をWGIP (War Guilt Information Program)で説明する陰謀論は、江藤淳が1980年代に主張したものだが、歴史的な証拠がない(本書も根拠を示していない)。
たしかにアメリカが憲法を「押しつけた」ことは明らかであり、GHQが検閲したことも周知の事実だ。東京裁判が戦勝国による一方的な断罪だったことも確かだが、そこにWGIPなどという系統的な方針があったわけではない。たとえGHQがそう考えていたとしても、占領の終わった1952年以降は、アメリカが日本でWGIPにもとづく情報を広める手段はない。
平和憲法がWGIPで強要されたものだとすれば、占領が終わったとき、日本人はそれを否定したはずだ。天皇が現人神だなどという神話は誰も信じていなかったので、戦争が終わった途端に人々は皇国史観を否定したが、占領統治が終わっても憲法は改正できなかった。本書は日教組やマスコミが悪いと書いているが、自民党も改正をいわなくなった。
本質的な問題は、戦後70年以上たった今も、こういう物語が続いているのはなぜかということだ。これは私が『丸山眞男と戦後日本の国体』で論じたテーマである。この複雑な問題に単純な答は出せないが、結果的には日本人は平和憲法を受け入れたのだ。それは主権者としての主体的な選択ではなかったが、平和の長かった日本人にはなじみやすかった。
この「アメリカの物語」は自民党の親米路線とも親和的だったので、平和憲法は戦後日本の国体になってしまった。それは矛盾しているが、戦前の国体ほど荒唐無稽ではないので、多くの人が信じている限り続く。今どき憲法9条を本気で信じている人は少ないが、日本人には島国の自然なアイデンティティがあるので、この程度のいい加減な物語で十分なのだ。
だから日本人にはいまだに自前の物語がなく、自分が何者かわからない。この平和ボケを脱却する必要はあるが、それに対抗するのがGHQ陰謀論では「日帝36年」と大差ない被害妄想である。日本が政治的に成熟するためには歴史観をめぐる対話が必要だが、本書をバッシングする左派と盲目的に支持する右派の対立をみると、対話の道は遠いようだ。