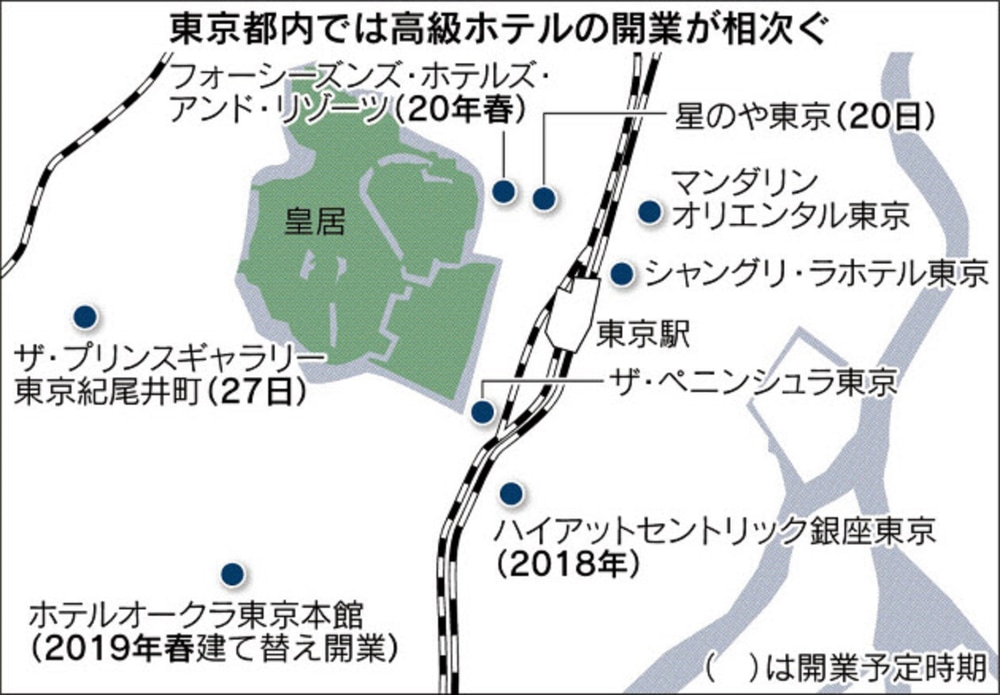ローマ法王フランシスコは今月27日からポーランドを訪問する。目的はクラクフで開催される第31回世界青年集会に参加することだが、ユダヤ人強制収容所があったアウシュヴィッツを訪ね、そこで75年前犠牲となったマキシミリアノ・コルベ神父の前で祈祷を捧げる予定だ。なお、故ヨハネ・パウロ2世、前法王ベネディクト16世も任期中に同地を訪問している。
フランシスコ法王のポーランド訪問に先駆け、バチカン放送独語電子版は13日、「アウシュヴィッツ以降の神学」という見出しの興味深い記事を掲載している。600万人以上のユダヤ人がナチス・ドイツ軍の蛮行の犠牲となった後、「なぜ神は多数のユダヤ人が殺害されるのを黙認されたか」「神はどこにいたのか」といったテーマが1960年から80年代にかけ神学界で話題となった。すなわち、アウシュヴィッツ前と後では神について大きな変化が生じたわけだ。神学界ではそれを「アウシュヴィッツ以降の神学」と呼んでいる。
ドイツの実存主義哲学者のハンス・ヨナス(1903~1993年)は「アウシュビッツ以後の神」という著書を出し、ナチス・ドイツの絶対悪に対してなぜ神は沈黙していたのか、暴力の神学的意味などを追求した一人だ。同時に、「神の死」の神学が1960年代に登場してきた。
キリスト教では神といえば、愛の神であり、慈愛の神を意味する。その「愛の神」の欧州キリスト教文化にアウシュビッツ以降、「神が愛とすれば、なぜ神は救済しなかったのか」という疑問が沸いてきたとしても不思議でない。アドルフ・フォン・ハルナックの「神は愛」といった神学ではもはや不十分だというわけだ。
今月2日死去したユダヤ人作家で1986年のノーベル平和賞受賞者エリ・ヴィーゼル氏(1928-2016年7月2日)は自身のホロコースト体験を書いた著書「夜」の中で、「神はアウシュヴィッツで裁判にかけられた。その判決は有罪だった」と述べている。アウシュヴィッツ以降、神の全能性、善性に疑問が呈されていったわけだ。
もちろん、神の不在が問われたのはアウシュヴィッツが初めてではない。欧州の近代史で2回、大きな天災があった。「リスボン大地震」と「1816年」だ。前者は1755年11月1日、ポルトガルの首都リスボンを襲ったマグニチュード8.5から9の巨大地震で、津波が発生。同市だけでも3万人から10万人が犠牲となり、同国全体では30万人が被災した。文字通り、欧州最大の大震災だった。その結果、国民経済ばかりか、社会的、文化的にも大きなダメージを受けた。ヴォルテール、カント、レッシング、ルソーなど当時の欧州の代表的啓蒙思想家たちはリスボン地震で大きな思想的挑戦を受けた。そして北欧、米国・カナダなど北半球全土を覆う異常気象が発生し、農作物に大被害をもたらし数万人の飢餓者が出た「1816年」の時もそうだった。「夏のない年」と呼ばれた。
アウシュヴィッツの場合、犠牲者の多くがユダヤ人だった。彼らは神を信じる民だ。そのユダヤ人がユダヤ人であるゆえにナチス・ドイツ軍の蛮行の犠牲となった。その数はリスボン大震災を上回っている。神の不在に悩み、その解答を見いだせないため信仰を捨てた多くのユダヤ人もいた。神を捨てることができない者の中には神と和解するために苦難の日々を過ごした人たちも少なくなかっただろう。神学者の中には、「神はその全能性を被造世界の創造後、放棄した。そして人類が神に代わって責任を担うことになった」と考えて、神の不在を乗り越えていこうとした。カール・バルトの「悪は創造の影」といった神義論もある。
ユダヤ民族は“受難の民族”と言われる。その受難は、神を捨て、その教えを放棄した結果の刑罰を意味するのか、それとも選民として世界の救済の供え物としての贖罪を意味するのか。アウシュヴィッツ以降の神学はその答えを見出すために苦悶してきたわけだ。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2016年7月20日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。