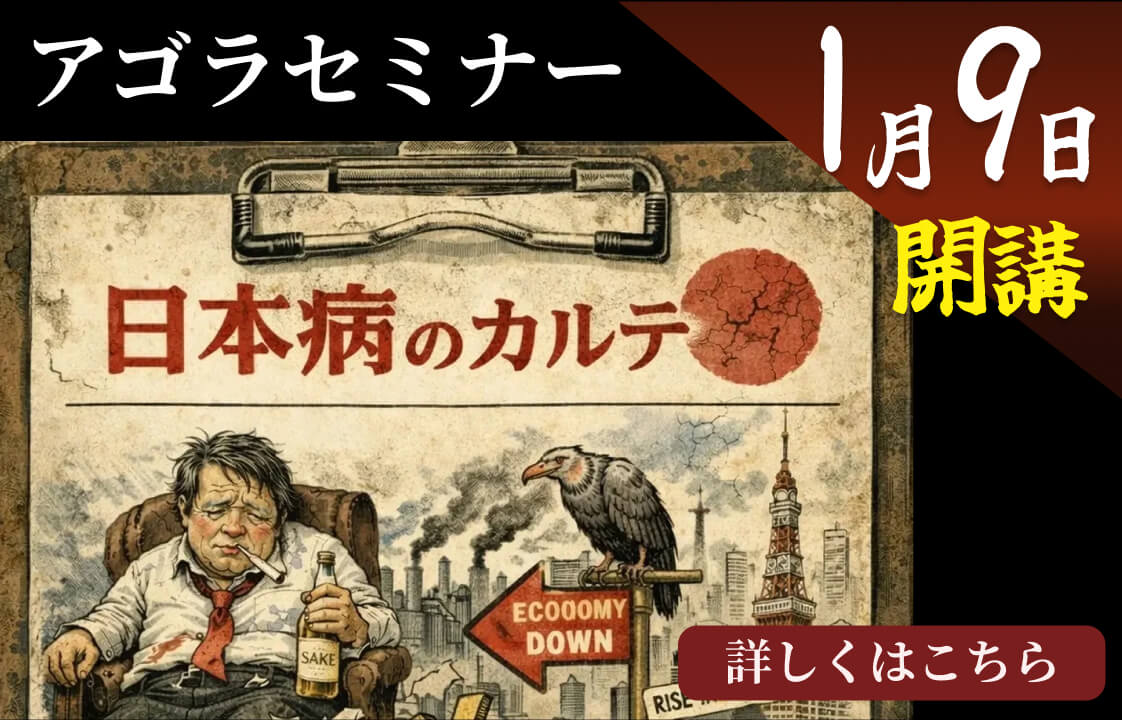ShutterOK/iStock
個人の高所得者の重税感が高まっています。個人の所得に対する最高税率は、所得税と特別復興所得税さらに住民税を加えて55%を超えています。
高所得者の富裕層にどこまで累進で課税するべきかの議論はありますが、ここで忘れてはいけないのは、個人の高所得者だけが富裕層ではないと言うことです。
高所得者とは収入、つまり資金のインフローが多い人です。一方で、フローはそれほど多くなくてもストックの資産が多い富裕層も存在します。リタイアした年金生活者の中にはこのストックの富裕層が多数存在します。
資産に関しては不動産の所有者には固定資産税が課されていますが、株や投資信託などの金融資産には大量に保有していても税金はかかりません。
ストックに対する課税はフローに比べてかなり小さいと言えます。
さらに考えなければいけないのは、法人の存在です。オーナー経営者の中には、個人と法人に資産を分散させ、収入に関しても2つを使い分けているケースがあります。
法人と個人が実質的に一体化している状態にもかかわらず、2つの課税方法は異なります。
だから個人の所得を減らし法人に寄せることで、所得税を減らし法人税を増やすことも可能になります。逆もまた然りです。
このように考えていくと、富裕層とは個人の収入が多い人だけではなく、個人のストック、法人のフロー、法人のストックが多い人も含めるべきということがわかります。4つのパターンに分類することができるのです。
そして、この中では個人のフローに対する税負担が一番重いように思います。
誰しも税金はあまり払いたくないものですし、払うのであれば負担の公平感が損われるのは好ましいことではありません。
取れる所から取るという安直な発想ではなく、勤労意欲を高め、真面目に努力してリスクテイクしている人が報われるような税体系を実現しないと、生産性は上がらず、成長率も上向く事はないでしょう。
そして税の公平性の前に、税の無駄遣いを見直すことも必須です。納税者が真面目に税金を払うのが馬鹿馬鹿しく感じないようにして欲しいものです。
編集部より:この記事は「内藤忍の公式ブログ」2025年2月5日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿をお読みになりたい方は内藤忍の公式ブログをご覧ください。