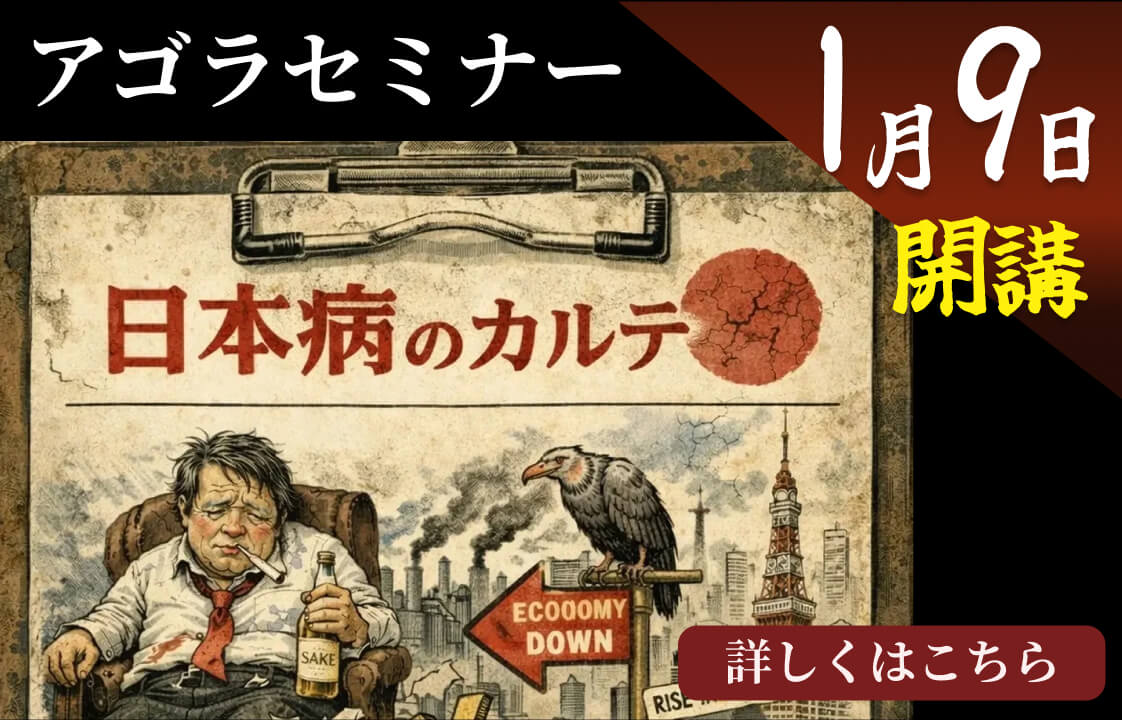昨年、コメ不足でニュースでは学生がコメをもっと食べたいという声を報じていたのが印象的でした。この米不足は23年度が不作だったことが要因とされるも24年度は作柄が良く、新米が出れば価格は落ち着くとされてきました。私もそのようなことをこのブログで書きました。実際、2024年は679万トン生産され、23年に比べて18万トンも多いのです。18万トンとはおおよそ茶碗28億杯ぐらいにあたります。日本人のうち、1億人が一日1膳食べる分として約1か月分にあたります。24年の全生産量679万トンで計算すると1038億杯分になるわけで1億人の国民が一日3膳弱食べられる計算です。

Yuki KONDO/iStock
つまり生産量から計算すると概ね日本人の胃袋は満たしているのです。ところが価格が下がらない不思議が起きているわけです。
日経は計算上、17万トンが消えているとしています。どこに、であります。その可能性が指摘されているのが卸問屋などに値上がり期待で滞留している可能性です。そこで今回、農水省が重い腰を上げ、政府備蓄米の放出ができるような仕組みを導入、放出した場合、所定在庫量に1年程度で戻すことを前提としました。さて、これが機能するでしょうか?
ここカナダ。アジア系スーパーに行けば様々なコメが販売されており、日本人が好む水分の含有量が多いコメも人気ある種類です。コメは主に短粒米、中粒米、長粒米があり、日本で売っているのはほとんどが短粒米ですが、カリフォルニア産のジャポニカ米とされるものは中粒米(カルローズ)になります。食感は私的には全く問題ありませんが、日本の新米と比べるとそれは厳しいものになります。しかし、価格的には4.5㌔で2000円から2500円程度で日本のスーパーが5キロで4000円近くなっているのと比べればかなり安いと言えます。
味は若干落ちるけれどこれを日本に入れられないのか、と思います。輸入米に関しては知る人ぞ知る1993年のウルグアイラウンドで日本は年間77万トンの輸入が決まり、多くは飼料になりますが、食用分として10万トンあります。この輸入米は年4回入札があるのですが、このところの入札では応募倍率が3倍程度あり、価格は1年で15%程度上昇、もちろん全量入札完売状態となっています。よってこの10万トンを仮に20万トンに増やすといえば倉庫に備蓄している業者は先々、値下がりすると見込み、民間備蓄分を売り急ぎ、価格が崩落するというシナリオは当然あるわけです。
農水省がこのあたりをどう手さばきするかですが、ウルグアイラウンドの77万トンの枠のうち、食用を増やせばよいだけの話でそんなに小難しい話をしているとは思えないのですが、こういうことには社会が暴動的な声をあげない限り役人は動かない、米問屋も「うちにはない」と知らんぷりなのでしょう。
ところで、この10万トン枠とは関税の枠組みであり、輸入制限されているわけじゃないのです。キロ当たり341円の関税を払えばいくらでも輸入できます。上記10万トン枠は無税ですが、政府が手数料みたいなものを課しており、それがキロ当たり292円。つまり枠を超えても実質的には49円しか違わないわけです。円安のデメリットを乗り越えても今はカリフォルニア米のほうが競争力はあります。ただし、国内が本質的なコメ不足ではなく、米一揆にならない現代版米騒動というか、米問屋のせこいビジネスが背景です。
私が気になるのは食べ放題店が増えたことで当然、米もその一環にあること。そして食べ放題経営につきものの廃棄が多く、米も多くが無駄になっていやしないだろうかという点です。昨年の朝日新聞の記事にはコンビニ、スーパー、食品会社から持ち込まれる廃棄米は一日おおよそ8トンだと報じています。この記事の信憑性については十分検討しなくてはいけませんが、それぐらい廃棄されているということでしょう。炊飯米だけで8トンだとすれば米で計算すれば仮におおざっぱに水分含有量が50%として4トン程度が廃棄されているという計算になります。もったいないです。
将来的な話をするにはファクターが多いのですが、一つは気候変動のリスク、もう一つはコメ食が今後どう変化するかであります。私が小さい頃はコメ生産の北限は東北地方と学校で習ったものですが、今では北海道産も高い人気があるほどです。コメ食についてはパンやパスタなどが増え、また健康管理上、過剰な炭水化物摂取は良くないという声からコメの消費は人口低下のトレンドに沿うとみています。ただ、近年のおにぎりブームなどでマーケティング的にコメの消費が増えていることは一時的な消費増大となっているのでしょう。
生産者目線で見れば農家経営者の高齢化と生産を維持できなくなるケースが出てくるかもしれません。
コメはカロリーベースの食糧自給という観点から政府が強く後押しするものでその発想を否定するものではないのですが、海外からの輸入枠や輸入量といういざという時の手段は確保すべきだと思います。国民に経済的負担にならない金額でコメを供給するのはある意味テクニック論でもあります。ましてや「コメの価格が高い」となれば余計食べたくなるのが人間の心理。とすればそのマインドを冷やすという手法も重要だと思います。
では今日はこのぐらいで。
編集部より:この記事は岡本裕明氏のブログ「外から見る日本、見られる日本人」2025年2月7日の記事より転載させていただきました。